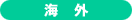
上海株式市場、大幅安8.26%安6月5日0時18分配信 Record China
最終更新:6月5日0時18分 上海株式市場の狂乱
━━━━━━━━━ ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 平成19年(2007年) 6月5日(火曜日) 通巻第1820号 (6月4日発行) △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 上海株式市場の狂乱株価、まだまだ収まらず
バブル崩壊は世界史的規模になるかもしれない ********************************
まだ誰も逃げ出していない。
ババ抜きゲームのババは、まだ宙を舞っている。
株の突然の劇的な収縮があるだろう、とグリーンスパンが演説しても、温家宝首相が憂慮を表明し、周小川(人民銀行総裁)がバブル崩壊の懸念を言い募っても、いまの株高はどうにも止まらない。
「もはや制御不能だ」とメリルリンチの中国支社長は言う(ブルームバーグ、5月25日付け)。
「ペトロ・チャイナ」の持ち株を市場に売った「フィデリティ」(全米
最大の投資信託)の理由は、米国内の人権批判の高まりから、世論に配慮してのことであり、株が暴落する予兆を感じたからではなかった。 ペトロ・チャイナは、人権弾圧の著しいスーダンで石油を採掘している国有企業。中国メジャーを代表する企業だ。
それにしても中国の株式はいつまで、どこまで暴騰をし続けるのだろうか?
「これは完全にバブルと断定できる」とは李嘉誠のことばである。
日本のGDPの57%にも迫った中国経済。しかし、中国の株式取引が、日本を上回っていると聞けば、異常というほかはない。(日本のGDP4・5兆ドルに対して中国は2・6兆ドルまでに猛追。株式売買はたとえば、この4月1ヶ月だけで6453億ドルvs日本のそれは5124億ドル)。
だからバブル崩壊は必ず来るのである。
しかし、当面は株式は高騰を続けるだろう。
理由は、一日20万人とも30万人ともいわれる新規の市場参加者が、証券会社に口座を開設しているように、いったん火のついたブームを冷却化することは難しい。
中国語でいう「株民」(株式投資家)はついに2千万人に達したと推測され、しかも貯金を取り崩しての株式参加が目立ち、国民の貯金残高が激減していることが分かった。 また中国の金融機関、保険基金もひそかに株式投資に参入している。
▼欧米金融機関がバブルに拍車をかけているのが実態 UBS(ユニオンバンク・オブ・スィス)は中国ベンチャー企業の上場
に幹事役を射止めた。 ゴールドマンサックスにつづいて欧米の大手老舗銀行が中国企業の上場を引き受けるのである。
青海省にある「西部鉱業」は、上海証券取引所に上場が決定(6月4日)、UBSが幹事行となって、5億7500万ドルを投資家から掻き集める。
UBSの手数料は1・5%で、8700万ドル(邦貨換算104億円)。 2006年からの夥しい中国企業の上海(ならびに深センへの)上場で、すでに410億ドルが資金調達された。
それ以前、7年間の蓄積実績額を僅か一年で更新したのである。 07年単独でさらに260億ドルが調達される予定で、上場予定企業リストが出回っている。新規に調達される株式の時価発想総額だけでもイタリアの総額を抜く勢い。
ゴールドマンサックスは、すでに中国第2位の生保「平安保険」の株式公開の幹事役をつとめ、53億ドルをかき集めた。
平安保険は温家宝首相夫人と息子が“特殊な関係”をむすぶ政治銘柄としても知られる。
これは香港に上場されたCITIC(59億ドル)につぐ規模のもので、
同GSは、さきにも「交通銀行」の上場に際しての顧問をつとめている。 四大銀行についで民間最大手の「交通銀行」は33億ドルを調達した。 まだまだ狂乱株価の醜態な宴が続くだろう。 |
沖縄タイムス 2007年6月3日(日) 朝刊 1面
「軍命が死を強要」/「集団自決」シンポ
体験者、再び証言/検定の問題点を論議
文部科学省の教科書検定で沖縄戦の「集団自決」の記述から「軍命」削除を求める検定意見がついた問題をテーマに、シンポジウム「挑まれる沖縄戦―『集団自決』検定を問う」(主催・沖縄タイムス社)が二日、那覇市の県青年会館で開かれた。「集団自決」体験者の金城重明さん(沖縄キリスト教短期大学名誉教授)が「軍の命令以外に住民の死はありえない」とあらためて軍命があったことを証言した。続くシンポジウムで研究者らが検定の問題点について論議。約二百七十人の参加者からは戦争体験を正しく引き継ぐ大切さが指摘された。
講話した金城さんは、一九四五年三月、渡嘉敷島の「集団自決」を体験。「米軍上陸の一週間前に手りゅう弾が日本軍から住民に渡された。一木一葉まで日本軍の指揮下だった。村長といえど、住民に死を強要することなどできなかった」と語り、軍命による悲劇であることを強調した。
金城さんは当時十六歳。「スパイ容疑で日本軍が住民や朝鮮人軍夫を処刑した。島に日本軍がいる中、米軍が上陸し、離島の狭い空間で精神的にも追い詰められていき、死につながった。軍隊のいたところでしか集団死は起きていない」と語った。
講話後のパネルディスカッションでは高嶋伸欣琉球大学教授、安仁屋政昭沖縄国際大学名誉教授、屋嘉比収沖縄大学准教授らが教科書検定の実態や沖縄戦の「集団自決」について議論を深めた。諸見里道浩沖縄タイムス社編集局長がコーディネートした。
高嶋教授は「沖縄がしっかり意思表示すれば、検定意見を変えさせることは可能だ」と述べ、検定撤回に向けた取り組みの必要性を訴えた。
フロアからの意見で、現職教員が「戦争体験に全く興味を示さない子どもたちがいる」と語るなど、風化が叫ばれる沖縄戦を継承する難しさがあらためて指摘された。
◇
「集団自決シンポ」が行われることは一昨日の夕刊報道で知ってはいたが、まさかこのように大きく取り扱われるとは。
1面のみならず、21、20面でも大きく取り上げられ「集団自決」問題に対する沖縄タイムスの並々ならぬ、というより,必死の態度が分る。
『鉄の暴風』の出版元である沖縄タイムスは、ある意味「大江・岩波裁判」の当事者だ。 むきになって世間を煽るのもやむを得まい。
シンポでは「集団自決」体験者の金城重明さんが
「軍の命令以外に住民の死はありえない」
「米軍上陸の一週間前に手りゅう弾が日本軍から住民に渡された。一木一葉まで日本軍の指揮下だった。村長といえど、住民に死を強要することなどできなかった」とあらため証言した。
4月1日の東京新聞のコラム筆洗(文末に掲載)で、金城さんの悲惨な体験は次のようにも紹介されている。
≪当時十六歳の金城さんには手榴弾が回ってこなかった。だから二つ年上の兄と一緒に泣き叫びながら、石を持った両手を母親の上に打ち下ろした。次に九歳の妹と六歳の弟の命も絶った。どうやったのか記憶はない。≫
16歳と言う多感な年頃で、このような苛酷な体験をされた金城さんには、気の毒とか同情とかの言葉はかえって失礼だろう。
言葉を失うと言うのが正直な気持ち。
金城さんの「証言」が、「軍命令があった」説の証拠にあたるかどうかは係争中の司法の判断に委ねたい。
記録保存として、沖縄タイムス21・20麺の記事も引用しておく。
2007年6月3日(日) 朝刊 21・20面
厳しい真実証言/「歪曲」に危機感
「軍命がなければ住民は集団死を選ぶことはなかった」。体験者は静かに語り、「過去の歴史やいまの教育行政に対するうそを見逃さしてはいけない」と研究者が力強く呼び掛けた。二日、那覇市の県青年会館で開かれたシンポジウム「挑まれる沖縄戦―『集団自決』検定を問う」では熱心な意見が交わされ、会場からは「まだ間に合う。沖縄戦の正しい姿を教科書に取り戻そう」との声も上がった。
「私が体験した時は十六歳の少年だった。あの生き地獄から六十二年間、今日まで生かされている」。渡嘉敷島でいわゆる「集団自決」を体験した金城重明・沖縄キリスト教短大名誉教授は、訥々と話した。
「兄と二人で母や弟、妹に手をかけ、自分たちの順番を待った」。重く、厳しい真実をどう話せばいいのか。考えが行きつ戻りつする。「決して自発的な死ではない。日本軍の命令、強制、抑圧によって死に追い込まれたんです」。一番伝えたい思いが、何度も口をついた。
パネルディスカッションでは高嶋伸欣琉大教授が、なぜ今年の検定で歴史教科書の「集団自決」の記述から「軍命による」の主語が消されたのか、背景を解いた。
文科省は「集団自決」訴訟を理由に挙げているが「訴訟は二年前に提訴された。安倍内閣の方針におもんぱかったのでは」と指摘、「教科書が印刷されるのは年末。県民が声を上げ、全国を動かせばまだ修正させることは可能」と呼び掛けた。
安仁屋政昭沖国大名誉教授は「合囲地境(自陣が陸海空ともに敵軍に囲まれている状態)」という言葉を引き合いに、軍命の存在を裏付けた。「『合囲地境の状況で、民政は存在しない』のが日本軍の常識だ。渡嘉敷、座間味はまさにこの状況だった。大局から見ればすべて軍命だった」と語った。
一九八二年の教科書検定でも、日本軍による沖縄戦での住民虐殺の記述が削られた。屋嘉比収沖縄大准教授は当時と現在の違いとして「戦争体験者が減少した沖縄社会の変化」を挙げた。
「非体験者がその次の世代にいかに沖縄戦を伝えるかが課題」と述べ、「八二年当時は教科書検定をきっかけに、県史が売り切れた。今回の危機も、沖縄戦を学び直す機会に」と提案した。
◇ ◇ ◇
聴衆「全国に届く機運を」
「この流れを止めなければ」「若い世代につなぐ教育とは」―。フロアの参加者からは、高校の歴史教科書から「軍関与」が消されたことへの憤りや、沖縄戦の事実を語り継ぐという重い課題について、さまざまな意見が聞かれた。
「沖縄戦に関心を持つ生徒と、そうでない生徒の二極化が進んでいる」。うるま市の高校教諭知念勝美さん(37)は語気を強めた。
学校現場で感じるのは、格差社会が進む中で、親に大事にされず、人とのかかわりが希薄な生徒が増えたことだ。「そんな子どもたちに沖縄戦の背景や証言者の話を聞かせても心に入ってこない。証言者が減っているという量の変化と同時に、若い世代の質の変化という現実を認識して対応することが大事だと思う」
バスガイドの仲間静香さん(32)=宜野湾市=は、県外の修学旅行生を戦跡に案内するときに金城重明さんの体験談を紹介する。「県外の子は沖縄戦を熱心に勉強しているが、県内での平和教育はどの程度行われているのか。戦争体験者がいなくなった後、誰がどう伝えていくのか危機感を感じる」
宜野湾市の会社員池田紘子さん(23)も「体験者がいなくなる十年後、二十年後には『軍命がなかった』が当然になってしまう。教科書から事実を削らせてはいけない」と話した。
「教科書検定はすきをつかれた」と指摘する恩納村の造園業伊波保人さん(51)は「こうしたシンポも自己満足に終わってはいけない。知らない人、無関心な人の目も引く伝え方を考えなければいけない」と訴えた。
高校の社会科教員を目指す琉球大学四年の松田浩史さん(24)は「体験者の話で分からないことも多かった。疑問をきちんと自分なりに調べ、伝えることを常に意識していきたい」と語った。
名護市の金治明(キム・チンミョン)さん(56)=在日朝鮮二世=は、政府が歴史を書き換えようとする現状に「ぜひこの流れを止めなきゃ」との思いで駆けつけた。「県内の盛り上がりが弱い感じがして気になる。この問題が全国に届いてほしい」と話した。
市民団体、撤回へ意欲
文部科学省は二〇〇八年度から使用される五社七冊の日本史A、Bで「集団自決」について、日本軍の関与を記した申請段階の表現の削除・修正を教科書会社に求めた。
これまでは日本軍の関与を明記してきた教科書会社側も今回は、文科省の修正に応じた。
これに対し県内では反発が強まっている。仲井真弘多知事が「軍命」削除に疑義を唱え、県内の市町村議会では検定意見の撤回を求める意見書の採択が相次いでいる。公明党県本部も文科省を訪れ、検定意見の見直しを訴えた。
市民団体や労組は「沖縄戦の実相をゆがめる行為だ」と抗議。「沖縄戦の歴史歪曲を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会」や沖教組、高教組が中心となって、軍関与を記した申請時の表現に戻すよう求めた。
「すすめる会」などは九日に五千人規模の「沖縄戦の歴史歪曲を許さない!沖縄県民大会」(主催・同実行委員会)を県庁前の県民広場で計画。
県議会に対し検定撤回の意見書決議を求めていく方針だ。
県議会は一九八二年に文部省(当時)が今回と同様に「住民虐殺」記述を削除しようとしたことに対し、全会一致で意見書を採択。記述を復活させた経緯がある。このため同実行委は県議会の動きに強い期待を寄せている。
市民団体などは、教科書が印刷され始める秋口まで「二段、三段構えで」運動を強め、「軍命」関与の記述の復活を目指していく。
◇
次回の裁判から、愈々本裁判の最大の見せ場とも言うべき証人尋問が始まる。
金城重明さんもその証言者の一人。
次回 第10回期日の予定
7月27日(金)証人尋問
証人 皆本義博氏
証人 知念朝睦氏 宮城晴美氏
次々回 第11回 期日の予定
9月10日(月)証人尋問 沖縄に出張尋問の予定
証人 金城重明氏
第13回期日の予定
11月9日(金)証人尋問
証人 梅澤裕氏 赤松秀一氏
証人 大江健三郎氏
「座間味島の集団自決は梅沢隊長の命令だった」、との証言を翻し「軍命があった」というのは間違いだったと書き残した故宮城母初江さん。
その遺言を「母の遺したもの」として著した宮城晴美氏も証言台に立つ。
◆「母の遺したもの」http://www.zamami.net/miyagi.htm
当然原告側の梅沢、赤松両氏も証言するが、被告の大江健三郎氏は何故か証言出廷を拒んでいると聞く。
以下南木さんのサイトより引用。
「被告大江健三郎の証人尋問は、その必要性を、裁判官と双方の弁護士との進行協議において裁判長自身が認めておられ、裁判官によって必要との判断が下されています。」
「・・・大江氏がこれを拒み続ける場合は、拘引の可能性もあります。拘引されたくなければ別紙、朝日の読者に対して行った約束、
http://blog.zaq.ne.jp/osjes/article/31/
を守って出廷するべきだと言わねばなりません。」
被告大江健三郎は、本件訴訟提起直後、朝日新聞のコラム「伝える言葉」にこう書きました。「求められれば、私自身、証言に立ちたいとも思います。その際、私は中学生たちにもよく理解してもらえる語り方を工夫するつもりです」と約束しています(甲B56として提出済み)。
言葉に矛盾する行動は、その言葉を蔑ろにすることであり、なによりも言葉を発した者に対する信頼を失わせます。それが著名なノーベル文学賞受賞作家とあれば、およそ「言葉」に対する信頼は地に墜ち、出廷しないことで日本の恥を世界に晒し、ノーベル文学賞にも泥を塗る事になります。
被告大江健三郎は、「伝える言葉」で述べた自らの言葉を裏切るべきではありません。
以上の点について、今回「原告準備書面(8)」において以下のように詳しく言及しています。ここに再掲しておきます。
全文は
http://minaki1.seesaa.net/
にあります。
◆大江健三郎が出廷宣言をしている新聞記事http://blog.zaq.ne.jp/osjes/article/31/
◇
◇大江氏と岩波書店、沖縄戦めぐり検定で文科省に抗議
(2007年04月04日18時47分 朝日新聞)
(略) 声明では、大阪地裁での訴訟がまだ続いており、証人尋問もされていないことや、集団自決で軍の強制を示す文献や資料も多数あることを指摘。「裁判を参照するのであれば、被告の主張・立証をも検討するのが当然だ」と訴えている。
大江氏と岩波書店を代表して会見した月刊誌「世界」の岡本厚編集長は「訴訟では守備隊長による命令があったかどうかが争われているが、より大きな日本軍の関与は問われていない。にもかかわらず、日本軍の強制全体をひっくり返そうとしている」と述べた。
◇
>裁判を参照するのであれば、被告の主張・立証をも検討するのが当然だ
そう言いながら大江氏は卑怯にも証人尋問の出廷を拒否していると聞く。
実際に法廷を傍聴した人の中からは、
「法廷へも出ないで、減らず口をたたくな!」
という声も挙がっており、
「大江健三郎を法廷に引きずり出す運動」も行われている。
>より大きな日本軍の関与は問われていない。にもかかわらず、日本軍の強制全体をひっくり返そうとしている
キタ! 「より大きな日本軍の関与」と来た。
「日本軍の強制全体」とまで来たか。
次は「日本国全体の強制」とまで来るののだろう。
だったらなお更、前線の一守備隊長に「日本軍の強制全体」の責任を背負わせて、「軍命令で集団自決をさせた」と個人攻撃はできないはずだ。
個人名を挙げて守備隊長を糾弾した「大江、岩波コンビ」は潔く謝罪べきだ。
さもなくば法廷で堂々と証言すべきだろう。
醜悪なるノーベル賞作家は腐臭を撒くだけ撒き散らし、それに対する法廷での証言を卑怯にも拒否している。
梅沢、赤松両原告も、被告側の金城さんも宮城さんも証言台に立つという。
大江さん、恥を知るなら法廷で証言しなさい!
筆洗 東京新聞
2007年4月1日
六十二年前、目の前で起きたことが金城(きんじょう)重明さんのまぶたには焼き付いている。村長の「天皇陛下万歳」の三唱を合図に、多くの家族が次々と手榴(しゅりゅう)弾を爆発させた。約一週間前、日本軍が一人に二個ずつ配った。一つは敵に備えるため、もう一つは自決用だったという▼沖縄県に属する慶良間(けらま)諸島最大の島、渡嘉敷(とかしき)島での出来事だ。当時十六歳の金城さんには手榴弾が回ってこなかった。だから二つ年上の兄と一緒に泣き叫びながら、石を持った両手を母親の上に打ち下ろした。次に九歳の妹と六歳の弟の命も絶った。どうやったのか記憶はない▼米軍が三月下旬に慶良間諸島、四月一日に沖縄本島に上陸して始まった沖縄戦は「軍民一体」の戦争だった。渡嘉敷島では軍の指示を受けた村長のもと、住民は日本軍の陣地近くに移動させられ「ともに生き、ともに死ぬ」と教えられた。手榴弾の配布は「自決せよという言葉以上の圧力だった」という▼文部科学省による高校教科書の検定では、集団自決を日本軍が強制したという趣旨の記述が修正された。例えば「日本軍のくばった手榴弾で集団自害と殺しあいがおこった」と▼同省は「近年の状況を踏まえると、強制したかどうかは明らかではない」と説明している。自由意思とでも言いたいのだろうか。金城さんは「歴史の改ざん。軍の駐留先で集団自決が起きている。本質はそこにある」と訴えている▼金城さんにとって、語りたい過去ではないはずだ。過ちを繰り返さないため、歴史の証言者になっている。耳を傾けたい。
健康食品にステロイド剤・中国製、幼児に被害
厚生労働省と茨城県は31日、アトピー性皮膚炎に効くとされる中国製の健康食品を服用した同県内の幼児が、顔がむくんで丸みを帯びる「ムーンフェース」や、体毛が濃くなる「多毛」の健康被害を発症したと発表した。幼児は快方に向かっている。
同省や県によると、商品名は「適応源」。ステロイド剤の一種「ベタメタゾン」が検出された。〔共同〕(00:02)
◇
何事も問題があまり極端に走ると、怒りを通り越して笑うしかない場合がある。
最近の一連の中国製商品の偽物報道がそうだ。
「健康の為には命も要らない」という笑い話があるが、最近の中国製商品はこれが笑い話でないから恐ろしい。
「健康食品」を食べた幼児の顔が膨らんで毛が生え出したら笑ってはおれないだろう。
中国の偽商品を一々取り上げていたら一冊の本が出来るくらいなので、当日記では文末の関連ニュースリンクに譲りたい。
そして、今朝の琉球新報の共同記事にあった「笑い話」を記事のオチとして紹介する。
「笑えない」と文を結んでいる記者さんには申し訳ないが、正直爆笑してしまった。
「農民が稲を植えたが芽が出ず、服毒自殺を図ったが死ねなかった。助かったことを喜んだ妻と祝いの酒を酌み交わしたら二人とも死んだ」
暫く前に中国で流行った小話だ。稲も薬も酒も偽物だったと言うのがオチ。
コメ、薬、酒の偽物は実際に氾濫しており笑えない。
|
沖縄タイムス 2007年6月1日(金) 朝刊 36面
あす「集団自決」シンポ
沖縄タイムス社は二日午後二時から、那覇市久米の沖縄県青年会館で緊急シンポジウム「挑まれる沖縄戦―『集団自決』検定を問う」を開催する。高校歴史教科書の「集団自決(強制集団死)」をめぐる検定について、体験者や識者を交えて考える。入場無料、同午後五時まで。
渡嘉敷島での「集団自決」を生き延びた金城重明さんの講話、安仁屋政昭・沖縄国際大名誉教授▽高嶋伸欣・琉球大教授▽屋嘉比収・沖縄大准教授によるパネルディスカッションがある。コーディネーターは諸見里道浩・沖縄タイムス編集局長。
◆
「軍命令による集団自決」という神話が、初めて活字として現れたのは沖縄タイムス社が発刊した『鉄の暴風』においてである。
『鉄の暴風』の初版は昭和二十五年、朝日新聞により出版されたが、二版より沖縄タイムスに引き継がれ現在は絶版になっているという。
この本はその杜撰な伝聞記事が各村史に転記され、更には同記事を検証無しに鵜呑みした高名なノーベル賞作家の著書に飛び火して教科書に記載されるまでなった。
『鉄の暴風』がいかに杜撰な伝聞記事に溢れていたかは、次に挙げる一例だけでも充分であろう。
問題の渡嘉敷、座間味両島の守備隊長は赤松少尉と梅沢少佐だった。
同書は守備隊長の一人梅沢少佐に関して次のように書いた。
「隊長梅沢少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した」と。
ところが、現在もなおご健在の梅澤氏は、『鉄の暴風』を引用したメディアのバッシングを受けて、その後職も転々とし、またご家庭も崩壊状態になったという。
隊長梅沢少佐とは、何よりも今回の「岩波・大江訴訟」原告の一人である。
『鉄の暴風』で『不明死を遂げたことが判明した』として死亡宣告された梅沢氏その人なのだ。
終戦間も無いない時期で取材にハンディがあったとは言え、最重要人物の生死を間違えるような杜撰な伝聞取材だった。
その後沖縄タイムスは梅沢氏の生存を知り、その部分は削除し、現在「鉄の暴風」は絶版になっているので今回の訴訟の被告にはなっていない。
だが、「鉄の暴風」をネタ本にしたのが大江健三郎の「沖縄ノート」(岩波書店刊)である以上当事者の一人であることに違いない。
沖縄タイムスは沖縄の各市町村長にアンケートをとり、「歴史歪曲による教科書の書き換えは反対」と言った運動を各議会に煽り決議案成立に追い込むキャンペーンを図っている。(下記リンク④参照)
その結果「集団自決」の当事村である、渡嘉敷、座間味両村議会まで「反対」議決をするにまで至っている。(下記リンク①参照)
一方上記記事のような「プロ市民集会」を開いて「世論」あおりに必死である。(下記リンク②参照)
プロ市民団体の中心は、高嶋琉球大教授らだが、彼らが「シンポ」という名の「市民集会」活動に懸命なのは、「軍命令」が否定されれば、この作り話を真実として活字にした新聞社も、学説の根拠とした学者も、全てその立場がなくなってしまうからだ。(下記リンク③参照)
「集団自決の軍命はあった」という命題は、沖縄のサヨク勢力にとってもはや歴史の解明ではない。
命を賭してでも護るべき「イデオロギー」になりはててしまっている。
しかし、「軍命令」があったという客観的証拠はない。
あるの「従軍慰安婦問題」と同じく「証言」だけで、それをバックアップするのが「市民集会」であり「村議会議決」である。
だが、歴史の真実を解明するのは、市民集会でもなければ村議会の議決でも無いはずだ。
◆①座間味・渡嘉敷 撤回要求へ/「集団自決」軍関与削除
|
大江健三郎・岩波書店沖縄戦訴訟連絡会(「傍聴記録」より抜粋)http://www.sakai.zaq.ne.jp/okinawasen/index.html
大江・岩波側は、日本軍は「軍官民共生共死の一体化」方針の下に、総動員作戦を展開し、村民に軍への協力を村長、助役、兵事主任、防衛隊長などを通じて命令していた。この状態を安仁屋名誉教授は「合囲地境」と説明しておられる。
軍は、米軍が上陸した場合には村民とともに玉砕する方針をとり、捕虜になることを禁じ、捕虜となったとの理由で処刑された人もいる。当時座間味島及び渡嘉敷島の日本軍の最高指揮官は梅澤隊長及び赤松隊長であり、日本軍の指示・命令、すべて梅澤・赤松隊長の指示・命令であったというべきである。。
◇
5月25日、沖縄集団自決冤罪訴訟第9回口頭弁論が大阪地裁で行われた。
◆沖縄集団自決冤罪訴訟第9回口頭弁論http://blog.zaq.ne.jp/osjes/
裁判を傍聴した南木さんの記録によると、
被告側は≪「米軍の捕虜となることを禁じていた証拠がある」とか、「現に捕虜となったと言う理由で処刑された例がある」
等々の本件と直接関係のない弁論を終始展開した。≫
≪梅澤、赤松の両隊長が自決命令を出したかどうかと言う、この裁判の最大の争点について、結局何も新しい弁証を展開する事ができなかった≫という。
いくら探しても、両氏が自決命令を出したという客観的証拠が見つかっておらず、被告側の唯一の論拠が証言だけという点で、本訴訟は「従軍慰安婦」問題と相似形をなす。
「被告側代理人弁護士は既に追い込まれ、困り果てている・・・」(上記サイト)という感想は否めない。
>村民に軍への協力を村長、助役、兵事主任、防衛隊長などを通じて命令していた。この状態を安仁屋名誉教授は「合囲地境」と説明しておられる。
証言以外では、結局被告側が「軍命はあった」とする唯一の理論的拠り所は安仁屋名誉教授の「沖縄=合囲地境」論なる聞きなれない概念しかなくなったのだ。
「合囲地境」とは戦争地域では「直接軍の命令がなくとも役所の指示でも全ては軍の命令だ」というまことに乱暴な説である。
この論からいけば「直接の軍命のある無しは問題ではない」という粗雑な主張になる。
>日本軍の指示・命令、すべて梅澤・赤松隊長の指示・命令であったというべきである。。
粗雑な理屈で「命令であったというべきである」と云わざるを得ないところに被告側の焦りが垣間見れる。
「合囲地境」ついては『「集団自決」 各紙なで斬り 朝日編』で詳しく述べた。
煩雑を承知で引用すると、
≪今朝の社説のタイトル「集団自決―軍は無関係というのか 」でも最近の朝日の弱気が現れている。(2007年3月31日朝日社説)
「集団自決」は「鉄の暴風」を降らしたと言われる圧倒的物量に勝る米軍の総攻撃を直前にした村民があまりにも脆弱な日本軍の守備隊の状況にパニックになった結果だと当日記は推察する。
当然軍に無関係だとは言い切れない。
米軍の総攻撃を目前にパニックになって「集団自決」したとなると無関係とはいえないだろう。
朝日が言う「広義の関係」がここでも顔を出してくる。
「集団自決はすべて軍に強いられた」と言っているわけではない。
「自決を強いられたとしか読めない」
「軍隊が非戦闘員に武器を手渡すのは、自決命令を現実化したものだ」といった主張も裏返すと「軍命令は無くとも戦時中の行動は全て軍命令と同じ」だという理屈に支えられている。
だったら、貧弱な武器で島中を取り囲んだ米軍に決死で立ち向かおうとした梅沢、赤松の若き両司令官(座間味島と渡嘉敷島の)を「住民に集団自決の命令を下した極悪非道の男」として糾弾するいわれはないはずだ。
ましてや教科書に「集団自決」があった事はともかく「軍命令でやった」とは記載すべきではない。
この「直接の軍命令が無くとも命令と同じ」と言う理屈を最初に言い出したのは、安仁屋沖縄国際大学名誉教授である。
同氏は沖縄タイムス(2005年7月2日)の[戦後60年]/[「集団自決」を考える](18) /識者に聞く(1)/安仁屋政昭沖国大名誉教授・・・と言う特集記事で記者の質問に答えた次のように語っている。
http://www.okinawatimes.co.jp/sengo60/tokushu/jiketu
20050702.html
「『集団自決』は日本軍と住民が混在していた極限状態で起きている。沖縄戦は、南西諸島が米軍によって制海権も制空権も完全に握られ、民政の機能しない戒厳令に似た『合囲地境』だった。その状況下では、駐留する日本軍の上官が全権を握り、すべてが軍の統制下にあった。地域住民への命令や指示は、たとえ市町村職員が伝えたとしてもすべて『軍命』として住民が受け取るような状況があった」 ・・・
*
>「地域住民への命令や指示は、たとえ市町村職員が伝えたとしてもすべて『軍命』」
・・・と言う、いわば「広義の軍命令」を言い出した安仁屋教授の理屈の根拠はどうやら『合囲地境』と言う聞きなれない言葉にあるらしい。
戦時中の沖縄を「戒厳令」状態と仮定しようとしたが2・26事件以来日本で戒厳令が引かれた例はない。
安仁屋教授はそこで日本の戒厳令においては、「臨戦地境 」と「合囲地境 」の2種類の戒厳地域区分が存在するということに着目した。
特に後者の「合囲地境 」 とは「敵に包囲されている、または攻撃を受けている地域で、一切の地方行政・司法事務が当該地域軍司令官の管掌となる」とあるのでこれを沖縄戦に適用しようと考えた。
だが、実際には日本では法制度上は存在してもこれが適用された例はない。
勿論「沖縄戦」にも「合囲地境」はしかれていない。
安仁屋教授個人が勝手に「合囲地境とみなした」に過ぎない。
この伝でいくと、沖縄だけではなく、1945年の日本列島全域、またソ連参戦後の樺太や千島列島は外形的には敵国に包囲され攻撃されているという合囲地境の条件を満たしており、樺太や千島で自決した住民も、いや日本国中で自決した人全てが日本軍の命令で死んだ事になる。≫
軍命令があった」という客観的証拠が無いとわかると、「合囲地境」なる概念を持ち出して、「直接軍命があったかどうかは問題ではない」、「広義の軍命」があったというに及んで、「従軍慰安婦問題」と全く同じで、被告側の焦りを感じてしまう。
「駄作、愚作といったレベルではない。もはや、井筒は映画制作を今後一切放棄すべしと思わせるほど全編、半日思想一色に塗られた吐き気を催す作品である。これほど前に、極端に偏向した映画をボクは観たことがない。大げさではなく、朝鮮労働党が作る洗脳メディアとしての将軍様マンセー映画と何も変わりはしないと言って構わない。
(略)
在日=善。人の心がわかる、素晴らしき民族。日本人=悪。侵略戦争を冒した愚かで汚い人間。「LOVE&PEASE」は、この実に安易で無知な歴史観と思想を押しつけるプロパンダ映画と断言していい。在日の人々が日本で暮らしていく中で、大小の差別を受けることはあるだろう。ましてや、本作の描く74年当時は、現在より露骨だったのかもしれない。
が、映画人として表現者として、井筒が無様なまでのバランスを欠いた作品を作ったことはまったく別問題だ。
(略)
在日と同じ弱者であるとでもいいたげな、孤児院育ちの藤井隆演じる日本人青年の意味不明さ。アンソンの子供が不治の病であるという安直な設定。何もかもが、一方的な被害者意識に立ったゴミ映画。井筒をはじめこの映画に関わった全てのスタッフ、全ての俳優をボクは心底嫌いになった。 」(ヤフー映画評より)
こんなにまで悪評プンプンの反日映画・『パッチギ!LOVE&PEACE』が文化庁の推薦を受け3000万円の支援を受けたと言うから驚いた。
「LOVE&PEACE」さえ声高に叫べば、文化庁の推薦を受けられるなら文化庁推薦映画なんて素人でも簡単に作れる。
詳しくは「この国は変だ!よーめんのブログ」さんでどうぞ。http://youmenipip.exblog.jp/5510731
文化庁への電凸の音声は見事です!
◆参考エントリ:
映画・『パッチギ!LOVE&PEACE』 どうして「愛」と「平和」なの?
◆「中国と対等の力を」李登輝氏が講演で日本に注文へ (読売 07/6/2)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070602i501.htm?from=main5
来日中の李登輝・前台湾総統(84)が、7日に都内で行う講演の内容が明らかになった。
本紙が入手した「2007年とその後の世界情勢」と題する講演原稿によると、李氏は、米政権がイラク問題などで弱体化するなか、「長期的に見て、中国と米国による太平洋制海権の争奪戦は避けられない」として、日本に対し「安倍政権時代に中国と対等に張り合う力を持つよう努力すべきだ」と注文をつけている。
明言は避けているものの、安倍政権が進める憲法改正作業や集団的自衛権行使に向けた動きなどに対し、支持を示したものと見られる。
原稿には、中国の金融危機の可能性を指摘するなど、「対中けん制」発言も随所に見られ、李氏来日に反対し、「政治的発言」に神経をとがらせる中国政府が反発するのは必至だ。
李氏の訪日は、総統退任後3回目だが、これまでは日本政府に配慮し、講演や記者会見は行わなかった。「世界情勢」に関する講演は、都内のホテルで政財界人ら約1200人を招いて行われる。
◇
>「政治的発言」に神経をとがらせる中国政府が反発するのは必至だ。
読売は信頼できると思って、前もって講演の原稿内容を伝えたと思われるのに。
朝日を真似て、中国の「神経」を心配するのは大きなお世話だ。
少なくとも北京オリンピックまでは万事まるく抑えたいのが中国の本音。
挙げたくも無い拳を無理やり挙げさせるつもりなのか。
中国の「家庭の事情」を読み取った上での、李氏の突然の「靖国参拝希望」であり 「対中けんせい」等の「政治的発言」の筈。
これらの先制攻撃で李氏は日本国内での(政治的)発言、行動を既成事実として着実に作って行く考えと当日記は推察する。
【追記】08:52
日本のマスコミよ、私人である李登輝氏の発言で一々中国の顔色伺うような暇があるなら、中国の大学教授、知識人たちの発言にも目を配れ。
彼らが日本の大学やマスコミで行っている日本及び台湾非難は、もっと露骨で激しい。
何度でも言おう。
日本は中国の属国ではない。
◇
これからは日本の番だー李登輝氏のメッセージを受け
台湾研究フォーラム会長 永山英樹
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/
本日都内で催された後藤新平賞の授賞式に出席した李登輝前総統は、「農業学者として台湾経済の発展に寄与できたことは最高の喜びであり、総統として一滴の血も流さずに『静かな革命』と呼ばれた台湾の民主化を行うことができた。新たな台湾政府を設立できたのは私の一生の誇りだ。後藤新平が進めた台湾開発の基礎の上に、民主化
を促進した私とは無縁ではない」と、受賞の喜びを語った。
後藤新平総督府民政長官をはじめ、戦前に台湾の建設に尽くした多くの日本の先人にとり、これほど嬉しい言葉はないのではないかと思う。
さて式典後に開かれた記者会見で李氏は、「日本と台湾は生命共同体だ。台湾にいったん何かあればすぐ日本にも響く。台湾海峡問題も日本の大きな一つの問題だ」とした上で、「二国は外交関係がなく、単なる赤の他人みたいな形になっている。赤の他人ではいざというときに何もできない。こういう困難を抱えつつも(日本の)政治家は台湾と付き合っていくべきだ」と強調した(日台関係強化の問題に関する櫻井よしこ氏の質問を受け)。
「台湾は日本の生命線である」と初めて唱え、日本人の覚醒を促し続けてきたのが李氏である。そしてそのような李氏の日本への影響を恐れたのは中国政府だが、その中国政府に配慮して、李氏の日本での発言に規制を加えてきたのが日本政府だった。
つまり敵への警戒を懸命に呼びかけてくれる友に対し、敵を恐れてその口を封じると言うのが、これまで日本人がやってきたことなのである。
しかしもう過ぎたことである。李氏は今日、このような形で眠れる日本国民に対し、メッセージを発してくれたのだ。まずは何よりも感謝しよう。
しかし感謝するだけではだめである。李氏は今日こうも言った。「自分はすでに政治的な力はないが、それでも個人として二国関係の促進には努力している」と。
これを聞いて奮起しない者は日本人ではない。これからは、いよいよ日本が「努力」する番なのである。(19.6.1)
平成19年(2007年) 6月2日(土曜日)
通巻第1815号 (6月1日発行)
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
(速報)
「わたしは後藤新平の台湾施政を民主台湾の政治の土台にした」
李登輝前総統、後藤新平賞受賞記念スピーチで強調
*********************************
6月1日午前、六本木の国際文化会館は早朝から異様な緊張に包まれた。
日頃ならのんびりとテラスで喫茶する外国人宿泊者、新聞をたたむ音しか聞こえないロビィの静けさ。誰もが愛でる日本庭園の美しさ。
独特の静謐は警備陣と報道陣によって一瞬に掻き消された。
第一回「後藤新平賞」に決まった李登輝前台湾総統が記念講演をするからである。
世界から報道陣がおよそ120名。SPが数名。台湾から随行してきたカメラとテレビクルーも目立ち、ぎっしりと会場の余地を埋めた。日本の台北特派員も随行してきている。
テレビカメラがずらりと会場の右側と後方を占め、身動きがとれないほどの熱気に溢れた。
参会者はイス席定員120名に対して200名以上。ぎっしりと立ち見も出たが、さらに一部は入場できなくロビィに屯する有様だった。
偶然、小生の隣席は竹村健一氏、すぐ二人して控え室にいる李登輝総統に挨拶に行った。
控え室には総統ご夫妻を囲んで中嶋峰雄氏、粕谷一希氏、金美齢女史、台湾から同行してきた黄昭堂氏ら。
会場には許世楷(台北駐日経済文化代表処代表)はもちろんのこと、岡崎久彦、櫻井よし子、大宅映子、日下公人、花田紀凱、塩川正十郎、住田良能(産経社長)、小田村四郎氏らの顔もあった。
授賞までの経過説明を主催者の藤原書店代表が述べたあと、粕谷一希(元『中央公論』編集長)が選考審査過程を披瀝され、受賞牌の贈呈。副賞はシチズンの置き時計で、理由は「シチズン」の銘々が後藤新平による由。
▼改革への情熱と先見性
以下は李登輝前総統の講演「後藤新平とわたし」の要旨である。
「後藤新平の生誕百五十年を記念して全集が藤原書店から刊行され、「後藤新平賞」が新設されたことは画期的で、新しい時代の指導者育成を目的とする栄誉に初回に輝けたことを光栄に思う。
後藤新平は1857年生まれで、1929年に没した。私は1923年生まれ、交差していないが、精神の空間で結ばれている。
後藤新平は1898年3月から1906年9月まで、8年7ヶ月を台湾民政長官として過ごし、未開だった台湾の近代化のために成し遂げた功績は大きい。その生い立ち、功績、人間としての偉大さを私は深く心に刻み込んできた。
後藤は貧窮のどん底から立ち上がり、医者から衛生局長となり、1895年児玉源太郎の推挙によって台湾へ赴任した。
かれの復員傷兵の帰国に際しての検疫能力を高くかったから、とされる。
当時の台湾は匪賊が跋扈し、ペスト、赤痢、チフス、毒蛇が蔓延して、不衛生極まりなく、漢族と原住民部族の対立があり、産業は未開のまま、およそ近代化には遠い状況だった。
後藤は台湾近代化、台湾の開発に何が目的であり、その目的達成のためには何が大切かを考えて、明治政府の全面的な支援の元に諸改革を実行に移した。
第一は人材の確保であった。1800人の無能の役人を馘首し、新しい人材を適所に配置した。この中には新渡戸稲造も含まれていた。
第二に匪賊対策を従来の路線から変更し、単に匪賊を退治するのではなく労働の現場へ配置しなおして、かれらを生産、建設に役立てて任務を教えた。
第三に「保甲制度」、つまり地方自治の確立である。
住民の自治を尊び、交通を整備し、戸籍制度の充実と整備をなした。同時に自治の責任を持たせた。
第四に劣悪な衛生環境を改善し、マラリアなどの退治のために血清の研究と同時に田舎にも医者を配置して政府派遣として医療行政を実地した。
都市部では下水道の整備を急いだ。
第五が教育の普及である。
(ほかの列強は現地植民地を搾取するばかりで教育をおざなりにしたが)日本は台湾の植民地経営を教育から開始したのだ。
第六に開発近代化の財源を確保するために地方債券を発行し、内地(日本)の国会の承認を得た。
これにより土地改革がすすみ、鉄道が敷設され、基隆港が整備された。
第七は「三大専売法」を施行させたことだ。
阿片,樟脳、食塩、酒、煙草が専売となり税金収入が公債の返済に充てられた。
第八に「台湾銀行」が創設されて台湾銀行券が流通、また「度量法」が統一され、それまで台南と台北で異なった重さや長さの図り方が統一された。
第九は産業の奨励で、砂糖、樟脳、茶、こめ、阿里山森林の開発が進められて開発が軌道に乗る。
第十は貿易の拡大であり、そのために外国資本が独占していた商船の運搬を民間にも広げた。
第十一に後藤の「南進政策」がある。
当時、アモイ、香港への投資も開始され、アモイには台湾銀行支店が設置を見た。
第十二に国民の生活習慣のなかで弁髪、纏足など悪習を禁止した。
後藤はその後、満鉄総裁として満州に赴くが、もし、台湾に留まっていれば、台湾の行政はさらに異なったレールを走ったことと思われる。
▼なぜ、日本人はああまで情熱的だったのか?
生誕百五十年を待たずに後藤新平の研究がおおいに進み、許文龍氏をして、
「台湾への政策は素晴らしかったけれども、なぜ、日本人はあれほどの情熱を燃やして台湾の近代化に努力したのか」と問いかけている。
とくに拓殖大学で、この研究が進められた。
池田憲彦前拓殖大学教授は「まず明治天皇の御叡慮があり、新しい版図への使命観があった。みずみずしい感受性と、ひるまない精神、つまり『肯定的思考』が多くの勇断を運んだと指摘している。
いま84歳になる私は、台湾人として生まれた悲哀と、同時に22歳まで日本人だった私が、日本の教育を受け、『肯定的人生』という人生観を体得して、農業の改革に着手し、その後、台北市長、台湾省省長を経て、副総統、そして十二年間にわたって総統として、一滴の血も流さないで台湾に民主化という“静かなる革命”をもたらすことが出来たことを一生の誇りとする。
これらは後藤新平の台湾施政への哲学的基礎の上になりたっており、今日の台湾の民主と繁栄が築かれてきたのだ。
その精神的な繋がりの空間で、世代と時間をこえての共通の価値があり、だから私は後藤新平を敬愛してきたのである」。
感動的な講演にしばし拍手が鳴りやまなかった。
李登輝氏の靖国参拝を巡る台中の異なる対応
台湾研究フォーラム会長 永山英樹
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/
昨日来日した李登輝氏が靖国神社への参拝希望を表明したことは、台湾でも随分話題になっているが、現地のテレビニュースでの取り扱いは、各局とも比較的に落ち着いたもので、本土派の民視の場合は、やはり靖国神社に「兄が祀られている」と言うことで、昨日はアナウンサーが微笑みを浮かべながら報道していた。今日は統一派のTVBSも、李氏が「兄の印象はフィリピンへ出征する前に家族で記念撮影をした六十年前のときのまま」と語って嗚咽したことを取り上げ、李氏が「真情を吐露した」と報じた。つまり政治性を抜きにした「暖かみ」ある報道が目立つのだ。
台湾の外交部も「個人の信仰を尊重する」として、李氏批判、靖国神社批判をするようなことはしていない。
それに比べて中国はどうか。やはり中国人と台湾人とは違うなと思う。
それと言うのは今日、この国の外交部スポークスマンは、李登輝氏の参拝問題に関し、日本政府への「強烈な不満」を表明したのだ。つまり「李登輝の訪日の目的は台独分子の勢いづけと日中関係の破壊にある。それを日本政府は許してしまった」と言うわけだ。そして「一つの中国の原則を堅持し、台独分子とその勢力にいかなる活動の舞台も提供してはならない」と。それから「日本側が台湾問題と歴史問題を適切に処理することは、日中関係の健康的な発展の基本条件だ」とも。
いったい何を言いたいのかよくわからない発言である。日本の首相が参拝するなら「中国人民の感情を傷つける」とか「日本軍国主義の復活だ」などと罵ることはできても、今回は台湾人の参拝問題だから、適当なセリフが見つからないのだろう。
おそらく李氏の参拝で、日本人が自信を回復するのが怖いのに違いない。日本軍国主義と台湾独立派の「結託」をつねに非難しているように、中国にノーを言う日本と台湾の連携を、この国が極度に恐れていることだけは確かだ。安倍首相が「日本は自由な国だから、私人として当然、信仰の自由がある。(李氏)ご本人が判断されることだ」と、中国に一切配慮のない発言を見せたことにも、相当刺激されたことだろう。
李氏の参拝希望表明で、日本では相変わらず「中国の反発必至」との報道も見られたが、今回の「反発」の場合に限っては中国の勝手な政治的都合によるものだから、日本人としてはいちいち歴史の贖罪意識を持つ必要はなさそうだ。
もっとも台湾でも、反靖国で売名に走る高金素梅議員はもとより、国民党議員が大騒ぎだ。「李登輝は歴史の罪人」などと李氏を罵っているが、やはり彼らは「中国人」だなと思う。これに対して台湾団結連盟の議員からは「兄を参拝するのは当然の人情」との反論が出たが、これが「台湾人」の落ち着きであり、良識である。
ところでTVBSの報道によると、日本の外務省も李氏に対し、「敏感な問題だから、靖国神社に関する発言はしないで欲しい」と頼んでいるのだとか。
それではそう言う外務省は、いったい「何人」なのだ。(19.5.31)
◇
李前総統の靖国参拝 「私人の信仰の自由」と首相
安倍晋三首相は30日夜、同日来日した台湾の李登輝前総統が靖国神社を参拝する意向を示したことについて、「李氏は私人として来日した。私人として当然、信仰の自由がある。本人が判断することだ」と指摘した。李氏の来日が日中関係に与える影響については「ないと思う」と述べ、明確に否定した。首相官邸で記者団に述べた。
また、塩崎恭久官房長官は30日の記者会見で、李氏の来日について、「今回の訪日は家族の観光旅行と学術文化交流が目的と聞いている。わが国の台湾に対する立場は日中共同声明にある通りで、李氏の訪日によって何ら影響を受けるものではない」と述べた。
(産経新聞 2007/05/30 19:43)
◇
>日本の外務省も李氏に対し、「敏感な問題だから、靖国神社に関する発言はしないで欲しい」と頼んでいるのだとか。
安倍首相の「李氏は私人として来日した。私人として当然、信仰の自由がある。本人が判断することだ」
との明確なる発言ににもかかわらず、
靖国について発言もするなと戯言をぬかす屈中外交官は即刻名前を挙げて首にすべきだ。
それに引き換え,当の李氏はまことに堂々としている。
30日午後、都内で記者団に対し
「中国が靖国問題(の批判の矛先)をわたしに持ってくるのはおかしい。全然事情が違う」と中国の筋違いな言いがかりを指摘していた。(5月30日 共同)
記者の質問に笑顔で答える台湾の李登輝前総統=30日午後、東京都江東区

|
記者の質問に笑顔で答える台湾の李登輝前総統=30日午後、東京都江東区 |
 |
「世界があっと驚く駅を造れ」。大風呂敷のあだ名で知られる鉄道院総裁、後藤新平の号令のもとで、大正3(1914)年に東京駅は完成した。全長335メートル、赤レンガを積み上げた巨大建築を目の当たりにして、人々は度肝を抜かれたに違いない。
▼明治の後半まで丸の内界隈(かいわい)には、茫々(ぼうぼう)たる草むらが広がり、夜になると大の男も1人では怖くて歩けなかった。開業後の1日の平均乗降客も1万人足らずにすぎない。93年後のいまでは、利用客は90万人をこえ、手狭に思えるほど。後藤は今日の混雑を見通していたのだろうか。
▼設計にあたったのは、日本近代建築の祖といわれる辰野金吾だ。もっとも「辰野式ルネサンス」と呼ばれたデザインは古くさいと、専門家の評価は意外に低かった。にぎわいのある八重洲側には乗降口がなく、日本橋や京橋方面からは、遠回りしなければならない不便な造りでもあった。
▼関東大震災には耐えたものの、昭和20年5月の空襲で、3階部分と円形ドームを焼失した。戦後の混乱期では、2階建てにとんがり屋根という応急修理を施すことで精いっぱいだった。昭和30年ごろからは、何度も高層ビルへの改築計画が持ち上がる。
▼実現しなかったのは、規制の問題や資金不足もあったが、何より「東京のシンボルを残したい」という声が根強かったからだ。確かにガラスだらけで、似たり寄ったりのノッポビルが乱立するなか、ますます存在感を増している。
▼約500億円かけて、創建時の姿に復元する工事がついに始まった。5年先の完成を心待ちにしながら、平成という時代のことを思う。100年後に復元を望まれる建物と、その先見性をたたえられる政治家を生み出すことができるのだろうか、と。
(2007/06/01 05:01)
◇
2007/05/31-18:11 時事通信
「奥の細道」の旅スタート=李・前台湾総統、芭蕉記念館を訪問
日本に滞在している台湾の李登輝前総統は31日、曽文恵夫人らとともに東京都江東区の芭蕉記念館を訪問し、長年の念願だった「奥の細道」の旅をスタートさせた。
李氏は6月1日に明治・大正時代の政治家、後藤新平の生誕150周年を記念して創設された「後藤新平賞」の授賞式に出席。翌2日から6日まで松尾芭蕉がたどった「奥の細道」ゆかりの東北地方を訪れる。
記念館では山崎孝明江東区長らの案内で館内を見学。「深川に 芭蕉を慕い来 夏の夢」と自作の俳句を詠み、その後、芭蕉が居を構えた隅田川沿いの周辺を散策した。
◇
◆【正論】国際教養大学理事長・学長 中嶋嶺雄 李登輝博士来日に期待する|正論|論説|Sankei WEB
(略)
≪講演「後藤新平と私」≫
思えば、李氏の訪日を期待する動向や世論は、すでに長年のものであった。「アジア・オープン・フォーラム」においては、早くも1992年の京都会議でかなりの準備をし、内閣官房や外務当局にも理解を求め、東京を訪れないことを条件に、その実現が見通せたのだが、天皇皇后両陛下の訪中と時期が重なることによって実現しなかった。この間、李氏は3度にわたって訪米し、訪英・訪欧も続いたのだが、肝心の訪日は実現しなかった。2000年秋の「アジア・オープン・フォーラム」松本会議に際しても、今は亡き亀井正夫氏や武山泰雄氏ら同フォーラムメンバーの強い要望にもかかわらず実現せず、映像による参加にとどまった。昨年5月には、ほぼ今回と同じ日程で来日が予定されていたが、李氏が軽い肺炎で主治医から安静を命じられ、延期されたのであった。このような経緯ののちの今回の来日なのである。
本年は台湾の治世に歴史的な貢献をなした後藤新平生誕150周年に当たり、「後藤新平賞」が設けられることになった。その第1回受賞者に李氏が選ばれたのである。巨大な事業に献身した後藤新平の業績に学ぶという意味で、台湾の近代化、とくに民主化に献身した李氏はまことにふさわしい人物である。李氏は6月1日の授賞式に出席し、「後藤新平と私」と題する受賞記念講演を行う予定であるが、その中身は李氏ならではの格調の高い後藤新平論になるであろう。(略)
(2007/05/23 06:26)
◇
2007/05/08-17:13 李登輝氏に「後藤新平賞」=本人が授賞式出席へ
明治・大正時代の政治家、後藤新平の生誕150周年を記念して創設された「後藤新平賞」の第1回受賞者に8日、台湾の李登輝前総統(84)が選ばれた。評論家の粕谷一希氏や出版社社長の藤原良雄氏らでつくる「後藤新平の会」が発表した。李前総統は来月1日、東京都内での授賞式に出席し、講演を行う予定。
同賞は、故後藤新平元内相が100年先を見通した政策により、人を育てながら地域や国家の発展に寄与したとして、同じような業績を残した国内外の人物を対象に授与。毎年1回表彰する。
李氏は台北市長や総統などを歴任。「後藤の仕事と精神を継承し、台湾近代化の発展に貢献、台湾島民を代表する存在」として受賞が決まった。後藤氏は台湾総督府の民政長官時代に、上下水道などのインフラ整備を進めた。 (時事通信)




















