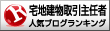以前書いた原稿をもう一度・・。
まず一番大事なことは、時間短縮できることがポイントです。
解いた後に、解いた感がないと受かりません。それはどういうことでしょうか。
合格するためには、50問のすべての問題をしっかりと読めることが大前提なのです。
つまり、時間がなく慌てて読んでも、答えは出ないはずです。
そうならないことが本試験では非常に重要です。
特に、最後の方で時間が足りなくなって、最後の10問は斜め読みだった、キーワードしか検討できなかった、など、普段ではじっくり読めたのに本試験では慌てて解いたために1,2点届かなかった、などです。
1、2点で落ちる人も、40点近くでうかる人も、普段の力の差はないことが多いものです。
実際に、模試で40点近くコンスタンスに得点できていた人も、3年連続で1点差で不合格になった人を知っています。
最後の1年は、少しテクニックを磨いた結果4年目にうかりました。
では、これ何が原因か。
1つは、最後の方で十分に解く時間がないため失敗した(2時間の勝負であって、3時間ではない)
試験中(だんだん時間がなくなる)→あわてる→普段起きないミスが出る→不安を持ちながら解く→ますます読めなくなる
最後の方では、普段と違いもうしっかり検討できずにミス連発です。
逆に、早く読もうと、読み飛ばず。
解決策ですが、これは時間を捻出するための解き方テクニックを身につければいいことです。
このため、ぜひ予想問をといてください。
何かつかむはずです。もしかしたら、目から鱗が・・・。
今回は、時間内におさめるため、解くテクニックを身につけることも必要だということを指摘します。
では、また。
※注意
この記事のベースは、平成24年度にかいたものです。その当時の合格点は、平成22年、23年とも、36点でした。
3年連続不合格だったその方は、平成23年に合格したのですが、前年も35点の1点差で不合格でした。その方と、37点38点 で合格した方との実力の差は、通常のときではほとんどなかったという意味でした。
実は、その方は23年も試験後では35点でしたが、その年は、問48が全員正解となり、見事36点に繰り上がり、合格でし た。運命的な合格の仕方だったことを覚えています。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

まず一番大事なことは、時間短縮できることがポイントです。
解いた後に、解いた感がないと受かりません。それはどういうことでしょうか。
合格するためには、50問のすべての問題をしっかりと読めることが大前提なのです。
つまり、時間がなく慌てて読んでも、答えは出ないはずです。
そうならないことが本試験では非常に重要です。
特に、最後の方で時間が足りなくなって、最後の10問は斜め読みだった、キーワードしか検討できなかった、など、普段ではじっくり読めたのに本試験では慌てて解いたために1,2点届かなかった、などです。
1、2点で落ちる人も、40点近くでうかる人も、普段の力の差はないことが多いものです。
実際に、模試で40点近くコンスタンスに得点できていた人も、3年連続で1点差で不合格になった人を知っています。
最後の1年は、少しテクニックを磨いた結果4年目にうかりました。
では、これ何が原因か。
1つは、最後の方で十分に解く時間がないため失敗した(2時間の勝負であって、3時間ではない)
試験中(だんだん時間がなくなる)→あわてる→普段起きないミスが出る→不安を持ちながら解く→ますます読めなくなる
最後の方では、普段と違いもうしっかり検討できずにミス連発です。
逆に、早く読もうと、読み飛ばず。
解決策ですが、これは時間を捻出するための解き方テクニックを身につければいいことです。
このため、ぜひ予想問をといてください。
何かつかむはずです。もしかしたら、目から鱗が・・・。
今回は、時間内におさめるため、解くテクニックを身につけることも必要だということを指摘します。
では、また。
※注意
この記事のベースは、平成24年度にかいたものです。その当時の合格点は、平成22年、23年とも、36点でした。
3年連続不合格だったその方は、平成23年に合格したのですが、前年も35点の1点差で不合格でした。その方と、37点38点 で合格した方との実力の差は、通常のときではほとんどなかったという意味でした。
実は、その方は23年も試験後では35点でしたが、その年は、問48が全員正解となり、見事36点に繰り上がり、合格でし た。運命的な合格の仕方だったことを覚えています。
 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋 克典 | |
| 住宅新報社 |