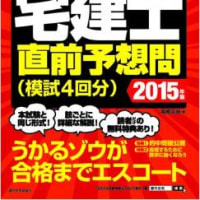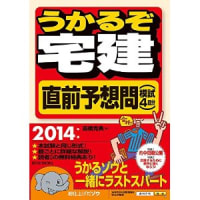R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問2・法人・・・。
宅建では出にくいのですが、他の国家試験では、基本です。
・・・・・・
問2 法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.法人は,その定款に記載された目的に含まれない行為であっても,その目的遂行に必要な行為については,権利能力を有する。
イ.理事が法人の機関として不法行為を行い,法人が不法行為責任を負う場合には,その理事は,個人として不法行為責任を負うことはない。
ウ.法人の代表者が職務権限外の取引行為をし,当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても,相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは,法人は,代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
エ.外国人が享有することのできない権利であっても,認許された外国法人は,日本において成立する同種の法人と同様に,その権利を取得することができる。
オ.設立登記が成立要件となっている法人について,設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ
・・・・・・
多少知識がなくても法的センスで判断してみましょう。
まず、肢アですが、○といえますね。
杓子定規では、まずいというものです。
確かに、「定款その他の基本約款で定められた目的」は重要で、その範囲内で、権利能力を有するとされています。
しかし、法人が目的を達成するためには、いろいろな関連する行為をしなければならないでしょう。
そうであれば、当該目的を遂行するために、直接・間接に必要な一切の行為を含むとしてもいいのではないか、という判断をします。
そこから生じた結果とか責任も、その法人に負わせた方がいいということですね。
○として、肢1か2のどちらかが正解となりますね。試験では、イを飛ばして、ウかオで勝負です。
肢イですが、これも感覚的には、×を付けられますね。
まず、理事が、法人の手足つまりその機関として職務を行って第三者に損害を与えた場合には、一般社団法人が損害賠償責任を負ってもいいでしょう。
理事は、手足だからそれ以上は責任はないといえるかですが、被害者救済の観点からいえば、その者個人が不法行為責任を負っていいでしょうね。
肢ウは、宅建レベルですし、○と付けられないといけません。そうすると、正解は肢1となります。
このとき使用する理論は、使用者責任でも出てきます。
「外形理論」というものですね。被害者保護から、「行為の外形からこれを判断し、実際のところは職務権限外の行為を理事が行ったとしても、客観的にみれば職務執行行為にあたる」として、法人の責任を問うのです。
もちろん、被疑者保護からすると、相手方が、当該理事の行為が職務権限外のものであることを認識しているか、ないしは認識しえた場合には、相手方を保護しなくてもいいのでは、ということです。主観的要件も考慮するということです。
肢エですが、×と付けられそうですか。
外国法人が日本で成立できても、外国人が享有できない権利については、法人としてもダメでしょう。
肢オですが、×と断定するのは、ちょっと勇気が要るかもしれません。
法人は自然人と並んで権利能力があります。
権利能力がない団体は、権利能力なき社団といっていましたね。
そこでは、なるべく法人に近づけて考えるのですが、不動産の登記はできないという知識程度は覚えておいてください。簡単に虚偽の登記が生まれてしまうからですね。
そして、法人の設立に当たっては、(設立の)登記が必要と解されていて、会社がその典型ですね。その登記が設立要件ですから、それを欠いているのであれば、法人格は認められません。
それで、そういう団体は権利能力なき社団としてが認められることはあっても、権利能力は有さないとしているのですね。
意外と解けたでしょう。自信が出てきましたか。
では、また。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

宅建では出にくいのですが、他の国家試験では、基本です。
・・・・・・
問2 法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.法人は,その定款に記載された目的に含まれない行為であっても,その目的遂行に必要な行為については,権利能力を有する。
イ.理事が法人の機関として不法行為を行い,法人が不法行為責任を負う場合には,その理事は,個人として不法行為責任を負うことはない。
ウ.法人の代表者が職務権限外の取引行為をし,当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても,相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは,法人は,代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
エ.外国人が享有することのできない権利であっても,認許された外国法人は,日本において成立する同種の法人と同様に,その権利を取得することができる。
オ.設立登記が成立要件となっている法人について,設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ
・・・・・・
多少知識がなくても法的センスで判断してみましょう。
まず、肢アですが、○といえますね。
杓子定規では、まずいというものです。
確かに、「定款その他の基本約款で定められた目的」は重要で、その範囲内で、権利能力を有するとされています。
しかし、法人が目的を達成するためには、いろいろな関連する行為をしなければならないでしょう。
そうであれば、当該目的を遂行するために、直接・間接に必要な一切の行為を含むとしてもいいのではないか、という判断をします。
そこから生じた結果とか責任も、その法人に負わせた方がいいということですね。
○として、肢1か2のどちらかが正解となりますね。試験では、イを飛ばして、ウかオで勝負です。
肢イですが、これも感覚的には、×を付けられますね。
まず、理事が、法人の手足つまりその機関として職務を行って第三者に損害を与えた場合には、一般社団法人が損害賠償責任を負ってもいいでしょう。
理事は、手足だからそれ以上は責任はないといえるかですが、被害者救済の観点からいえば、その者個人が不法行為責任を負っていいでしょうね。
肢ウは、宅建レベルですし、○と付けられないといけません。そうすると、正解は肢1となります。
このとき使用する理論は、使用者責任でも出てきます。
「外形理論」というものですね。被害者保護から、「行為の外形からこれを判断し、実際のところは職務権限外の行為を理事が行ったとしても、客観的にみれば職務執行行為にあたる」として、法人の責任を問うのです。
もちろん、被疑者保護からすると、相手方が、当該理事の行為が職務権限外のものであることを認識しているか、ないしは認識しえた場合には、相手方を保護しなくてもいいのでは、ということです。主観的要件も考慮するということです。
肢エですが、×と付けられそうですか。
外国法人が日本で成立できても、外国人が享有できない権利については、法人としてもダメでしょう。
肢オですが、×と断定するのは、ちょっと勇気が要るかもしれません。
法人は自然人と並んで権利能力があります。
権利能力がない団体は、権利能力なき社団といっていましたね。
そこでは、なるべく法人に近づけて考えるのですが、不動産の登記はできないという知識程度は覚えておいてください。簡単に虚偽の登記が生まれてしまうからですね。
そして、法人の設立に当たっては、(設立の)登記が必要と解されていて、会社がその典型ですね。その登記が設立要件ですから、それを欠いているのであれば、法人格は認められません。
それで、そういう団体は権利能力なき社団としてが認められることはあっても、権利能力は有さないとしているのですね。
意外と解けたでしょう。自信が出てきましたか。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |