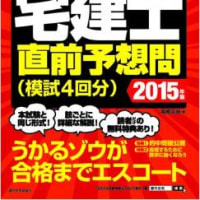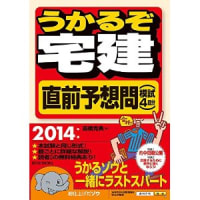R2年司法試験の民法を丁寧に分析“よーくわかる”問3・錯誤・・・。
もしかしたら、宅建の方が難問だったかもしれません。
これはしっかり解いておくべきでしょう。
宅建試験も行政書士も今年も出題可能性が大です。解けるぞー。
・・・・・・
問3 錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される。
イ.AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,Bも,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。
ウ.負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
エ.AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。
オ.AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ
・・・・・・
肢アですが、最初は△でしょうが、最終的に×ですね。
改正前は、表意者を中心に重要性を判断していました。
しかし、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければならない、といっていますから、相手方の保護とか取引の安全をも考慮する必要性があって、このような形になったといえるでしょう。
錯誤の重要性は、表意者を基準にしているわけではありませんね。
肢イですが、これはミスをしてはダメです。×ですね。これで肢1と3は消去できます。
無効ではなく取消しにしている理由の一つは、取消権を行使できる者を限定できる点です。
取消権者は、「表意者本人、代理人若しくは承継人」であり、これら以外の者は取消権行使を認めていません。Bが×ですね。
肢ウですが、今後出題される内容です。最初は、△でもこれも試験前には最終的には○にしていきましょう。
改正により規定されたものですが、「無償契約が取り消された場合に、取消原因につき、給付を受けた当時において善意であれば、現存利益の範囲の返還で足りる」とするものです。
有償契約ではないですよ。有償なら双方の給付の均衡性から、契約がない場合と同し状況、原状に回復せよといっています。
無償契約においては、それと状況が異なるからですね。
ぜひ、ここでこの知識を覚えておいてください。
肢エですが、これも○を付けられないといけません。
エが含まれる肢4か5が正解です。
錯誤の取消権を行使すると、第三者は、錯誤により取り消されることにつき、善意かつ無過失であれば保護されます。改正された点ですね。以前では、常に錯誤者が勝っていました。
肢オですが、一見○としそうですから注意してください。×ですね。
肢5が消えますから、肢4がのこって、正解です。
まず、「錯誤による意思表示につき、それに表意者の重過失がある場合には、取消権の行使」ができません。
しかし、これには例外が2つ認められています。
一つは、相手方が当該意思表示の錯誤が重過失によるものであることにつき、悪意または重過失がある場合です。
そして二つ目に、双方が錯誤に陥っていた場合です。
双方が錯誤に陥っている場合に、表意者の錯誤が重過失によるものであることで取消ができないとすると、相手方も錯誤に陥っていて、表意者の重過失を文句をいえないのに、その取消が制限されることで相手方が保護されないことになってしまってはおかしいからです。
難問もあり、うまく覚えていってください。
では、また。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

もしかしたら、宅建の方が難問だったかもしれません。
これはしっかり解いておくべきでしょう。
宅建試験も行政書士も今年も出題可能性が大です。解けるぞー。
・・・・・・
問3 錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される。
イ.AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,Bも,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。
ウ.負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
エ.AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。
オ.AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ
・・・・・・
肢アですが、最初は△でしょうが、最終的に×ですね。
改正前は、表意者を中心に重要性を判断していました。
しかし、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければならない、といっていますから、相手方の保護とか取引の安全をも考慮する必要性があって、このような形になったといえるでしょう。
錯誤の重要性は、表意者を基準にしているわけではありませんね。
肢イですが、これはミスをしてはダメです。×ですね。これで肢1と3は消去できます。
無効ではなく取消しにしている理由の一つは、取消権を行使できる者を限定できる点です。
取消権者は、「表意者本人、代理人若しくは承継人」であり、これら以外の者は取消権行使を認めていません。Bが×ですね。
肢ウですが、今後出題される内容です。最初は、△でもこれも試験前には最終的には○にしていきましょう。
改正により規定されたものですが、「無償契約が取り消された場合に、取消原因につき、給付を受けた当時において善意であれば、現存利益の範囲の返還で足りる」とするものです。
有償契約ではないですよ。有償なら双方の給付の均衡性から、契約がない場合と同し状況、原状に回復せよといっています。
無償契約においては、それと状況が異なるからですね。
ぜひ、ここでこの知識を覚えておいてください。
肢エですが、これも○を付けられないといけません。
エが含まれる肢4か5が正解です。
錯誤の取消権を行使すると、第三者は、錯誤により取り消されることにつき、善意かつ無過失であれば保護されます。改正された点ですね。以前では、常に錯誤者が勝っていました。
肢オですが、一見○としそうですから注意してください。×ですね。
肢5が消えますから、肢4がのこって、正解です。
まず、「錯誤による意思表示につき、それに表意者の重過失がある場合には、取消権の行使」ができません。
しかし、これには例外が2つ認められています。
一つは、相手方が当該意思表示の錯誤が重過失によるものであることにつき、悪意または重過失がある場合です。
そして二つ目に、双方が錯誤に陥っていた場合です。
双方が錯誤に陥っている場合に、表意者の錯誤が重過失によるものであることで取消ができないとすると、相手方も錯誤に陥っていて、表意者の重過失を文句をいえないのに、その取消が制限されることで相手方が保護されないことになってしまってはおかしいからです。
難問もあり、うまく覚えていってください。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |