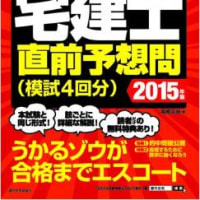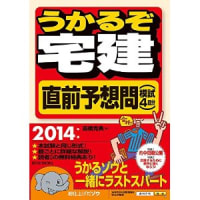すき間時間でR2年行政書士試験の民法を丁寧に分析“よーくわかる”問29・根抵当権・・・。
まず、根抵当権は、ほとんどの人が大嫌いだという声が聞かれます。
ポイントを押さえれば、ここもなんとかなるはずです。
宅建試験でも、今年は出題可能性が大です。
・・・・・・
問29 民法 物権
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1.被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
2.元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
3.元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
4.元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
5.根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
・・・・・・
肢1は、誤りですね。基本中の基本です。
根抵当権とは、バケツのようなもので、その中で元本とか利息などがあってそれらをすくってみて、いっぱいまでは大丈夫です。そのいっぱい状態が極度額ですね。
そうすると、バケツの中にはいる根抵当権の被担保債権の範囲とは、「極度額を限度」として、「確定した元本、利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部」になるわけです。
極度額の範囲以内であれば、すべて担保されるかもしれませんし、少しでも溢れれば利息は1年でもオーバーして担保できないとかになるわけです。本肢の「利息その他定期金の2年分という制限」は、普通の抵当権の引っかけですね。
これはきちんと判断できないとダメです。
肢2も、誤りですね。
後順位抵当権者などの第三者に影響を与えるのは、極度額の変更のときです。それ以外は、逆に極度額がきちんと定められていれば、あまり影響は受けないはずです。
確定前の根抵当権においては、被担保債権の範囲の変更をすることができますが、後順位抵当権者などの第三者に不利益を与えませんので、その承諾は求められていません。
もちろん、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます。ここでは、登記が対抗要件ではなく、効力要件になっている点です。
肢3は、正しいものとなり、これが正解ですが、ちょっと確定するには、全部読んで消去法で出す問題でしょう。
この元本確定期日は定めても定めなくてもいいのですが、定めたときには5年以内という制約があり、さらにその定めの変更については、肢2と同様、第三者の承諾は不要とされて、当事者の合意によってのみ成立します。
変更後の期日については、変更した日から5年以内との制限がありますが、元本確定期日の変更には、登記をすることが求められていて、元本確定期日の変更登記をしないときは、その変更前の期日に確定します。
ここまで覚えている人はなかなか(え、私もすぐに忘れます)いませんので、まずは△でしょうね。
肢4ですが、誤りです。
元本の確定前の根抵当では、継続的な関係が続いていますので、随伴性は認められていません。付従性もありませんね。
ということで、随伴しないので、「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない」し、「根抵当権については、免責的債務引受があった場合においても、根抵当権者は、引受人の債務について、根抵当権を行使することができない」となっています。
ちなみに、免責的債務引受の方から見ると、原則(根抵当権は例外)は、「担保権の移転をすることができる」ことになっています。それでも担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならないのです。
この問題も基本的知識にしておいてくださいね。
肢5も誤りですね。ちょっと難易度は高いかもしれません。これと肢3で比較していくことでしょう。
これは、元本の確定後においては、現存する債務額と極度額との差を見たときに、二つ考えられますが、それを調整するものです。
一つ(前者とします)は、現存する債務総額が極度額より少ない場合、本肢ですね。バケツの8分目しかない場合などです。
もう一方(後者とします)は、極度額より債務額がオーバーしている場合です。バケツからあふれている状態です。
前者においては、少ないのですから、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を下げるために、「現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額」に減額することを請求できてもいいのではないか、ということです。より小さなバケツしてほしい、ということです。
ちなみに、後者では、「他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者(物上保証人です)又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者(第三取得者です)は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる」としてもいいのではないかということです。バケツからこぼれた部分は債務者にいってね、ということですね。
この2つのパーターンが理解できて合格ですね。
では、また。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

まず、根抵当権は、ほとんどの人が大嫌いだという声が聞かれます。
ポイントを押さえれば、ここもなんとかなるはずです。
宅建試験でも、今年は出題可能性が大です。
・・・・・・
問29 民法 物権
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1.被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
2.元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
3.元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
4.元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
5.根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
・・・・・・
肢1は、誤りですね。基本中の基本です。
根抵当権とは、バケツのようなもので、その中で元本とか利息などがあってそれらをすくってみて、いっぱいまでは大丈夫です。そのいっぱい状態が極度額ですね。
そうすると、バケツの中にはいる根抵当権の被担保債権の範囲とは、「極度額を限度」として、「確定した元本、利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部」になるわけです。
極度額の範囲以内であれば、すべて担保されるかもしれませんし、少しでも溢れれば利息は1年でもオーバーして担保できないとかになるわけです。本肢の「利息その他定期金の2年分という制限」は、普通の抵当権の引っかけですね。
これはきちんと判断できないとダメです。
肢2も、誤りですね。
後順位抵当権者などの第三者に影響を与えるのは、極度額の変更のときです。それ以外は、逆に極度額がきちんと定められていれば、あまり影響は受けないはずです。
確定前の根抵当権においては、被担保債権の範囲の変更をすることができますが、後順位抵当権者などの第三者に不利益を与えませんので、その承諾は求められていません。
もちろん、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます。ここでは、登記が対抗要件ではなく、効力要件になっている点です。
肢3は、正しいものとなり、これが正解ですが、ちょっと確定するには、全部読んで消去法で出す問題でしょう。
この元本確定期日は定めても定めなくてもいいのですが、定めたときには5年以内という制約があり、さらにその定めの変更については、肢2と同様、第三者の承諾は不要とされて、当事者の合意によってのみ成立します。
変更後の期日については、変更した日から5年以内との制限がありますが、元本確定期日の変更には、登記をすることが求められていて、元本確定期日の変更登記をしないときは、その変更前の期日に確定します。
ここまで覚えている人はなかなか(え、私もすぐに忘れます)いませんので、まずは△でしょうね。
肢4ですが、誤りです。
元本の確定前の根抵当では、継続的な関係が続いていますので、随伴性は認められていません。付従性もありませんね。
ということで、随伴しないので、「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない」し、「根抵当権については、免責的債務引受があった場合においても、根抵当権者は、引受人の債務について、根抵当権を行使することができない」となっています。
ちなみに、免責的債務引受の方から見ると、原則(根抵当権は例外)は、「担保権の移転をすることができる」ことになっています。それでも担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならないのです。
この問題も基本的知識にしておいてくださいね。
肢5も誤りですね。ちょっと難易度は高いかもしれません。これと肢3で比較していくことでしょう。
これは、元本の確定後においては、現存する債務額と極度額との差を見たときに、二つ考えられますが、それを調整するものです。
一つ(前者とします)は、現存する債務総額が極度額より少ない場合、本肢ですね。バケツの8分目しかない場合などです。
もう一方(後者とします)は、極度額より債務額がオーバーしている場合です。バケツからあふれている状態です。
前者においては、少ないのですから、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を下げるために、「現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額」に減額することを請求できてもいいのではないか、ということです。より小さなバケツしてほしい、ということです。
ちなみに、後者では、「他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者(物上保証人です)又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者(第三取得者です)は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる」としてもいいのではないかということです。バケツからこぼれた部分は債務者にいってね、ということですね。
この2つのパーターンが理解できて合格ですね。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |