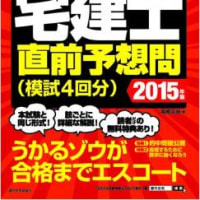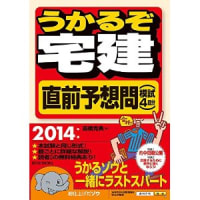R2年司法試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問4・代理・・・。
宅建試験でも全部出題されそうな内容です。
特に肢エ・オは今年宅建で出るかも・・・。
・・・・・・
問4 Aは,Bの代理人と称して,Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが,実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.AがCに対する無権代理人の責任を負う場合,Aは売買契約の履行をするか,又は損害賠償責任を負うかを自ら選択することができる。
イ.Bが売買契約を追認した場合,AはCに対する無権代理人の責任を負わない。
ウ.代理権を有しないことを知らないことにつきCに過失がある場合,Aは,自己に代理権がないことを知っていたときであっても,Cに対する無権代理人の責任を負わない。
エ.売買契約の締結後にAがDと共にBを相続した場合,Dの追認がない限り,Aの相続分に相当する部分においても,売買契約は当然に有効となるものではない。
オ.売買契約の締結後にBがAを単独で相続した場合,売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・・
肢アですが、×を付けられないといけません。
選択できるのは、保護されるべき相手方であって、無権代理人ではないでしょう。
そして、肢1か2が正解となります。エとオを読まなくても答えが出てしまいます。
肢イですが、これも自信を持って○としたいですね。
本人が無権代理行為を追認した場合には、契約時にさかのぼって効力が生じますから、初めから有効なものだったわけです。
無権代理人の責任を追及することはおかしいでしょう。法的にはですけど・・・。
ここで、もう正解は肢2で確定です。
肢ウですが、改正で、×になります。
相手方が、無権代理人に責任追及するためには、無権代理人が無権代理行為であることにつき善意であれば、相手方は善意かつ無過失であることが必要で、無権代理人が無権代理行為であることについて悪意であれば、相手方が善意かつ有過失であっても、責任を追及できます。
これは出ます。
肢エですが、これも○と自信を持って判断できるようにしてほしい。
実は、当然有効になるのは、本人が死亡して無権代理人が単独相続した場合だけです。信義則に反するでしょう。
本肢は、共同相続ですから、有効とはなりませんね。
その理屈ですが、無権代理人が他の相続人とともに本人の地位を相続した場合、追認権とはこれらの者の問で不可分的に帰属しているとみるわけです。全体として追認するのかしないのかなのです。ですから、全員が賛成しないかぎり追認できません。複雑にならないよう、やむを得ないんです。
肢オですが、こんどはAが死亡したときですから、やはり当然有効とはなりません。
覚えるのは、唯一有効となる場合だけです。受験対策としてはこれで問題ありません。
なお、本人は追認もできますし、追認拒絶もどちらもメリットはありますからできます。ただし、無権代理人の地位を相続しているため、相手方から責任追及を受ける可能性はありますので、注意してください。
では、また。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

宅建試験でも全部出題されそうな内容です。
特に肢エ・オは今年宅建で出るかも・・・。
・・・・・・
問4 Aは,Bの代理人と称して,Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが,実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.AがCに対する無権代理人の責任を負う場合,Aは売買契約の履行をするか,又は損害賠償責任を負うかを自ら選択することができる。
イ.Bが売買契約を追認した場合,AはCに対する無権代理人の責任を負わない。
ウ.代理権を有しないことを知らないことにつきCに過失がある場合,Aは,自己に代理権がないことを知っていたときであっても,Cに対する無権代理人の責任を負わない。
エ.売買契約の締結後にAがDと共にBを相続した場合,Dの追認がない限り,Aの相続分に相当する部分においても,売買契約は当然に有効となるものではない。
オ.売買契約の締結後にBがAを単独で相続した場合,売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・・
肢アですが、×を付けられないといけません。
選択できるのは、保護されるべき相手方であって、無権代理人ではないでしょう。
そして、肢1か2が正解となります。エとオを読まなくても答えが出てしまいます。
肢イですが、これも自信を持って○としたいですね。
本人が無権代理行為を追認した場合には、契約時にさかのぼって効力が生じますから、初めから有効なものだったわけです。
無権代理人の責任を追及することはおかしいでしょう。法的にはですけど・・・。
ここで、もう正解は肢2で確定です。
肢ウですが、改正で、×になります。
相手方が、無権代理人に責任追及するためには、無権代理人が無権代理行為であることにつき善意であれば、相手方は善意かつ無過失であることが必要で、無権代理人が無権代理行為であることについて悪意であれば、相手方が善意かつ有過失であっても、責任を追及できます。
これは出ます。
肢エですが、これも○と自信を持って判断できるようにしてほしい。
実は、当然有効になるのは、本人が死亡して無権代理人が単独相続した場合だけです。信義則に反するでしょう。
本肢は、共同相続ですから、有効とはなりませんね。
その理屈ですが、無権代理人が他の相続人とともに本人の地位を相続した場合、追認権とはこれらの者の問で不可分的に帰属しているとみるわけです。全体として追認するのかしないのかなのです。ですから、全員が賛成しないかぎり追認できません。複雑にならないよう、やむを得ないんです。
肢オですが、こんどはAが死亡したときですから、やはり当然有効とはなりません。
覚えるのは、唯一有効となる場合だけです。受験対策としてはこれで問題ありません。
なお、本人は追認もできますし、追認拒絶もどちらもメリットはありますからできます。ただし、無権代理人の地位を相続しているため、相手方から責任追及を受ける可能性はありますので、注意してください。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |