今回は、民法で行政書士でも出題されそうな論点を取り上げましょう。
今年の宅建 問8です。
新傾向でしたが、正答率は非常に高かったですね。
問題文「AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。」
ですが、1つが契約で、他はそうでないものですから、3つは何を聞いているか、分からなかったとしても答えは出せたのでしょう。
行政書士では、「根拠が異なるものをひとつ選びなさい」という形で出すと思われ、非常に難しくなりますよ。
では、各肢はどういう内容かというと。
肢1は、「青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求める場合。」
この根拠は、不法行為(使用者責任)ですから、契約ではありませんね。
肢3は、「Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約は無効であるとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。」
この根拠は、不当利得ですね。それは公平の原理です。
肢4は、「4 BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから領まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。」
この根拠は、事務管理です。義務がない(あれば委任だから)のにやった場合には、委任に近づけて関係を生じさせようとしています。
だから、おぼれている人を見ず知らずの人が助けた場合がこれですね。見て見ぬふりをしてもいいことですが・・・。
この事務管理は、好意で行ったのですが、一度他人の領域内に入ったら、委任と同様の関係を認めようとするのですから、それなりの覚悟がいりますよ。
事務管理は、宅建では解禁です。これでほとんどの分野が出題されたかな。あと、来年は和解が出たりして。
では、この契約以外で債権が発生する、逆に言うと債務・義務が発生するものを覚えましたから、これを論文に出すならどうなるか、提示しておきましょう。
「人は自らの意思によらずに義務付けられることはないという原則をのべなさい。」という問題です。
この原則は、もちろん契約があることですね。契約は自分の意思で結ぶものですから、そこから義務が発生しても当然甘んじなければいけないですね。
でも、例外も書かないと、出題者の意図に答えたことにならないでしょう。
で、以上の3つを書くわけです。
どうですか、深いですね。こんなのが他の試験で出ると宅建をちょっとみておいてよかったということになります。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
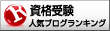
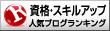
今年の宅建 問8です。
新傾向でしたが、正答率は非常に高かったですね。
問題文「AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。」
ですが、1つが契約で、他はそうでないものですから、3つは何を聞いているか、分からなかったとしても答えは出せたのでしょう。
行政書士では、「根拠が異なるものをひとつ選びなさい」という形で出すと思われ、非常に難しくなりますよ。
では、各肢はどういう内容かというと。
肢1は、「青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求める場合。」
この根拠は、不法行為(使用者責任)ですから、契約ではありませんね。
肢3は、「Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約は無効であるとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。」
この根拠は、不当利得ですね。それは公平の原理です。
肢4は、「4 BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから領まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。」
この根拠は、事務管理です。義務がない(あれば委任だから)のにやった場合には、委任に近づけて関係を生じさせようとしています。
だから、おぼれている人を見ず知らずの人が助けた場合がこれですね。見て見ぬふりをしてもいいことですが・・・。
この事務管理は、好意で行ったのですが、一度他人の領域内に入ったら、委任と同様の関係を認めようとするのですから、それなりの覚悟がいりますよ。
事務管理は、宅建では解禁です。これでほとんどの分野が出題されたかな。あと、来年は和解が出たりして。
では、この契約以外で債権が発生する、逆に言うと債務・義務が発生するものを覚えましたから、これを論文に出すならどうなるか、提示しておきましょう。
「人は自らの意思によらずに義務付けられることはないという原則をのべなさい。」という問題です。
この原則は、もちろん契約があることですね。契約は自分の意思で結ぶものですから、そこから義務が発生しても当然甘んじなければいけないですね。
でも、例外も書かないと、出題者の意図に答えたことにならないでしょう。
で、以上の3つを書くわけです。
どうですか、深いですね。こんなのが他の試験で出ると宅建をちょっとみておいてよかったということになります。
では、また。

























