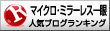向田邦子 新潮文庫

オリジナルの刊行は昭和55年12月だという。
ちょうど昨日の話題、五輪真弓の「恋人よ」がヒットし、その年の紅白に出場したりしていた頃だ。昨日書いたように、それからしばらくして、「少女」をラジオで聞いた。
「思い出トランプ」は、当時新聞などでかなり話題になっていたはずだ。手にしたことはなかったが、タイトルは良く覚えている。
向田邦子の名も、テレビで頻繁に目にしてたはずだ。「あ・うん」も見たような気がする。
ただ、当時の僕にはちょっとちがう世界というか、大人の世界の話、という感じで、本は読んだことはなかった。
今こうして手にしてみると、確かに主人公は大人ばかりだ。40代、50代の分別ざかりの男と女。
僕にとっては、今が読み頃なのだろう・。
配偶者や親、子供達、部下、相手のことはもうわかっているつもりだったのに、日々のふとしたきっかけが意外な面を照らし出す。
自分自身ですら、何かの瞬間に、思いも寄らなかった反応を示すことに驚いたりする。
「ダウト」の塩沢は、良くできた人物として知られ、常務にまで上り詰めた男だ。
自分のなかに、小さな黒い芽があることに塩沢は気がついていた。
人が見ていないと、車のスピード違反をする。絶対安全と判ると、小さなリベートを受け取ったこともある。出張先で後くされのない浮気をしたことも二度や三度ではなかった。
人間的にも良くできた人、という評価の裏のこういう面を、我ながら嫌だな、と思いながら、なあに人間なんてこんなものさ、このくらいは誰だってやっているさ、とうそぶくところもあった。
「りんごの皮」の時子は、弟の如才なさが気になる。
菊男は、姉とは正反対である。
ほどほどの身のまわり。ほどほどの就職。ほどほどの妻や子供たち。手にあまるものは見ないで暮らす菊男のやり方を、時子は歯がゆいと思ったこともあったが、気がつくと、年とった動物が、少しずつ、目に見えないほど少しずつ分厚く肥えふとってゆくように実りはじめている。今夜、団地の換気扇から流れていた魚を焼く匂いは、その実りの匂いであろう。
よく噛めば噛むほど、という言い方があるが、とても一度や二度読んだだけでは味わいきれない気がする。