俳句の解釈 19
「190.帯巻くとからだ廻しぬ祭笛
(鈴木鷹夫
/祭り笛聞けば帯巻く手間さえも惜しくて体回すようだと)」
「191.女郎花少しはなれて男郎花
(星野立子
/植生はよくわからずも女郎花まわり見やれば咲く男郎花)」
「192.およぎつゝうしろに迫る櫓音あり
(及川貞
/泳ぐときひたすら前を見ていたら背後気配櫓の音がする)」
「193.凡そ天下に去来程の小さき墓に参りけり
(高浜虚子
/上の句がやたら長くて字余りの例句に引かれる虚子の句である)」
「194.オリオンの楯新しき年に入る
(橋本多佳子
/オリオンに楯があるのかないのかはよくわからねど年改まる比喩でありしか
/新品の楯かも知らぬ新しき年になれればあるかもしれぬ)」
「195.折鶴のごとくに葱の凍てたるよ
(加倉井秋を
/葱折れて凍れるさまが折り鶴のように見えたる瞬間があり)」
「196.折鶴をひらけばいちまいの朧
(澁谷道
/朧とは折り鶴開け一枚の紙に正体なきが如しか)」
「197.をりとりてはらりとおもきすすきかな
(飯田蛇笏
/穂が曲がり重心手元になきゆえにはらりと重く感じたるかな)」
「198.音楽漂う岸侵しゆく蛇の飢
(赤尾兜子/岸辺には静かな音楽漂える一瞬にして蛇は飲むごと)」
「199.貝こきと噛めば朧の安房の国
(飯田龍太
/貝噛めばよくわからぬも朧なる千葉房総が浮かぶというが
/安房の国置き換えできぬものなのか貝はアワビかこきと噛むとは)」
最新の画像[もっと見る]










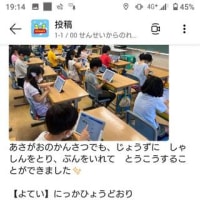
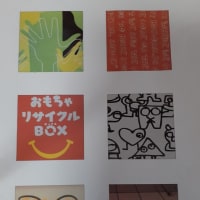














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます