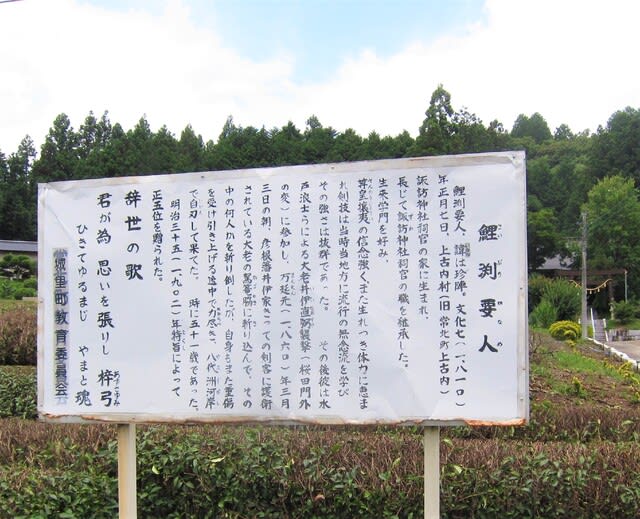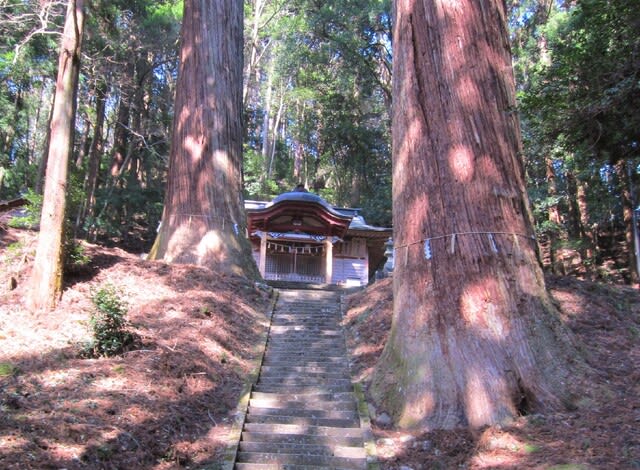水戸市植物公園では、水戸の梅まつりに合わせて3月21日まで園内の梅林を特別公開しており、花を愛でる「花梅」が100種以上あるという西川園長の動画も配信されています。初めて見る梅もありましたのでその一部をご紹介いたします。

「古郷の錦」 李系難波性 上品な薄紅色が好まれて、盆栽などにも人気の品種です。

「残雪」 野梅系 まだ雪が残る中で咲き、まるで雪ののような際立った白が命名の由来でしょうか。

「五節の舞」 李系紅材性 鮮やかな濃紅色と白くて長い雄蕊が特徴です。
「五節(ごせち)舞」とは、宮廷で舞われる唯一の女舞で十二単に檜扇をもつ5人の女性によって奏されるそうです。

「司絞り」 李系難波性 紅い絞りがかすかに見えます。紅白咲き分けにもなるそうです。

「司絞り虎斑」 司絞りの変種?…虎斑(とらふ)とは、虎の毛の横縞のような模様のこと、盆栽の松に葉に縞々の模様が入る虎斑松がありますが、この時期梅の葉の確認はできません。

「夏衣」 李系紅材性 内側が濃い紫紅色、梅では異色の艶麗な花色と図鑑には出ています。

「通小町」 野梅系 雄蕊は長くて黄色いのが特徴です。
通(かよい)小町という謡曲の演目に、百夜通いして精根尽きた深草少将の霊が死後も小野小町の霊を追いますが、僧の回向で成仏する話があるそうです。

「高砂」 杏系豊後性 図鑑には大宰府天満宮の銘品と載っています。高砂とは、高砂の浦の老松の精が相生(あいおい・夫婦がともに長生きすること)の老夫婦になって現れたという故事にならった能楽曲で、婚礼などの祝儀で謡われます。

「黄金梅(おうごんばい)」 野梅系 黄色がかった細い花弁と長い雄蕊、梅花とは思えないような姿です。秩父地方で産出し青梅で命名されたと伝わります。

「黄金鶴(こがねづる)」 野梅系 梅花名品集に珍品種として初めて記載されたと出ています。40枚以上の黄色い花弁が波打ち、雌蕊が蕾から飛び出している異様な姿で、開花するのに日数がかかるということです。

「雪山枝垂れ」 万博記念公園にもあるそうですが、詳細は分かりません。枝垂(しだれ)と雪崩(なだれ)は一字違い、間違うと大変です。

「蝶の羽重」 杏系豊後性 重なった花弁が乱れ、なんとも艶やかで名前の通りのイメージです。

「雪月花」 野梅系 花の形がよく、銘品であると図鑑に出ています。四季おりおりの風雅な眺めである「雪月花」のすべてを併せ持つ美しさというような命名でしょうか。

「八重海棠」 杏系紅筆性 花が下向きに咲くハナカイドウ(花海棠)に似ているので付けられた名前のようです。写真では横向きですが…。

「雲井」 杏系豊後性 花底に向かって紅色が淡くなります。雲井には雲のある大空や、宮中、皇居などの意味があります。また、福岡藩十代藩主黒田斉清の「諫言褒美・雲井の梅」という逸話も残っているようです。
名前を見て梅の花を見ると、付けた先人の思いが分かるような花もあり、何かと想像が膨らみますが命名者、命名由来、時期についてはもちろん知る由もありません。

中国原産の梅は、水田稲作技術と同じ頃に日本に渡来したといわれ、やがて武士社会になると実用面に加え、春にさきがけて芳香を放つその精神面でも珍重されてきました。
水戸藩2代藩主徳川光圀公は、17世紀後半に上屋敷(小石川)に梅園をつくり、また旗本の春田久啓は数百株の梅を屋敷に蒐集して韻勝園と称し、約100種を写生、解説した「韻勝園梅譜」を文化8年(1811)に発刊しています。

写本や模写版もあるようですが、写生図の入っていないアマゾンkindle版がなんと110円で購入できました。(国会図書館デジタルコレクションでも閲覧できます)
いま国内で梅の種類は約400種といわれます。現代でも流通している名前もこの「韻勝園梅譜」に多く記載されていますので、命名時期は相当古いものもあることは確かのようです。