「ソフィーの世界」の四回目は、いよいよ20世紀の哲学者が登場します。
キルケゴールやニーチェ、ハイデガーなど、そうそうたるメンバーですが、彼等はちょっと飛ばして、実存主義のリーダー的存在、ジャン=ポール・サルトルから、この物語から脱出するヒントをもらうことにしましょう。
キーワードは、もちろん、『実存』。
「実存は本質に先立つ。」
人間の本質とは、『人間とは何か?』という定義のことです。しかし、サルトルによれば、人間にはそういう本質なんかない。人間は自分をゼロからつくらなければならない。なぜ、何のために生きているかは、自分達で決めなければならない。と言うのです。
「人間は意味のない世界に投げ出されて、疎外感を抱き、絶望、倦怠、嘔吐、不条理感に襲われる。人間は、『自由の刑』に処されているのだ。」
「私達は、自分を自分で自由であるようにつくったわけではない。にもかかわらず、私達は、自由な個人であるのだ。そして、その自由のために、私達は自分でなにもかも決めるように、死ぬまで運命づけられている。頼りになる永遠の価値も基準もない。私達がどんな決断をするか、どんな選択をするかが、とてつもない重みをもってくる。『仕事だから』とか、『みんながしているから』なんて、責任を押し付けるわけにはいかない。人間は、自分のしたことの責任から絶対に逃れられない。」
サルトルは生には決まった意味はないと主張しましたが、だからと言って、なにもかもどうでもいいと思ったわけではありません。
サルトルは、『生には意味がないわけにはいかない』、と考えました。
これは逃れられない定めだ。『実存』するとは、自分の存在を自分で創造するということだ。
二人の人が、同じ部屋にいても、二人ともその部屋をまるで違ったイメージで捉えることがよくあります。これは二人の関心や意向のはたらかせ方が違うからです。つまり、私達が何を感じるかの決定には、私達自身が参加していて、私達自身の存在のしかた、生き方が、その部屋にあるものをどんなふうに認識するかを、大きく左右しているのです。
妊娠している人は、おなかの大きな人につい目がいってしまいます。今まで、周りに妊婦さんがいなかったわけではありません。自分が妊娠したことによって、それが新たな意味を持ったということです。
この世界を、こうならしめているのは、つまるところ、私達自身の生き方なのです。そして、もちろん、ソフィー達の世界も・・・
「だから、『存在するかしないか』は問題のすべてではない。『私達は何なのか』ということも問題なのだ。」
バークリの回の冒頭に掲げた言葉、esse est percipi (エッセ・エスト・ペルキピ)はラテン語で「存在するということは、知覚されているということだ。」という意味でした。
ソフィー達は確かに物語の登場人物で、紙とインクの存在かも知れません。しかし、ソフィー達の存在でさえ、私達の生き方、考え方が影響を与えて、『ありよう』を左右しているとしたら?
バークリの言う、『知覚しているもの』とはキリスト教の”神”のことでした。では、「ソフィーの世界」を『知覚しているもの』は誰でしょう?
少佐?
ヒルデ?
作者のゴルデル?
でも、本当に本を開いているのは誰?
哲学的マジックによって、ソフィー達は見事、少佐の意識からの脱出に成功します。
ことの顛末はどうぞご自分の目で。
ながながと書いてきましたが、ここまで読んで下さった方、本当にありがとうございます。これに懲りずに、また遊びに来てやって下さい。
最後に、美しいビャルクリの夜空を見上げながら、父親がヒルデに宇宙の神秘について語るシーンでこの本の紹介はおわりです。
『今ここにいる』ということの不思議さを分かち合いたい方へ・・・
☆
「わたし達がこの宇宙の小さな惑星の上に生きているなんて、考えるとへんだね。」「もうすぐ海にも星が見えてくるわ。」「きみは小さい頃、夜光虫のことを海の星って言ってたね。きみは正しかったんだ。なぜなら夜光虫も他のすべての有機体も、かつてはひとかたまりの星だった元素でできているんだ。」「わたし達も?」「そうだよ、わたし達も星屑なんだ。」
ヨースタイン・ゴルデル 著
須田 朗 監修
池田 香代子 訳
NHK出版
キルケゴールやニーチェ、ハイデガーなど、そうそうたるメンバーですが、彼等はちょっと飛ばして、実存主義のリーダー的存在、ジャン=ポール・サルトルから、この物語から脱出するヒントをもらうことにしましょう。
キーワードは、もちろん、『実存』。
「実存は本質に先立つ。」
人間の本質とは、『人間とは何か?』という定義のことです。しかし、サルトルによれば、人間にはそういう本質なんかない。人間は自分をゼロからつくらなければならない。なぜ、何のために生きているかは、自分達で決めなければならない。と言うのです。
「人間は意味のない世界に投げ出されて、疎外感を抱き、絶望、倦怠、嘔吐、不条理感に襲われる。人間は、『自由の刑』に処されているのだ。」
「私達は、自分を自分で自由であるようにつくったわけではない。にもかかわらず、私達は、自由な個人であるのだ。そして、その自由のために、私達は自分でなにもかも決めるように、死ぬまで運命づけられている。頼りになる永遠の価値も基準もない。私達がどんな決断をするか、どんな選択をするかが、とてつもない重みをもってくる。『仕事だから』とか、『みんながしているから』なんて、責任を押し付けるわけにはいかない。人間は、自分のしたことの責任から絶対に逃れられない。」
サルトルは生には決まった意味はないと主張しましたが、だからと言って、なにもかもどうでもいいと思ったわけではありません。
サルトルは、『生には意味がないわけにはいかない』、と考えました。
これは逃れられない定めだ。『実存』するとは、自分の存在を自分で創造するということだ。
二人の人が、同じ部屋にいても、二人ともその部屋をまるで違ったイメージで捉えることがよくあります。これは二人の関心や意向のはたらかせ方が違うからです。つまり、私達が何を感じるかの決定には、私達自身が参加していて、私達自身の存在のしかた、生き方が、その部屋にあるものをどんなふうに認識するかを、大きく左右しているのです。
妊娠している人は、おなかの大きな人につい目がいってしまいます。今まで、周りに妊婦さんがいなかったわけではありません。自分が妊娠したことによって、それが新たな意味を持ったということです。
この世界を、こうならしめているのは、つまるところ、私達自身の生き方なのです。そして、もちろん、ソフィー達の世界も・・・
「だから、『存在するかしないか』は問題のすべてではない。『私達は何なのか』ということも問題なのだ。」
バークリの回の冒頭に掲げた言葉、esse est percipi (エッセ・エスト・ペルキピ)はラテン語で「存在するということは、知覚されているということだ。」という意味でした。
ソフィー達は確かに物語の登場人物で、紙とインクの存在かも知れません。しかし、ソフィー達の存在でさえ、私達の生き方、考え方が影響を与えて、『ありよう』を左右しているとしたら?
バークリの言う、『知覚しているもの』とはキリスト教の”神”のことでした。では、「ソフィーの世界」を『知覚しているもの』は誰でしょう?
少佐?
ヒルデ?
作者のゴルデル?
でも、本当に本を開いているのは誰?
哲学的マジックによって、ソフィー達は見事、少佐の意識からの脱出に成功します。
ことの顛末はどうぞご自分の目で。
ながながと書いてきましたが、ここまで読んで下さった方、本当にありがとうございます。これに懲りずに、また遊びに来てやって下さい。
最後に、美しいビャルクリの夜空を見上げながら、父親がヒルデに宇宙の神秘について語るシーンでこの本の紹介はおわりです。
『今ここにいる』ということの不思議さを分かち合いたい方へ・・・
☆
「わたし達がこの宇宙の小さな惑星の上に生きているなんて、考えるとへんだね。」「もうすぐ海にも星が見えてくるわ。」「きみは小さい頃、夜光虫のことを海の星って言ってたね。きみは正しかったんだ。なぜなら夜光虫も他のすべての有機体も、かつてはひとかたまりの星だった元素でできているんだ。」「わたし達も?」「そうだよ、わたし達も星屑なんだ。」
ヨースタイン・ゴルデル 著
須田 朗 監修
池田 香代子 訳
NHK出版













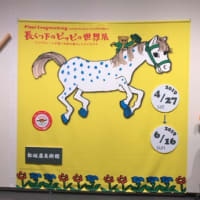
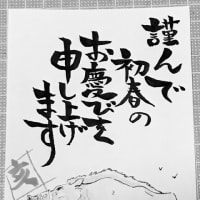
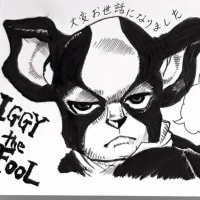
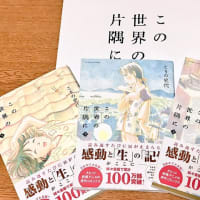

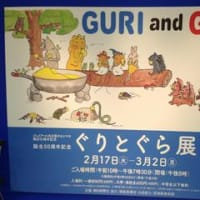





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます