日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中
Brugge Style
薔薇色の街、神の国
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  | 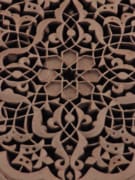 |  |
murt 'n akush
年賀状のボツ写真。
と言うのは、ここを訪れたのがすでに年始で、思いつきで薔薇色の写真群を組み合わせた時はすでに松の内を過ぎていたのです...
今見るとそれほどいい写真でもなく、かえってよかったもしれない(かわりに家族写真を使った)。
去年9月ホテルを去り際に、年末年始にもう一度と予約しておいたのは、われながら要領がよかったと誉めてやりたい。
...
ジョージ・オーウェルが20世紀の初めにこう書いた「マラケシュ」。
”As the corpse went pass the flies left the restaurant table in a cloud and rushed after it, but they came back a few minutes later.
レストランのテーブルにたかっていた蝿が、行き過ぎる葬列の方へ一団となって飛んで行った。しかし、奴らはすぐに戻って来た”
今でこそレストランで蝿は見ないが、蝿のたかる旧市街の路地は少なくない。
”It is only because of this that the starved countries of Asia and Africa are accepted as tourist resorts. No one would think of running cheap trips to the Distressed Areas. But where the human beings have brown skins their poverty is simply not noticed. What does Morocco mean to a Frenchman? An orange-grove or a job in government service. Or to an Englishman? Camels, castles, palm-trees, Foreign Legionnaires, brass trays and bandits. One could probably live here for years without noticing that for nine-tenths of the people the reality of life is an endless, back-breaking struggle to wring a little food out of an eroded soil."
...アジアやアフリカのような飢える国は「飢える国」としてではなく、「ツーリスト・リゾート」ととして受け入れられているからだ。誰も困窮した地域で格安旅行をしているなどとは思ってはいないのだ。茶色の肌をした人間の国では、貧困は完全に忘れられてしまう。フランス人にとってのモロッコとは何だ? オレンジの木立や政府の仕事。英国人にとっては? らくだ、椰子の木、仏外国人部隊、真鍮製のトレイや盗賊。痩せた土地からわずかな食料を奪い取るために、9割方の人々が終わりのない骨の折れる苦闘を続けなければならないことを、ツーリストは何年も気づかず暮らすことだってできるだろう” (訳はモエ)
「優雅で成熟した英国」(フィガロ・ジャポンの旅行特集や英国ミステリや、オースティン姉妹やら)で焚き付けられ、英国旅へといざなわれている人々の話を聞いて、「ピーターラビットで有名な湖水地方の近隣には住人9割がアル中か薬中かシングルマザーで生活保護を受けている街がある」とか、「階層と階層の間にハシゴのない社会で、自分が下の階級に生まれることを想定できないのはなぜ」などと鼻息が荒くなったりするのだが、なに、わたしだってモロッコが、ドバイが、アブダビが、エキゾティックだ、ロマンティックだ、文化が、伝説が、詩が、食が素晴らしいと賞賛している。
人間は片目をつむった状態でないと旅行すらできないのかもしれない。
だからこそオーウェルのような(遠く及ばないにしても)クールな目を常に持っていたい...
「クールな目を持っていたい」というのすら、「反省はもう済ませたからいいよね」という意味合いがあって、なんとなくいやだなあ。
「子供が飢えているのはもう分かったから、今日は食べ放題に行こう」みたいな感じで。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




