朝日新聞 2018年10月2日03時00分
 ハスカップごはんと鹿肉の駅弁=2018年9月20日午前10時17分、JR札幌駅構内の「弁菜亭」
ハスカップごはんと鹿肉の駅弁=2018年9月20日午前10時17分、JR札幌駅構内の「弁菜亭」
アイヌ民族の食文化を駅弁で再現した「イランカラプテ」弁当の第2弾が、JR札幌駅構内で販売されている。地震で北海道の観光客が減少するなか、弁当を製造する札幌駅立売商会は「元気な北海道」の発信につなげたいという。
駅弁の食材はすべて道内産。アイヌ民族に好まれてきたハスカップで味付けをしたご飯と、特製のしょうゆだれで漬け焼きしたエゾシカ肉(ユク)がメイン。カボチャの素揚げや昆布の佃(つくだ)煮も添えた。甘酸っぱいピンク色のご飯と、しっかり味が付いたシカ肉がマッチし、食べ応えも十分だ。
今年、北海道命名150年を機に、札幌駅構内で駅弁売店「弁菜亭」を営む同商会(札幌市東区)が駅弁を作った。4月に売り出した第1弾は、外国人観光客にも道民にも好評で、予定の5千食を9月に完売。第2弾も引き続き、アイヌ民族らでつくる団体「アイヌ女性会議 メノコモシモシ」が監修し、現代風に食べやすくアレンジした。
同社によると、地震による観光客の減少で、駅弁の売り上げも3~4割ほど落ち込んでいるという。洲崎昭光社長は「奥深いアイヌ民族の食文化とともに、元気で魅力ある北海道の発信になれば」と話す。税込み1080円。(斎藤徹)
https://www.asahi.com/articles/ASL9N3RDCL9NIIPE00K.html
 ハスカップごはんと鹿肉の駅弁=2018年9月20日午前10時17分、JR札幌駅構内の「弁菜亭」
ハスカップごはんと鹿肉の駅弁=2018年9月20日午前10時17分、JR札幌駅構内の「弁菜亭」アイヌ民族の食文化を駅弁で再現した「イランカラプテ」弁当の第2弾が、JR札幌駅構内で販売されている。地震で北海道の観光客が減少するなか、弁当を製造する札幌駅立売商会は「元気な北海道」の発信につなげたいという。
駅弁の食材はすべて道内産。アイヌ民族に好まれてきたハスカップで味付けをしたご飯と、特製のしょうゆだれで漬け焼きしたエゾシカ肉(ユク)がメイン。カボチャの素揚げや昆布の佃(つくだ)煮も添えた。甘酸っぱいピンク色のご飯と、しっかり味が付いたシカ肉がマッチし、食べ応えも十分だ。
今年、北海道命名150年を機に、札幌駅構内で駅弁売店「弁菜亭」を営む同商会(札幌市東区)が駅弁を作った。4月に売り出した第1弾は、外国人観光客にも道民にも好評で、予定の5千食を9月に完売。第2弾も引き続き、アイヌ民族らでつくる団体「アイヌ女性会議 メノコモシモシ」が監修し、現代風に食べやすくアレンジした。
同社によると、地震による観光客の減少で、駅弁の売り上げも3~4割ほど落ち込んでいるという。洲崎昭光社長は「奥深いアイヌ民族の食文化とともに、元気で魅力ある北海道の発信になれば」と話す。税込み1080円。(斎藤徹)
https://www.asahi.com/articles/ASL9N3RDCL9NIIPE00K.html












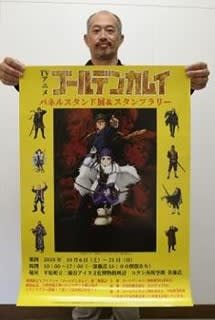
 アラスカの先住民族の衣装などを飾る会場
アラスカの先住民族の衣装などを飾る会場 




