R先生から以下の部分を含むLINEをもらいました、後半だけ載せます。
東大教授の酒井邦嘉さんのお言葉です「私たちが高度に発達した現代社会の中で、しかもこのかけがえのない地球上で生きていくには、人間と自然の科学を結びつける[知]のあり方こそが確かな力になるのです。そこで、学校を出た後の学びでは,思い切って自由に文系と理系の垣根を越えてみたいものです。」そこで昨日の「理系の回路」を「脳の活性化」に変更します。
不思議なことが起きるもので、今日偶々開いた本にこんなことが書かれいました。本は藤原彰・森田俊男編『近現代史の真実は何か』(1996年 大月書店)、そのなかの本多勝一の一文です。


このなかの「理系、文系」に触れている部分をここに載せておきます。
ところで「バカバカしい提起」にはもちろん文系も理系もありませんが、 両者の大きな違いのひとつは、多くの理系が「追試」可能な点です。たとえば「アルコールを燃やすと水と炭酸ガスができる」という仮説がウソかホントかは第三者が追試実験すれば証明できます。 しかし「南京大虐殺」の追試実験はできません。 追試ができないとインチキも当然のさばりやすい。もともと西欧的価値観による差別賞たる「ノーベル賞」も、理系より文系(平和賞や文学賞)にインチキが多いのはこのためです。だから理系でも追試不可能な分野にはインチキも出やすくなります。古生物学とか地質学とか。
他方では文系にしても、問題が事実関係と深くからんでいて、追試までは無理でも検証が可能な分野であれば、理系に近い作業と討論が期待できましょう。裁判と似ていて、動かぬ証拠があれば検証に耐える法廷となります。しかしここで裁判官が問題になる。「御用裁判官」であれば、一方の証拠ばかり採用して他方を採用しないことなどたやすい作業、教科書裁判はそれに近い例です。
理系が立脚すべき基盤は対象の客観性であるが、文系においては対象への価値観にある、本多が「西欧的価値観」と指摘しているのはそれを言っており、その価値観は社会性に取り込まれているので、本多のいう差別賞ということになるのでしょう。
経済学は西欧では理系に入るが、日本では文系扱いになっているらしい。「らしい」とは曖昧な言い方ですが、理系文系などと普段考えもしないことに頭を使い、ネットで垣間見た断片のなかで言われていたことです。とは言え経済学はまさに社会性に揉まれ、都合の良い経済学と悪い経済学に分かれているようです。
いずれにしても理系とか文系とか述べる水準には、とても到達していない頭ですから、少なくても客観性を背に「追試」可能な理系性を身につけるべきだというR先生の腹の中から、次のようなLINEが送られてきました。とてもそちらに頭が向かう状況ではないので、眠って覚めてから読んでみることにします。
中学での「変化の割合」の定義は高校では「平均変化率」となります。関数y=f(x)においてxの値がaからbまで変化する時{f(a)-f(b)}/(b-a)を関数f(x)の平均変化率という。ここで、b-a=hとおくと、b=a+hとなり平均変化率は、{f(a+h)-f(a)}/hと表されます。この時aの値を定めhを限りなく0に近づけときの極限値をf´(a)と表し関数y=f(x)のx=aにおける微分係数と言います。関数y=f(x)において,xの各値aに対して,微分係数f´(a)を対応させると、新しい関数が得られる。この新しい関数を,もとの関数f(x)の導関数といい,f´(x)で表す。f(x)から導関数を求めることを、f(x)を微分するといいます。

















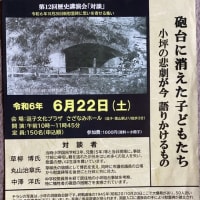


私的には 全ての人たちは 理系のものづくり人
私の経済学 人 物 金 で考えてしまいます
全ての人たちが いろんな物を作って お金に換えて
いろんな人たちが 食材を作り 食品を作り 調理を
してそこから全てのものづくりからお金づくりまで
そんな考え方をしている者には 理系も文系も・・
判りません。
じて生まれて来たものですから、元のところは知的系
列に属する人間作業のパターンです。と考えてみれば、1人の頭のなかでも同じ作業があるはずで、ある
ことには感覚的に、ある対象には理屈ぽく考えるとい
うことでしょう……、と書いてきてこれが文系だと。
この内容をもう少し筋立てして「論ずる」と理系にな
るということにしておきましょう。