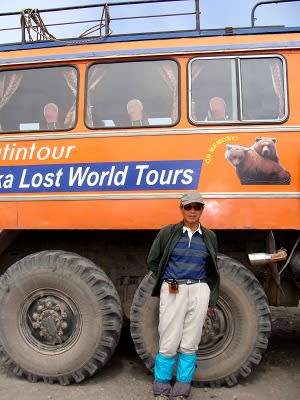7月26日、アバチャ山登頂の日です。残念ながらどんよりした曇り空で、コリャークもアバチャも、ラクダ山さえも雲の中に隠れています。
ザックには雨具、防寒具などの他、配給されたビニール袋の食料(チーズとサラミのサンドイッチ各1、ナッツ小袋、アンズ小袋、チョコレート小2、リンゴ、キャンディー数個、サクランボのジュースパック2)と水1.5Lを入れました。

午前8時、BC発。時間が遅いのは前に出発したパーティとの時間調整のようですが、夜は10時を過ぎても明るいので余裕たっぷりです。同行は山岳ガイドのワレンチンとニコライ、そしてスラーワ。TLのSさんもこの山に何度も登っているので心強いです。
ラクダ山への広い道と分かれて右へ、チシマフウロの群落を見ながら流れに沿って少し行き、対岸のジグザグ道を少し登るとケルンが三つ並ぶ台地に出ました。
スラーワの説明では「雪の季節にガイドレスのトレッカーが霧で道に迷い死んだところ」でケルンはその慰霊碑でした。
ここ(上のルート図で線の始まる地点)から、いよいよ登りになります。図の右へカーブする辺りで初めての休憩。最初はBCで残留予定の女性と、写真目的の参加で2000m迄同行予定の男性も含めて、2000M(図のP3)までは全員で行動するのでかなりゆっくりしたペースです。
(P1~P3は一応の目安としてあくまでも私が勝手につけたものです。)

9時40分、P1(1330m?)で2回目の休憩を終えて出発したところ。少し下って前に見えるP2(1550m?)に登り返します。
この辺りに来ると、砂礫のなかに所々クモマグサがしがみつくように咲いているだけで、他は岩に地衣類がついているだけの荒涼とした風景です。

雲の上に出てラクダ山が下になりました。コリャークは山裾だけが見えています。
しばらく急登が続いてP3に続くなだらかな赤茶けた砂礫の尾根に出ます。
推定1900m地点の岩陰で昼食(12:40)。

昼食を終えて出発(13:25)。この先の分岐から左に下る二人と付き添いのニコライとはここで分かれました。この先はもう引き返すことはできません。
正面の「悪魔の指」と呼ばれる奇怪な岩峰が近づきます。

P3(標高2000m地点)には岩室があり、前でロシア人が食事をしていました。
二、三人なら何とか風雨をしのげる程度の小さなものです。
正面に大きくアバチャ山が立ちはだかっています。あと標高差740m。(13:50)

空が青みを増してきました。この雪渓は見えている道を辿らず、縁を斜めに登って岩峰の下の短い部分だけ雪の上を行きました。(つづく)