奈良時代唐僧・為光上人によって開基された霊刹で、寺名は三つの井戸(湧き水)があることに由来している。西国三十三所観音巡礼第二番の札所でもあり、多宝塔は国の重要文化財に指定されている。
若かりし頃の、紀ノ国屋文左衛門が母を背負って寺の表坂を登ったところ、草履の鼻緒が切れてしまい、それを緒をすげ替えてくれたのが、紀三井寺の真向かいにある玉津島神社の宮司の娘のかよ。
これがきっかけとなって、文左衛門とかよの間に恋が芽生え、二人は結ばれる。そして、文左衛門は宮司(かよの父)の出資金で船を仕立て、蜜柑と材木を江戸へ送り豪商にまで上り詰めたと言われている。
以降、紀ノ国屋文左衛門の出世のきっかけとなった紀三井寺の表坂は、結縁坂と呼ばれるようになったそうな。

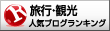
若かりし頃の、紀ノ国屋文左衛門が母を背負って寺の表坂を登ったところ、草履の鼻緒が切れてしまい、それを緒をすげ替えてくれたのが、紀三井寺の真向かいにある玉津島神社の宮司の娘のかよ。
これがきっかけとなって、文左衛門とかよの間に恋が芽生え、二人は結ばれる。そして、文左衛門は宮司(かよの父)の出資金で船を仕立て、蜜柑と材木を江戸へ送り豪商にまで上り詰めたと言われている。
以降、紀ノ国屋文左衛門の出世のきっかけとなった紀三井寺の表坂は、結縁坂と呼ばれるようになったそうな。






























