これぞまさに、日本製の二胡。
日本の木。
鎌倉時代以後の、寺院建築などに欅は使われてきました。
和太鼓の材料ですし、家具や船の舵などにも使われてきています。
色々調べてみると、日本だけではなく、台湾にも、中国にもあるようです。
只、木工品の材料としては、日本だけで使われているようです。
その理由は、中国の欅は、かなり密度が高く非常に硬いのですが、余程乾燥の仕方を上手にやらないと、ひび割れだらけになってしまいます。
あまりにも罅が多く、建築材や、ましてや家具などにはならないのです。
ただし、伐採の時期を選び、乾燥を非常に丁寧に、水をかけながら、日陰で日々手入れをしてややると、なんとか材料としては使えるようです。
乾燥のさせ方が、中国と日本では違いがありますので、中国では材料としては使っていないのでしょう。
木工の基本は、木をいかに知るかという事です。
この木はどうやって乾かせば、有用な材になるかとか、
どの部分を使えば、どのような木工品ができるかという知識の集積が、木工技術なのです。
刃物で削ったり、彫ったりするのは、木工技術のほんの一部なのです。
たとえば、アッシュという木があります。
普通木は赤身と、シラタによって構成されます。
シラタというのは、樹皮のすぐ下にあって、動物でいえば、脂肪に当たるところです。
殆どの木は、赤身の部分を使います。
シラタというのは、とても柔らかく、粘りがなくぼそぼそなのです。
黒檀などのシラタは、手でむしれるほどです。
アッシュは、乾燥の仕方によって、シラタの方がむしろ強い材料になったりもします。
以前は、野球のバットは、殆どがタモという木でしたが、今はこのアッシュのシラタも使うそうです。
木は、その樹種によっては、伐採時期の選択を誤ると、全く使えなくなります。
殆どの木は、春から夏にかけては伐採しません。
木が成長しようとしている時期ですから、そのままの力を伐採されても残していますので、
大きくひび割れたり、ゆがみがひどかったりもします。
椚(くぬぎ)や、エンジュ、柘植など、の伐採時期は年に1週間だけと言われます。
本来ならば全ての木の伐採は、木が生長を休む次期にやるべきなのですが、
最近の、流通を重んじる経済の中では、優先事項ではなくなってきています。
乾燥も同じことが言えます。
水分を調整しながら、ゆっくり10年も20年も乾燥させてはいられなくなってきています。
そこで、人工乾燥というのが、作られてきたのです。
この項続く
西野和宏
日本の木。
鎌倉時代以後の、寺院建築などに欅は使われてきました。
和太鼓の材料ですし、家具や船の舵などにも使われてきています。
色々調べてみると、日本だけではなく、台湾にも、中国にもあるようです。
只、木工品の材料としては、日本だけで使われているようです。
その理由は、中国の欅は、かなり密度が高く非常に硬いのですが、余程乾燥の仕方を上手にやらないと、ひび割れだらけになってしまいます。
あまりにも罅が多く、建築材や、ましてや家具などにはならないのです。
ただし、伐採の時期を選び、乾燥を非常に丁寧に、水をかけながら、日陰で日々手入れをしてややると、なんとか材料としては使えるようです。
乾燥のさせ方が、中国と日本では違いがありますので、中国では材料としては使っていないのでしょう。
木工の基本は、木をいかに知るかという事です。
この木はどうやって乾かせば、有用な材になるかとか、
どの部分を使えば、どのような木工品ができるかという知識の集積が、木工技術なのです。
刃物で削ったり、彫ったりするのは、木工技術のほんの一部なのです。
たとえば、アッシュという木があります。
普通木は赤身と、シラタによって構成されます。
シラタというのは、樹皮のすぐ下にあって、動物でいえば、脂肪に当たるところです。
殆どの木は、赤身の部分を使います。
シラタというのは、とても柔らかく、粘りがなくぼそぼそなのです。
黒檀などのシラタは、手でむしれるほどです。
アッシュは、乾燥の仕方によって、シラタの方がむしろ強い材料になったりもします。
以前は、野球のバットは、殆どがタモという木でしたが、今はこのアッシュのシラタも使うそうです。
木は、その樹種によっては、伐採時期の選択を誤ると、全く使えなくなります。
殆どの木は、春から夏にかけては伐採しません。
木が成長しようとしている時期ですから、そのままの力を伐採されても残していますので、
大きくひび割れたり、ゆがみがひどかったりもします。
椚(くぬぎ)や、エンジュ、柘植など、の伐採時期は年に1週間だけと言われます。
本来ならば全ての木の伐採は、木が生長を休む次期にやるべきなのですが、
最近の、流通を重んじる経済の中では、優先事項ではなくなってきています。
乾燥も同じことが言えます。
水分を調整しながら、ゆっくり10年も20年も乾燥させてはいられなくなってきています。
そこで、人工乾燥というのが、作られてきたのです。
この項続く
西野和宏











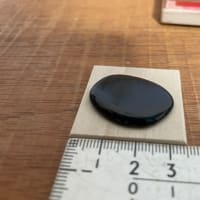














いやぁ、これまで西野さんから伺った話の内容が網羅されていて、興味深い内容です。今のテーマとリンクしていて面白さ3.2倍です。