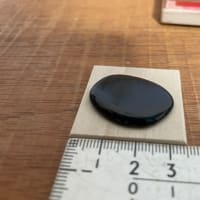最初に、二胡手渡されて、「さあ弾いてみましょう。」
そう言われて弾いた時、これは、勝手がちがう。
そう思ったのは、多分、チェロを弾いていた経験があるからでしょう。
弓が落ちない。
当然,
弦の間に挟まっているのですから、落ちません。
何?この、緩い弓。
なるほど、自分の手で張るのか!
この金具でシッカリ張ってしまえばよいじゃない。
で後ろのつまみを回すが、何時まで回しても、ピンとは張らない。
この竹、細すぎるのかしら。
とにかく弾いてみる。
酷い音、これはチェロの方が楽かな。良い音したし。
今になって考えてみると、もし私が、弦楽器初めて弾くのだったら、
二胡弾くのというのは、こんなに簡単なんだ、と思ったことでしょう。
そうですね、
二胡は、その弾く姿勢や、弦が少ないこと、弓を、弦に当てるのに、2本ですから、楽ですね。
ちなみに、4本の弦楽器は大変です。
手の角度がしっかり決まらないと、直ぐとなりの弦を弾いてしまいます。
多分早い人で、4本の位置把握するのに、丸一日、普通は、間違えなくなるのに2、3日懸ります。
姿勢も楽です。そのまま持てばよいのですから。
これは、良い。何でこんな良い楽器が広まらないのだろう?
二胡を弾いて最初に思ったのがこのことでした。
人の知識というのは、困ったことに、思いこんだら、それが決定的なものと思いやすいことです。
もしかしたらこの知識は違うかもしれない、と、思ってその知識を受け入れる人はいません。
それでは、心が壊れてしまうからです。
不安だらけになってしまいます。
例えば、暗闇の中で、冷たい何かわからない、ぐにゃっとしたもの触ったとします。
皆さん殆どの人が、わっと驚くでしょう。
それ、コンニャクですよと言われたとたんに、
なんだ、コンニャクかと安心します。
それがホントは、ナマコだったとしても。
あるいはもっと怖いものであったとしてもです。
二胡は中国の、伝統的な、民族楽器と、思っていらっしゃる方は、多分50%以上でしょう。
二胡弾かない人、入れれば90%はそう思っているでしょう。
伝統というのがどのくらい続けば成立するのかということは、かなり難しいです。
100年ですかね・200年ですかね?
そういう意味では、今の二胡の形、音域、調弦、
それらを考慮に入れるとまだ新しい、ともいえるぐらいではないですか?
劉天華先生が今の形にされたと、言われています。(それ以前は?)
まだ80年ぐらいです。
また、8角形ができてから、50年ぐらいでしょう。
これ、他の楽器にくれべれば、新しくは無いですか?
比較的最近作られて、世界中に広まった楽器の中に、サックスフォンがありますね。
これは、もう150年くらい経っています。
でも伝統という言葉を頭にかぶせて、書いたり話したりしているうちに、
もうそれは完成されたもの、という意味まで含んでしまいやすくは無いですかね?
それに、中国の伝統楽器というのも、言葉だけの意味からすると、変ですね。
それでも、2弦で、蛇皮でというのは、
7,800年くらいは経っているらしいので伝統というのは、問題ないかもしれません。
でも、胡、という名前自体が、中国の西から来たものというのを表わしていますね。
この辺は、それこそ、中国の中国たるゆえんで、
あらゆる民族を、吸収してしまい、一つの文明を作り上げる力でしょう。
ですから、その文明の中の中国ということだとしたら、二胡は中国の楽器とも言えるとは思います。
話は、飛びますが、
文化というのは、
ある特定の地域の、自然や民族性に根差した物ということが出来ると思います。
文明というのは、それら、個々のくせのある文化という物を含んだ上で、
他の文化を持つ人々にも浸透していける、
あるいは受け入れられる、普遍的な考え方、と言えるのではないでしょうか。
様々な、数十と言われる、民族たちを吸収して、それらが一つの文明を形成し、
それがましてや、数千年続いたという中国文明の凄さというのはあります。
ですから、それが、胡という西方の物ですよという名前がついていながらも、
国民的な、楽器になりうる二胡の、良さはあると思います。
二胡という楽器が、文化を超えて、文明の中に参加しうる、普遍的な力を持っていたということでしょう。
多分、其の数千年のありだに、様々な楽器が、中国に入ってきたことでしょう。
でもそれらは、形が変わるなり、あるいは一時のはやりで終わるなり、
今は、誰も演奏しなくなったものが、沢山あったはずです。
竹林の7賢人と言われる1700年前ぐらいの絵がありますが、
その中に書かれた、ゲンカン、と言われている楽器などは、もう存在しないようです。
話を元に戻しましょう。
考えるということは、言葉がなければ成り立ちません。
その言葉は、最初に、両親から、あるいはその身近の誰かから、
価値観を含んで教えられてきたものです。
その最初に刷り込まれた、言語、とその価値観は、なかなか拭えません。
新たな、知識に接したとしても、その時もう刷り込まれた、言語による価値観によって
その新しい知識は、選択されてしまうからです。
人は、その最初に刷り込まれた、言語、知識、価値観という、両親の描いた地図を持って、
人生を旅立つのではないでしょうか。
続く
西野和宏
そう言われて弾いた時、これは、勝手がちがう。
そう思ったのは、多分、チェロを弾いていた経験があるからでしょう。
弓が落ちない。
当然,
弦の間に挟まっているのですから、落ちません。
何?この、緩い弓。
なるほど、自分の手で張るのか!
この金具でシッカリ張ってしまえばよいじゃない。
で後ろのつまみを回すが、何時まで回しても、ピンとは張らない。
この竹、細すぎるのかしら。
とにかく弾いてみる。
酷い音、これはチェロの方が楽かな。良い音したし。
今になって考えてみると、もし私が、弦楽器初めて弾くのだったら、
二胡弾くのというのは、こんなに簡単なんだ、と思ったことでしょう。
そうですね、
二胡は、その弾く姿勢や、弦が少ないこと、弓を、弦に当てるのに、2本ですから、楽ですね。
ちなみに、4本の弦楽器は大変です。
手の角度がしっかり決まらないと、直ぐとなりの弦を弾いてしまいます。
多分早い人で、4本の位置把握するのに、丸一日、普通は、間違えなくなるのに2、3日懸ります。
姿勢も楽です。そのまま持てばよいのですから。
これは、良い。何でこんな良い楽器が広まらないのだろう?
二胡を弾いて最初に思ったのがこのことでした。
人の知識というのは、困ったことに、思いこんだら、それが決定的なものと思いやすいことです。
もしかしたらこの知識は違うかもしれない、と、思ってその知識を受け入れる人はいません。
それでは、心が壊れてしまうからです。
不安だらけになってしまいます。
例えば、暗闇の中で、冷たい何かわからない、ぐにゃっとしたもの触ったとします。
皆さん殆どの人が、わっと驚くでしょう。
それ、コンニャクですよと言われたとたんに、
なんだ、コンニャクかと安心します。
それがホントは、ナマコだったとしても。
あるいはもっと怖いものであったとしてもです。
二胡は中国の、伝統的な、民族楽器と、思っていらっしゃる方は、多分50%以上でしょう。
二胡弾かない人、入れれば90%はそう思っているでしょう。
伝統というのがどのくらい続けば成立するのかということは、かなり難しいです。
100年ですかね・200年ですかね?
そういう意味では、今の二胡の形、音域、調弦、
それらを考慮に入れるとまだ新しい、ともいえるぐらいではないですか?
劉天華先生が今の形にされたと、言われています。(それ以前は?)
まだ80年ぐらいです。
また、8角形ができてから、50年ぐらいでしょう。
これ、他の楽器にくれべれば、新しくは無いですか?
比較的最近作られて、世界中に広まった楽器の中に、サックスフォンがありますね。
これは、もう150年くらい経っています。
でも伝統という言葉を頭にかぶせて、書いたり話したりしているうちに、
もうそれは完成されたもの、という意味まで含んでしまいやすくは無いですかね?
それに、中国の伝統楽器というのも、言葉だけの意味からすると、変ですね。
それでも、2弦で、蛇皮でというのは、
7,800年くらいは経っているらしいので伝統というのは、問題ないかもしれません。
でも、胡、という名前自体が、中国の西から来たものというのを表わしていますね。
この辺は、それこそ、中国の中国たるゆえんで、
あらゆる民族を、吸収してしまい、一つの文明を作り上げる力でしょう。
ですから、その文明の中の中国ということだとしたら、二胡は中国の楽器とも言えるとは思います。
話は、飛びますが、
文化というのは、
ある特定の地域の、自然や民族性に根差した物ということが出来ると思います。
文明というのは、それら、個々のくせのある文化という物を含んだ上で、
他の文化を持つ人々にも浸透していける、
あるいは受け入れられる、普遍的な考え方、と言えるのではないでしょうか。
様々な、数十と言われる、民族たちを吸収して、それらが一つの文明を形成し、
それがましてや、数千年続いたという中国文明の凄さというのはあります。
ですから、それが、胡という西方の物ですよという名前がついていながらも、
国民的な、楽器になりうる二胡の、良さはあると思います。
二胡という楽器が、文化を超えて、文明の中に参加しうる、普遍的な力を持っていたということでしょう。
多分、其の数千年のありだに、様々な楽器が、中国に入ってきたことでしょう。
でもそれらは、形が変わるなり、あるいは一時のはやりで終わるなり、
今は、誰も演奏しなくなったものが、沢山あったはずです。
竹林の7賢人と言われる1700年前ぐらいの絵がありますが、
その中に書かれた、ゲンカン、と言われている楽器などは、もう存在しないようです。
話を元に戻しましょう。
考えるということは、言葉がなければ成り立ちません。
その言葉は、最初に、両親から、あるいはその身近の誰かから、
価値観を含んで教えられてきたものです。
その最初に刷り込まれた、言語、とその価値観は、なかなか拭えません。
新たな、知識に接したとしても、その時もう刷り込まれた、言語による価値観によって
その新しい知識は、選択されてしまうからです。
人は、その最初に刷り込まれた、言語、知識、価値観という、両親の描いた地図を持って、
人生を旅立つのではないでしょうか。
続く
西野和宏