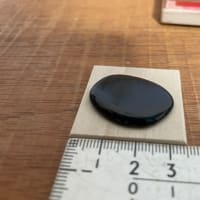内部を削るとすぐ6角形に組み立てます。
この時になるべく硬いボンドを使います。
普通ボンドは粘り気のあるものです。
日本でも昔はもち米を熱いうちに練って、続飯(そくいと読みます)という糊を使っています。
意外と良く付きますが、衝撃に弱いところが有ります。
一般的なのは、やはりニカワでしょう。
私も最初の頃はニカワを使っていましたが、やはり湿気に弱いのと、多少弾力が強いのとで、最近はタイトボンドという、アクリル系のボンドを使います。
このボンドは最近ではギター屋さんもバイオリン屋さんも使っています。
油分に強いのと、(紫檀黒檀は油分がとても強いのです)硬化した後にとても硬くなります。
そして上手い事に80度以上になると、弾力性が戻り、またはがすこともできるのでニカワと同じように扱うこともできます。
効果したらそのまま待ちます。1ヶ月から3ヶ月くらいですかね。季節によります。
この待っている間に木が動きますから、駄目な物も出て来ます。
これは叩くと分かります。
音がハレーションを起こすのです。これは直せませんから、一度分解して、再度削り直て6角形に組み上げ直します。
これだけしても、黒檀や、シャム柿というのはまた動くこともあるのです。
特に黒檀は何年かして必ずどこかしらに歪みが来たり、クラックが入ったりします。
それだけ力がたまっているということでしょう。
でもそれらは直せますし直せば更に良い音になります。
木の楽器は狂います、割れることもありますし、歪むこともあります。
今残っているストラデバリウスで、全くどこも直していない物など無いのです。
いずれは狂うだろうということを見越してその狂いを如何に平均化出来るかというのが、木工屋の技術になりますが、それらは何年か或いは何十年かの先を読むということになって行きます。
ですから、木の楽器は、メンテナンスというのがとても重要なことになって来ます。
今、二胡の世界にだけそのメンテナンスが存在していないのです。
光舜堂の場合これだけ時間をかけて、乾燥をしています。
しかしまだ有るのです。
この時になるべく硬いボンドを使います。
普通ボンドは粘り気のあるものです。
日本でも昔はもち米を熱いうちに練って、続飯(そくいと読みます)という糊を使っています。
意外と良く付きますが、衝撃に弱いところが有ります。
一般的なのは、やはりニカワでしょう。
私も最初の頃はニカワを使っていましたが、やはり湿気に弱いのと、多少弾力が強いのとで、最近はタイトボンドという、アクリル系のボンドを使います。
このボンドは最近ではギター屋さんもバイオリン屋さんも使っています。
油分に強いのと、(紫檀黒檀は油分がとても強いのです)硬化した後にとても硬くなります。
そして上手い事に80度以上になると、弾力性が戻り、またはがすこともできるのでニカワと同じように扱うこともできます。
効果したらそのまま待ちます。1ヶ月から3ヶ月くらいですかね。季節によります。
この待っている間に木が動きますから、駄目な物も出て来ます。
これは叩くと分かります。
音がハレーションを起こすのです。これは直せませんから、一度分解して、再度削り直て6角形に組み上げ直します。
これだけしても、黒檀や、シャム柿というのはまた動くこともあるのです。
特に黒檀は何年かして必ずどこかしらに歪みが来たり、クラックが入ったりします。
それだけ力がたまっているということでしょう。
でもそれらは直せますし直せば更に良い音になります。
木の楽器は狂います、割れることもありますし、歪むこともあります。
今残っているストラデバリウスで、全くどこも直していない物など無いのです。
いずれは狂うだろうということを見越してその狂いを如何に平均化出来るかというのが、木工屋の技術になりますが、それらは何年か或いは何十年かの先を読むということになって行きます。
ですから、木の楽器は、メンテナンスというのがとても重要なことになって来ます。
今、二胡の世界にだけそのメンテナンスが存在していないのです。
光舜堂の場合これだけ時間をかけて、乾燥をしています。
しかしまだ有るのです。