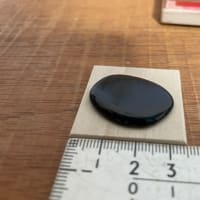先日ご来店のお客様のお一人、というより今までにもかなりの方が、
何人かの先生にお持ちの楽器についていろいろ言われ、
はたまた、他の楽器屋さんへ調整に行っても、なんだか釈然とした答えが返ってこず、
なんとなくもやもやとしていたのですが、
というかた、これかなり多いような気がします。
私が見ていても、まあ、私は二胡を弾くという事に関しては、お前は素人だろうと言われかねませんが、
なんだかお客様の弾くのを見ていて違和感を覚えることが多々あります。
弓そうやって引くのですか。
手は、そう動かすのですか?
とお聞きしても、
先生はこのように、と言うかたがずいぶん多いです。
私なんかは理屈屋ですから、なんで??と、様々なことに疑問を持ちます。
その疑問を持つという事が、大切なのではないかとも思っているのですが。
人に聞いてみて、答えが出なければ、自分で考えるきりないのではないでしょうか。
人の手(腕)は肩に一点でついています。
動かすとすれば、その肩を中心にした円であるはずなのです。
ところが擦弦楽器の弓というのは、弓が一直線に動くように弾きますね。
ただやみくもに弓をまっすぐといわれてもですね‐ーー
竹ではなく、弓の毛が一定の圧力で弦を鳴らすように弾くわけです。
60数センチもある弓の毛が一定の力で、弦を振動させるというのは、
先端に行けば手の力を入れないと手元とは同じようにはいかないですよね、
そこで竹のバネの力を使うのでしょうが、、、、
ましてや本来ならば円弧にきり動かない腕を使って未定の角度で一定の圧力というのが、
そんなの無理だろうという動きをしない限り、腕は動きません。
そこを、弓の竹の弾力と、手首の回転、指の微妙な動きによって、何とか実現するのが、
擦弦楽器の弓の運動なのです。
それを、昔からはこういう形だからと無理やり言われても、大人になってからの頭と体はなかなか馴染めませんね。
それをうまく説明してほしいのですが、なかなか、、
致し方ないので先生に言われたようにやっては見ても、
子供のころから習い覚えた技を,なかなかにはまねできませんね。
体操競技などのこと考えてください。
或いはもうすぐ始まるオリンピックのスキーのジャンプ、
スキーのジャンプ台に立ってみたことありますか?
かなり高いところが平気な私でさえ、あれを滑り降りるのだと思った瞬間、恐怖で叫びそうになりますね。
よくバンジージャンプに挑戦する人がいます。
あれも慣れがあるのでしょうが、
たぶんですよ、平気でバンジージャンプ飛ぶ人でも、スキーののジャンプをいきなりは難しいのではないでしょうかね。
スキーのジャンプも最初は5メートル10メートル20メートルと伸ばしていくんだそうです。
何事にも慣れというのはあります。
しかし、弓まっすぐに動かして、そこで手首を返して、言われても、
もうこれは慣れるしかありません。
しかしそこが問題なのでしょう。
ただ単に慣れるといっても、意外と微妙なところが違うような気がしませんか?
まったく同じように出来るとしたら、同じような音が出るはずなのです。
ですから、聞いてみましょう、何故?
何故そこでそういう動きをするのか、
弓は背中で弾くんだといわれても、
何故ですかと聞くほかないのです。
何故ならば言われてできる人は、解っているからです。
丹田に気を込めてとも言われます。丹田ってどこよ、
気を込めるってどうやるのよ?
すごく素朴な質問かもしれません、
意外と言っている人が理解していない場合も多いのです。
何故なら、私なんかなぜ自分が鉋の刃を平らに研げるのか、
指先だけに力を入れて、刃物を支え指を通して砥石の平らな面を感じて、
手首と腕の力を抜いて、背中の力で刃を動かすのです。
ね、解らないでしょう。
それでも、私なんかでも聞かれているうちに何とか考えて答えを出そうとはします。
まずは砥石を平らに常にしておく。
指先だけでカンナの刃を砥石の上に立てておくように何回も練習する。
まずは小さく前後に動かす。
1センチ、2センチと、
その時に手首の動きを教えます。
それができるようになったら、スピードを上げて手を前後に動かすように慣らします。
こうやって少しずつ、
またゆっくり動かして刃が平らな面から離れないように、
そうすると次第に指先が平らな面を感じるようになります。
それまで、1年。
これでもうまくは説明できていないです。
もっと筋肉の事、筋の事、手の関節の動きの事などきちっと説明しないとだめでしょう。
そうですね一つずつ、聞きながらやっていくしかないようです。
ですから皆さん、何故?と、質問してはいかがですか?
何人かの先生にお持ちの楽器についていろいろ言われ、
はたまた、他の楽器屋さんへ調整に行っても、なんだか釈然とした答えが返ってこず、
なんとなくもやもやとしていたのですが、
というかた、これかなり多いような気がします。
私が見ていても、まあ、私は二胡を弾くという事に関しては、お前は素人だろうと言われかねませんが、
なんだかお客様の弾くのを見ていて違和感を覚えることが多々あります。
弓そうやって引くのですか。
手は、そう動かすのですか?
とお聞きしても、
先生はこのように、と言うかたがずいぶん多いです。
私なんかは理屈屋ですから、なんで??と、様々なことに疑問を持ちます。
その疑問を持つという事が、大切なのではないかとも思っているのですが。
人に聞いてみて、答えが出なければ、自分で考えるきりないのではないでしょうか。
人の手(腕)は肩に一点でついています。
動かすとすれば、その肩を中心にした円であるはずなのです。
ところが擦弦楽器の弓というのは、弓が一直線に動くように弾きますね。
ただやみくもに弓をまっすぐといわれてもですね‐ーー
竹ではなく、弓の毛が一定の圧力で弦を鳴らすように弾くわけです。
60数センチもある弓の毛が一定の力で、弦を振動させるというのは、
先端に行けば手の力を入れないと手元とは同じようにはいかないですよね、
そこで竹のバネの力を使うのでしょうが、、、、
ましてや本来ならば円弧にきり動かない腕を使って未定の角度で一定の圧力というのが、
そんなの無理だろうという動きをしない限り、腕は動きません。
そこを、弓の竹の弾力と、手首の回転、指の微妙な動きによって、何とか実現するのが、
擦弦楽器の弓の運動なのです。
それを、昔からはこういう形だからと無理やり言われても、大人になってからの頭と体はなかなか馴染めませんね。
それをうまく説明してほしいのですが、なかなか、、
致し方ないので先生に言われたようにやっては見ても、
子供のころから習い覚えた技を,なかなかにはまねできませんね。
体操競技などのこと考えてください。
或いはもうすぐ始まるオリンピックのスキーのジャンプ、
スキーのジャンプ台に立ってみたことありますか?
かなり高いところが平気な私でさえ、あれを滑り降りるのだと思った瞬間、恐怖で叫びそうになりますね。
よくバンジージャンプに挑戦する人がいます。
あれも慣れがあるのでしょうが、
たぶんですよ、平気でバンジージャンプ飛ぶ人でも、スキーののジャンプをいきなりは難しいのではないでしょうかね。
スキーのジャンプも最初は5メートル10メートル20メートルと伸ばしていくんだそうです。
何事にも慣れというのはあります。
しかし、弓まっすぐに動かして、そこで手首を返して、言われても、
もうこれは慣れるしかありません。
しかしそこが問題なのでしょう。
ただ単に慣れるといっても、意外と微妙なところが違うような気がしませんか?
まったく同じように出来るとしたら、同じような音が出るはずなのです。
ですから、聞いてみましょう、何故?
何故そこでそういう動きをするのか、
弓は背中で弾くんだといわれても、
何故ですかと聞くほかないのです。
何故ならば言われてできる人は、解っているからです。
丹田に気を込めてとも言われます。丹田ってどこよ、
気を込めるってどうやるのよ?
すごく素朴な質問かもしれません、
意外と言っている人が理解していない場合も多いのです。
何故なら、私なんかなぜ自分が鉋の刃を平らに研げるのか、
指先だけに力を入れて、刃物を支え指を通して砥石の平らな面を感じて、
手首と腕の力を抜いて、背中の力で刃を動かすのです。
ね、解らないでしょう。
それでも、私なんかでも聞かれているうちに何とか考えて答えを出そうとはします。
まずは砥石を平らに常にしておく。
指先だけでカンナの刃を砥石の上に立てておくように何回も練習する。
まずは小さく前後に動かす。
1センチ、2センチと、
その時に手首の動きを教えます。
それができるようになったら、スピードを上げて手を前後に動かすように慣らします。
こうやって少しずつ、
またゆっくり動かして刃が平らな面から離れないように、
そうすると次第に指先が平らな面を感じるようになります。
それまで、1年。
これでもうまくは説明できていないです。
もっと筋肉の事、筋の事、手の関節の動きの事などきちっと説明しないとだめでしょう。
そうですね一つずつ、聞きながらやっていくしかないようです。
ですから皆さん、何故?と、質問してはいかがですか?