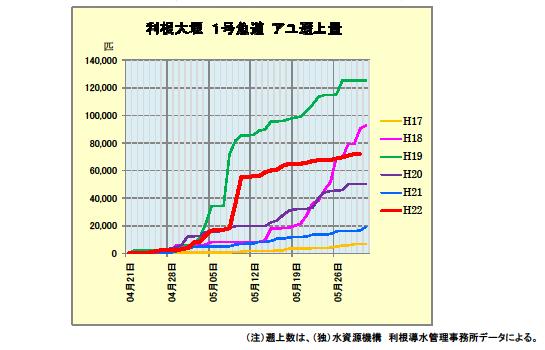前回に引き続き、コナラ属の虫えい(虫こぶ)Ⅱです。
最初の写真はクヌギエダイガフシで昨年のものです。クヌギエダイガタマバチによって若い枝に作られ、果実と間違えるような形の虫えい(虫こぶ)です。ほぼ球形でイガ状の突起が反り返りながら群生し、突起には軟毛が密生しています。8月上旬頃から出来始め9月頃にサナギ、10月に成虫が羽化して秋から春にかけて冬芽に産卵するそうです。冬芽の雄花に出来た虫えいがクヌギハナコツヤタマフシ(両性世代)になります。
ナラハグキコブフシ(タマバチ科)
カシワの葉柄に作られたこぶ状の虫えい(虫こぶ)です。

コナラやミズナラにも作られ、えい形成生物はナラハグキコブタマバチで葉裏側の発達が大きく、葉表は窪みがあります。虫えいの完熟は5月下旬頃で、6月上旬に蛹になり、中旬には羽化するそうです。
クヌギハクボミフシ(トガリキジラミ科)
クヌギの葉に形成される小さな突起状の虫えい(虫こぶ)です。えい形成生物はクリトガリキジラミで、一匹ずつ葉裏に固着して吸汁しています。

成虫で越冬して4月頃にナラやカシ類の新葉に産卵し、5月頃から黄緑色のいぼ状の虫えいが目立ち始めます。
コナラエダタマフシ?
コナラの小枝に作られたタマフシで名前は不詳。

クヌギのクヌギエダタマフシ(タマバチ科)に似ているのですが・・・
にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()
ポッチとクリックお願いします。