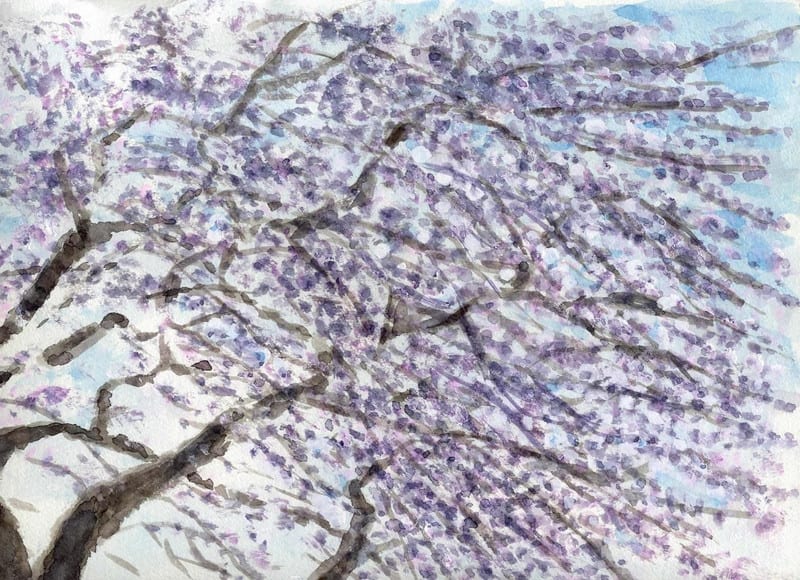わが家の庭のセッコク(石斛)です。10数年前、高知の従兄宅の庭にぶら下がっていたのをプレゼントされました。以来、毎年4月下旬になると、白というより淡いピンクと言った方がよさそうな花が風に揺れ、顔を近づけるとほんのり香りを漂わせています。
もともと、森林の老木やゴツゴツした岩肌にへばりついて育つラン科の植物。
だから、湿気は必要で、僕は晴天が続くようだと水やりをします。でも肥料はあまり気にかけず、年に1度か2度、少量の油かすか液肥を与えるくらいです。日当たりが比較的良くて風の通るところなら、放っておいても育つようです。
木にくっつけたり、ミズゴケで巻いたり。素焼きの小さな鉢などで育てることも多いようですが、僕は写真のように長さ15センチほどの棒切れを何本も組み合わせたところに載せて、ぶら下げています。もらった時がそうだったからですが、株数が多くなったので数年前に倍近い大きさに作り直しました。
しかし、ご覧のように再び過密状態。時期を見て株分けしようと思っています。
このセッコクが何という品種なのか分かりません。どのくらい品種があるのかも知りません。
先日、近くの園芸店で白や薄紅、薄紫、黄色がかった花など、20個ほどのセッコクが並んでいるのを見かけましたが、全て品種名が違うのには驚きました。この花も、愛好家たちの世界が広いことが伺えます。
花言葉は「(あなたは)私を元気づける」だそうです。

自宅庭の吊り下げプランターに咲くナスタチウム(キンレンカ)。先日、軒下で雪と寒波に負けずに3ヶ月間も咲き続けた一輪のミニバラを紹介しました(3月24日掲載)が、このキンレンカも軒下で冬を乗り切ったのです。
わが家にキンレンカが登場したのは10数年前、瀬戸内海を見下ろす高台の民宿の庭で咲き、朝食のサラダに添えられていたのがきっかけ。それがこぼれ種で咲くと知り、毎年育てています。
しかし、この花は耐寒性、耐暑性とも弱いのが特徴。わが家でもこぼれ種で苗は生えてきますが、夏の猛暑と冬の寒波にやられてしまいます。
そこで苗を見つけると小さなポットに移し、冬はガラスボックス(ヒーター装置などはありません)で育てます。しかし、ガラス窓を閉め忘れて寒波で枯らしてしまったことは、1度や2度ではありません。
写真のナスタチウムは、このような保護を止め、自力で育つのを見守ることにしました。
昨年の晩秋、プランターにこぼれ種の苗がいっぱい出ているのを見て、プランターをそのまま軒下へ移動させておきました。
苗をポットに植え替えることも考えましたが、根を崩すと根つきがよくないのもこの花の特徴で、苗と苗の間隔が2センチ前後しかない苗をポットに移植するには、何本かを間引きしなければなりません。他にも小さな芽が飛び出しそうになっている種もいくつかありました。
「このままにしておいて、苗たちの『生存競争』を見てみよう」。やや無責任で、常識を無視した栽培を試みることにしたのです。
軒下は雨や雪からは逃れても、寒気は避けられません。
伸びていた葉と茎の多くは冬の間に次々枯れ、周りの葉で寒風が直接当たるのを免れたのか、プランターの中央寄りの茎が葉を少し残すだけになりました。
でも、生き残っていた茎に新芽ができ、花芽もできて4月上旬から開花が始まったのです。
円形プランターの直径は25センチほど。そこに約15本の茎。せいぜい4、5本が限度でしょうから、明らかに「チョー密植」です。
液肥を多めにやればいい、というものでもないようです。草丈は短く、茎の太さも箸の先の方ほどのもあれば、爪楊枝ぐらいしかないものまでさまざま。葉も花数も、明らかに小さく少ないですね。
これまでのような、吊り下げプンターから沢山の花が垂れ下がる姿は期待できそうにありません。
東海地方の平野部を彩った桜前線が去って、早くも2週間余。吹き出した若葉が日に日に大きく、色濃くなっています。
遅くなりましたが、3月31日に紹介した岡崎市奥山田の枝垂れ桜を描いてみました。
あまりにも愚作なので止めようかと思いましたが、4月5日更新のブログで「2014桜(1)」としたのだから(2)もなければ、と掲載しました。
遠くから見た姿と、枝が折からの強い風に流される様子です。
この花の咲き始めは薄紅白色、満開になるにつれて白っぽくなるのが特徴だとか。見物に出かけた時は、ちょうど満開。青空に白い花は描きにくいので、枝が風に流される様子は逆光からとらえました。
枝周りが20メートル四方の大きさ。優美な姿は全国でも指折りの枝垂れ桜でしょう。僕に能力があれば、もっと素敵に描けたのに・・・。
このあと出かけた岐阜県根尾谷の淡墨桜もそうですが、圧倒的な存在感のある対象は描くのが難しいですね。
でも、これからも挑戦したいと思っています。
名古屋の松坂屋美術館で開催中の第69回春の院展の名古屋展(4月20日まで)を観てきました。今回は昨年12月19日掲載のブログ「日本画界の新星と85歳の新入生」で取り上げた「新星」が今回も入選したのに加えて、僕の親戚からも初入選者が出るという嬉しいニュースが重なりました。
「新星」として紹介した愛知県立芸術大学院生・平田望さんは、一昨年、同大学4年生で「秋の院展」に初入選。大学院に進んだ昨年の秋も入選。そして今回、春の院展に初入選したのです。画家の道を順調に歩んでいると言えるでしょう。
彼の相次ぐ入選を誰よりも喜んでいるのが、平田さんの祖父で、昨年秋に僕の通う水彩画教室に入ってこられた「85歳の新入生」平田正雄さん。「私も孫の頑張りに負けてはおれません」と、人生初めての「お絵かき」を楽しまれています。お二人に心から拍手です。
親戚の初入選者は、福岡県北九州市在住の松本由美子さん(65)。嫁御のお母さんです。
「芸術に対する憧れがあって以前から絵を楽しんでいたのですが、子育てや勤めにひと区切りついた10年ほど前から本格的に絵筆を取るようになりました」と松本さん。着実に力をつけて福岡県展や北九州市展などで入選・入賞するようになり、「春の院展初入選」の喜びにも浸ることができました。
絵のモチーフは身近なところで見つけることが多いとか。今回入選した「花の符」も、北九州市内の廃屋跡で出会ったヤマフジを題材にしたそうです。名古屋展には会場の都合で展示されてはいませんが、全作品集を手にして、その見事さにしばらく見とれました。
藤まつりなどで見るフジとは違う優しくて清楚な花の感じや、長く垂れる蔓の生命感。そして巧みな緑の使い分け。
「interminable fairy tale」
松本由美子さんの作品
「花の符」
(日本美術院「第69回春の院展全作品集」から)

今年の花見詣でを、岐阜県本巣市の「根尾谷淡墨桜」で締めくくりました。樹齢の推定約1500年。地元民ら多くの人たちの献身的な再生・延命・保護活動によって、国の天然記念物に指定された淡墨桜。10日に訪ねると、花舞台の主役であり続ける大スターは、今年も白鳥が羽を大きく広げるようにして迎えてくれました。
今回の淡墨詣では、JR大垣駅で乗り換える樽見鉄道を利用しました。花見期の渋滞に巻き込まれる車よりも、新緑に包まれた根尾川の渓谷や無人駅を各駅停車で行く方が、と考えたからです。結果は、一両だけ(2両編成のダイヤもある)の車内で立ち続ける1時間余になりましたが、車窓からの風景は期待通りでした。
樽見駅から歩いて15分。淡墨桜のある公園です。
ちょうど満開。幹周りが10メートルほど、枝回りは20メートルから27メートルほどあるという優雅な姿は圧巻です。心なしか数年前に会った時よりも若くなったように感じました。
背丈が70センチほどの淡墨桜の苗木も売られていました。
「2、3年後には花が咲きますか?」と、やや高齢の女性客。
「いや、10年は待ってもらわないと」と苗売のおじいさん。
「そんなに?私が持たないわ」と笑う女性。
春の日差しを浴びた公園は、小説や歌、絵画でも親しんだ淡墨桜のホンモノとの出会いや、山里の味を楽しむ人でいっぱいです。
そんな中でオカリナの音色が聞こえてきました。地元の根尾中学校の生徒たちによる演奏です。
この日は「総合的な学習」の時間。30人ほどの全校生が淡墨桜の花見にやってきた人たちと触れ合い、自分たちの町をより深く知ってもらおうというわけです。
オカリナでの「ふるさと」の演奏や、班に分かれて客たちを案内したり・・・。
ある班に耳を傾けると、自分たちで作成したパンフレットを手渡して淡墨桜の歴史、桜や特産の菊花石についての豆知識などを披露していました。
「淡墨桜は長細い葉のエドヒガンという種類ですが、丸い葉で桜餅を包んでいるのはオオシマザクラ。この2つの品種をかけ合わせて改良したのが、ソメイヨシノ(染井吉野)です」
「近くに、うすずみ温泉というのもありますから、楽しんでください」
淡墨桜を指差して、こんなクイズも。「淡墨桜の枝を支える支柱が立っていますが、全部で何本あるでしょう?」
「34本」と僕。「惜しい」と生徒。周りから「じゃあ37本」「39本」と声が飛びます。
正解は「44本です」。ここでも笑いと拍手。生徒たちだけでなく、私たちも「生きる学習」を楽しみました。
初めて出会った人に話しかけ、ガイドをしたり、オカリナのリクエストに応える中学生たち。
もう半世紀以上前だけど、僕にもこんなに目を輝かせた時代があったんだなあ。
そこで僕は僕自身に対して、こんな宿題を課してみました。
名古屋市博物館の3階ギャラリーで8日から始まった「ふわくの会」展、という名の絵画展を拝見してきました。僕が通う水彩画教室の仲間である、富岡僉治さんが出展していると聞いて出かけたのですが、教室内の多くが透明水彩絵の具を使っている中でアクリル画を描き続ける富岡さんと同様、絵具もジャンルも自由気ままな楽しい作品展でした。
「ふわくの会」の由来は?
会場の受付で、少々ぶしつけかなと思いつつ、こんな質問をしてみました。
「不惑」といえば論語の「40にして惑わず」を連想しますが、40歳は数十年前の僕と同年配の集まりのようだし、と思ったからです。
受付におられた会のまとめ役だという鈴木利昭さんが「そうした質問にお答えするために用意しておきました」と笑いながら、一枚の紙をくれました。
そこには「ふわくの会」綱領として、こうありました。
「ふわくの会」とは、惑わされることなく、絵の道に励むことをモットーにする集団として支えあっていくことを大切にする。
絵画のジャンルは自由=油彩、水彩、日本画、パステル、アクリル、鉛筆・・・。
画題も自由=風景、静物、人物、動物・・・。
とにかく何でも結構、というわけです。
だから、会としての講師がいるわけではなく、教室もなく、スケッチ旅行などもありません。ふだんは、それぞれがカルチャーセンターや絵画教室で学んだり、教えたりしています。
そして年1回、この時期に名古屋市博物館にF6号以上F30号以内の作品を1人3点を目標に持ち寄って、今回のような作品展を開いているのです。運営会費は1人当たり3000円。今回で4回目だそうです。
今回の出展者は13人。「どうです。あなたも入りませんか」と鈴木さん。
展覧会は13日(日)まで。みなさんも、ご覧になって作品発表の場に加えられてはいかがですか。

名古屋のサクラは、この週末がフィナーレでしょうね。僕も散歩コースにある公園から山崎川などの花見どころまで、桜三昧の一週間でした。
2枚を絵にしてみました。
㊤は山崎川堤防のソメイヨシノの並木の中で、数本見かけた枝垂れ桜です。絵も対岸のソメイヨシノを入れて描きました。
僕は植物を描いていく時、葉や花を彩色するのも楽しいですが、もっと楽しいのは枝を入れる時。雑然としていた画面が一気にしまり、木全体や花に命を吹き込んでいるように思えるからです。
この枝垂れ桜もピンクや紫がかった花をポンポン置いたあと、枝入れを楽しみました。それにしても垂れ下がる枝の数は多いですね。これも随分間引きしました。
㊦は、どこでも目にする枝の広がった古木の花。これまで、遠くから全体をとらえたり、近寄って一本の枝の花や幹のどっしり感を描くことが多かったですが、今回はびっしり付いた花のひとつ一つをできるだけ多く描き、遠くに覗く赤い屋根の建物を入れてみました。