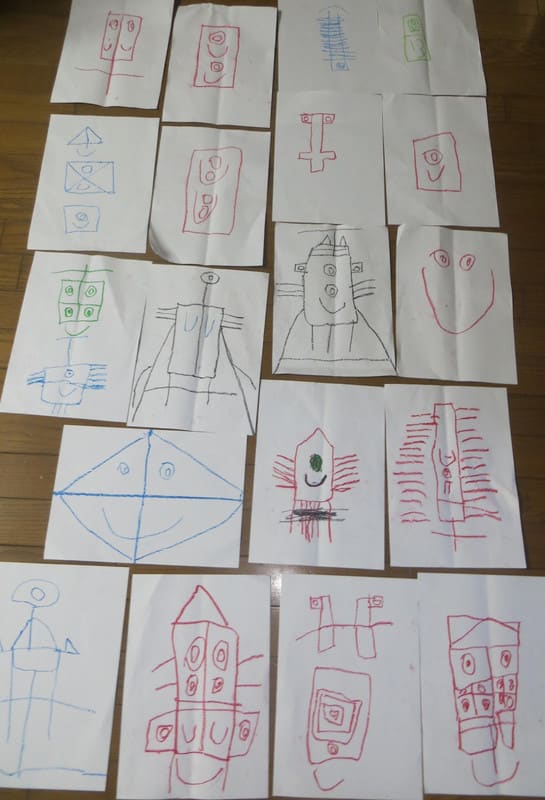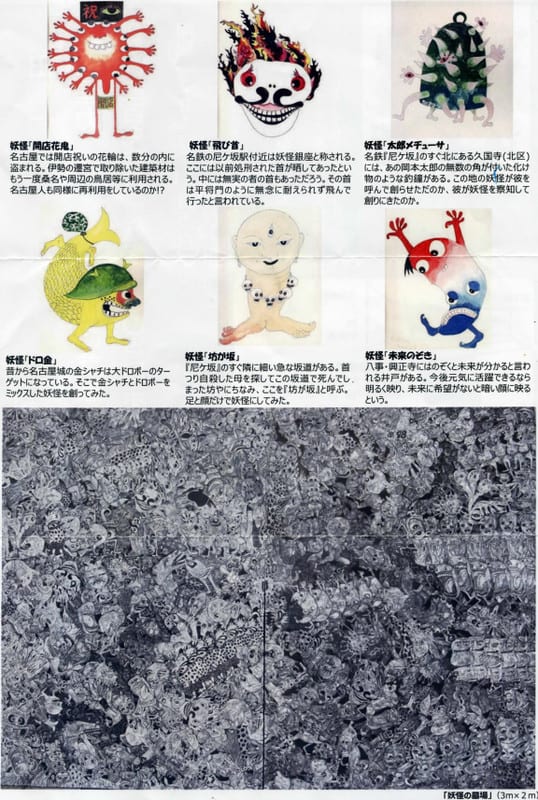「ヨーロッパの美術館と日本の美術館の違いは、鑑賞する側と美術館との距離感だ」という言葉をよく耳にします。ヨーロッパの美術館で、作品を前に模写やスケッチをする光景を目にするたびに、僕もそう感じます。先日訪れたパリのルーブル美術館ではその思いを一層強くしました。
巨大な彫像の前で2、30人ほどの児童がスケッチブックを開き、鉛筆を走らせています。その後ろに立ち、スケッチする大人の姿も。児童を引率する先生ではなさそうです。
30号ほどの展示作品の前では、イーゼルのキャンバスに絵筆を走らせるご婦人。年のころは僕と同年配とお見受けしました。近くには一本の筆を口にくわえ、手にした筆を力強くキャンバスに向ける男性。こちらも同年配でしょう。
デジタルカメラで展示作品の一部を撮影し、拡大した再生画面を見ながら絵の具を重ねている人もいます。テラスでは美術専攻の学生らしい若者たちが、思い思いの場所に陣取ってデッサンしています。
模写する人の周りには、一般客の人だかりができています。絵筆の動きに見入ったり、うなづいたり。描く人もそれを楽しみ、モチベーションを高めているようです。
こんな状況を一般客が「鑑賞の邪魔だ」と不快感を持っているようには、全く思えません。
ルーブル美術館でのこうした光景は、昨日今日始まった訳ではありません。日本の洋画界の巨匠・黒田清輝らも若いころルーブル通いで腕を磨いたと言われています。
もちろん、勝手気ままに模写できるわけではありません。きちんとした申請手続きが必要です。ブログにある体験談などによれば、外国人だと滞在許可書や大使館の証明書などが必要。認められれば曜日などに制限はあっても、入場料なしでかなりの期間、展示作品と向かい合い、絵筆を走らせることができるそうです。
まさに芸術の開放ですね。そこには人種、国籍、性別、年齢などの区別はありません。美術作家を目指す人たちのたちのために、だけでもありません。美術を愛好する全ての人々を平等に招き入れ、育てていこうという文化があるのでしょう。
日本でも、ギャラリートークや子供たちにホンモノの美術と対面する機会を設けるなど、鑑賞者との距離感を無くそうとしている美術館が増えてきたようです。
作品の細部を見ようと顔を近づけたり、同行者と「この部分の色が生きているね」などと指差す(触れないように、です)だけで係の人がとんできそうなピリピリ感は緩和して欲しいですね。美術館を出るときの満足感を半減させない努力を期待したいものです。