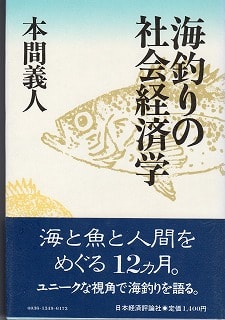本間義人 「海釣りの社会経済学」読了
“社会経済学”というとおり、中身は釣りエサの流通の話や釣具の売上高の話、釣り人が魚を釣る権利はどこまで守られるのかなど釣りと人間社会のかかわりについて書かれている。かなり変わった視点の本だ。大半は環境汚染の問題に費やされているがこれはこれで面白い。
本が書かれた年は昭和56年。高度経済成長が終わり、公害問題も一段落、オイルショックの大不況から復活し、これからまさにバブル経済の時代に突入しようかという時代だ。
釣りを取り巻く事情も大きく変わった時代だったようだ。
僕の当時の年齢は18歳、暗黒の受験生時代が終わるまであと1年というところだ。この本にも書いてあるが、オキアミが出現してほぼ一般的になった時代であった。僕の紀州釣りのキャリアも湖産海老ではなくてオキアミのエサからスタートしたのもうなずける。
父親からも、「これはオキアミというのだ、使いやすいぞ。」などと教えてもらったような記憶がある。ちなみのそれまでも湖産海老は、一番上に氷の固まりを入れた木製の三段式の箱の中に入れてしずくで生かしながら釣っていた。釣った魚はその氷の入ったところに入れることができて、イスにもなっている。そこに腰掛けてヌカ団子を投げるというスタイルが一般的だったのだ。多分このブログを読んでくれている方々は誰も見たことがないだろう。今の水箱ともかなり違うものだ。
生きたまま湖産海老を海底まで届けるため、砂は使わずに“石粉”を使ってかなりやわらかく仕上げていた。
フカセ釣りもクズの湖産海老を水に溶かして撒きエサにしていたそうだ。(いまのボイルのオキアミのような使い方なのだろうか?)
そういう意味では紀州釣りを含めて大きな転換期だったのかもしれない。
釣具屋さんも大きな転換期のころで、和歌山市にも初の大型釣具店「オーシャン」が矢の宮神社のそばにオープンしたのはこの年の4,5年前だったと思う。開高健の「オーパ!」が引き金になって日本での何回目かのルアーフィッシングブームがピークを迎えたのもこの頃だ。日本製のルアーなんて皆無で、ヘドンやラパラ、う~ん、あとは名前を忘れたがアメリカ製やヨーロッパ製のルアーやロッドにあこがれていたものだ。店舗が大きくなり、ダイエーなんかも釣具を扱うものだから商品の値崩れも激しく、釣具というのは3割引は当たり前という時代に突入したのもこの頃だったらしい。ちなみに上州屋は創業昭和38年で、業績を一気に伸ばしたのもこの頃だったらしい。釣具メーカーの昭和55年の売上第2位はオリムピックだ、隔世の感がある。
かなり古い本だったので、はたして読んで面白いのかと思ったが、なかなか、時代はつながっているのだ。けっこう面白い内容だった。
現在、日本国中どこを見ても水質はこの時代からあまり変化はないようだが、釣りエサはほとんどが海外から調達されるようになってしまい、麦の価格は国際相場に左右される。地震が起こるとアミエビとオキアミは高騰し、購入制限まで出てくる。PEラインも大きな革命のひとつだろう。僕みたいなヘッポコ釣り師が真鯛を釣るというのはこのラインなくしてはありえないのだ。
釣具メーカーもトップ3より下位のOEMメーカーのほうが勢いがいいみたいだし、小売店も中古釣具屋さんが上場してしまう。
釣り人自身の価値観も大きく変わっているのようで、魚を多く釣ることだけが喜びではないようだ。しかし、釣りガールは早くどこかへ消えてくれ。海は男の世界なのだ。(多分、今年の冬を越すことはできないはずだからあまり心配してはいないが・・・)
そういう意味では大きな変革の時代に入ってきたのかもしれない。
まあ、どんなに時代が変わっても、どこかで釣り糸をたらすことができれば僕は満足だ。
“社会経済学”というとおり、中身は釣りエサの流通の話や釣具の売上高の話、釣り人が魚を釣る権利はどこまで守られるのかなど釣りと人間社会のかかわりについて書かれている。かなり変わった視点の本だ。大半は環境汚染の問題に費やされているがこれはこれで面白い。
本が書かれた年は昭和56年。高度経済成長が終わり、公害問題も一段落、オイルショックの大不況から復活し、これからまさにバブル経済の時代に突入しようかという時代だ。
釣りを取り巻く事情も大きく変わった時代だったようだ。
僕の当時の年齢は18歳、暗黒の受験生時代が終わるまであと1年というところだ。この本にも書いてあるが、オキアミが出現してほぼ一般的になった時代であった。僕の紀州釣りのキャリアも湖産海老ではなくてオキアミのエサからスタートしたのもうなずける。
父親からも、「これはオキアミというのだ、使いやすいぞ。」などと教えてもらったような記憶がある。ちなみのそれまでも湖産海老は、一番上に氷の固まりを入れた木製の三段式の箱の中に入れてしずくで生かしながら釣っていた。釣った魚はその氷の入ったところに入れることができて、イスにもなっている。そこに腰掛けてヌカ団子を投げるというスタイルが一般的だったのだ。多分このブログを読んでくれている方々は誰も見たことがないだろう。今の水箱ともかなり違うものだ。
生きたまま湖産海老を海底まで届けるため、砂は使わずに“石粉”を使ってかなりやわらかく仕上げていた。
フカセ釣りもクズの湖産海老を水に溶かして撒きエサにしていたそうだ。(いまのボイルのオキアミのような使い方なのだろうか?)
そういう意味では紀州釣りを含めて大きな転換期だったのかもしれない。
釣具屋さんも大きな転換期のころで、和歌山市にも初の大型釣具店「オーシャン」が矢の宮神社のそばにオープンしたのはこの年の4,5年前だったと思う。開高健の「オーパ!」が引き金になって日本での何回目かのルアーフィッシングブームがピークを迎えたのもこの頃だ。日本製のルアーなんて皆無で、ヘドンやラパラ、う~ん、あとは名前を忘れたがアメリカ製やヨーロッパ製のルアーやロッドにあこがれていたものだ。店舗が大きくなり、ダイエーなんかも釣具を扱うものだから商品の値崩れも激しく、釣具というのは3割引は当たり前という時代に突入したのもこの頃だったらしい。ちなみに上州屋は創業昭和38年で、業績を一気に伸ばしたのもこの頃だったらしい。釣具メーカーの昭和55年の売上第2位はオリムピックだ、隔世の感がある。
かなり古い本だったので、はたして読んで面白いのかと思ったが、なかなか、時代はつながっているのだ。けっこう面白い内容だった。
現在、日本国中どこを見ても水質はこの時代からあまり変化はないようだが、釣りエサはほとんどが海外から調達されるようになってしまい、麦の価格は国際相場に左右される。地震が起こるとアミエビとオキアミは高騰し、購入制限まで出てくる。PEラインも大きな革命のひとつだろう。僕みたいなヘッポコ釣り師が真鯛を釣るというのはこのラインなくしてはありえないのだ。
釣具メーカーもトップ3より下位のOEMメーカーのほうが勢いがいいみたいだし、小売店も中古釣具屋さんが上場してしまう。
釣り人自身の価値観も大きく変わっているのようで、魚を多く釣ることだけが喜びではないようだ。しかし、釣りガールは早くどこかへ消えてくれ。海は男の世界なのだ。(多分、今年の冬を越すことはできないはずだからあまり心配してはいないが・・・)
そういう意味では大きな変革の時代に入ってきたのかもしれない。
まあ、どんなに時代が変わっても、どこかで釣り糸をたらすことができれば僕は満足だ。