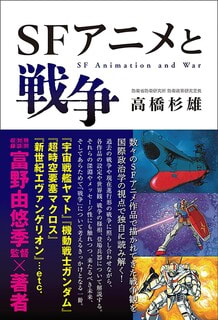高橋杉雄 「SFアニメと戦争」読了
以前、よく似たタイトルの「アニメと戦争」という本を読んだことがある。この本はアニメ制作者と戦争の距離感を主眼において書かれた本であったが、「SFアニメと戦争」はアニメファンであると同時に、原題軍事戦略を専門とする国際政治学者が、SFアニメで描かれる戦争について、国際政治学における安全保障の視点から分析をおこなったというものである。現実の世界で起こってきた戦争とSFアニメで描かれる戦争のギャップを見ていこうというものだ。まあ、柳田理科雄の著作の軍事バージョンといったところか。ただ、柳田理科雄よりもかなりお堅い文章なのでそういったところの面白さはない。
読み始める前、そのギャップというのはアニメでは絶対に表現できない戦場の臭いや、主人公だけがどうして生き延びることができるのかというようなものかと思ったが、そこは全然違っていた。僕が考えていたのは「戦争」ではなく、「戦闘」であったというのをこの本を読んではっきりした。
小学生のころの国語のテストで、「平和」の反対語を問うという問題があった。この答えは「戦争」であったのだが、この答えにはどうしても違和感が残った。それが「戦争」と「戦闘」の違いであったのだ。
19世紀のプロイセンの軍人であったカール フォン クラウゼヴィッツが著した「戦争論」に書かれている戦争の定義というのは、『戦争は、政治的行為であるばかりでなく、政治の道具であり、彼我両国の間の政治的交渉継続であり、政治におけるとは異なる手段を用いてこの政治交渉を遂行する行為。』ということだ。すなわち、戦争も平和もある状態を示しているということで同等なのでお互いを反対語とすることができるのである。
SFアニメの中の戦争についてはとりあえず置いておいて、国際政治学が考える戦争についてまずは書いておく。
戦争が起きる原因について、ケネス・ウォルツという国際政治学者が、人間、国家、国際システムの三つに帰するとしている。それぞれ順番に、第1イメージ、第2イメージ、第3イメージと名付けているが、求められる戦争の原因とは、
人間:人間の欲望や邪悪さかに戦争の原因を求める
国家:戦争を志向しやすい国家が存在する。資本主義は帝国主義を追究する傾向にあり、戦争を志向しやすくなる。
国際システム:主権国家が最高の権威と最大の権力を有している。これらの国家の上位に立つ超国家組織が存在しない(アナーキーとよぶ)ことがそれぞれの国家は自己の生存を自助に頼らざるを得ない。その場合、最も安全なのはほかの国に優越した軍事力や経済力を持つということになる。
だから、基本的に世界から戦争はなくなることはないし、各国の軍備は縮小されることはない。ニュータイプ理論における、人々が心からわかり合うことができれば戦いを無くすことができるというのは理想論でしかない。
これを元にSFアニメで繰り広げられる戦争が起こった理由をみてみると、大半は敵キャラがいかにもというようなデザインの軍服を着ているくらいなので第1イメージ、もしくは第2位イメージの中で起こっているとみえる。
逆に、戦争が起こらない条件というのは次のふたつだ。これは、ケネス・ウォルツというアメリカの国際政治学者が論じたものである。
①敵と味方のすべての情報が手に入っており、戦争になった場合の結果が予測可能である。合理的な政策決定者であれば、負けると分かっている戦争をあえてたたかうことはない。②国家が約束を絶対に守ることが保証されていること。
である。これもそんな情報を得ることは実質不可能であるので、世界から戦争が無くなることはない。
その他、戦争には、「必要による戦争」、「選択による戦争」という分類がある。これは、アメリカの外交政策の専門家であるリチャード・ハースという人が論じたものであるが、「必要による戦争」は、戦わなければならない状況で開始した戦争、「選択による戦争」は、強い法的な根拠や国際世論の支持が無いのにもかかわらず開始された戦争である。実世界では、前者は1991年の湾岸戦争、後者は2003年のイラク戦争であると言われる。
SFアニメの世界では、前者は地球側から見たガミラスとの戦争、後者は、ジオン公国が起こした一年戦争がそれに当たりそうである。
これらの論理から、SFアニメに描かれている戦争にリアリティがあるかどうかというと、それは間違いなく、ない。
こんなことを事細かく描いていたら1クールで放送が終わらないし、かなり退屈になってくる。「銀河英雄伝説」はそういう意味ではかなり特異なSFアニメであったのだと思う。
元々、SFアニメの主人公のほとんどすべては政治家でもなく上級軍人でもなく前線で戦う一戦士である。そこでは政治的なかけ引きは関係ない。毎回、「機動戦士ガンダム」の次回予告の最後にナレーションで入る、「君は生き残ることができるか」ということがすべてだ。
まあ、これを最初に言ってしまうとこの本の存在意義がなくなってしまうのではないかと思うが、前書きに、『SFアニメは報道でもドキュメンタリーでもなく商業作品としての創作であり、戦争を描くことそれ自体が目的ではない。多くのSFアニメは登場人物たちが織りなす群像劇であり、その中での主人公たちの成長が主題である。いってみれば、戦争は彼らの成長を描く上での舞台装置でしかなく、国際政治学における議論に忠実に戦争を描くことが目的ではないし、そもそもその必要もない。』と本当に身もふたもないことを書いている。
しかし、それでも著者がこの本を書くのは、『SFアニメが広く視聴されるようになり、社会にある程度の影響力を持つようになっている今では、創作だからといって、現実世界の戦争のダイナミクスを完全に無視したかたちで戦争を描いていくことは好ましくないように思われる。・・・アニメを通じて戦争を感じたり、あるいは知ったつもりになる視聴者は少なくないように感じられる。』からだという。
確かにそう思う。僕でも、徴兵されて前線に出たとしても、主人公になぞらえて自分は多分死ぬことはないだろうと思っている。そんなはずはないのであるが・・。
国際政治としての戦争を知るというところまでいかなくても、戦場の臭いや音、そういったものに想像を巡らせるという必要はあるのではないかとこの本を読みながら思うのである。
この本の内容のおそらく三分の一は取り上げられているアニメのあらすじになっている。なんだかムダのようにも思えるが、僕にはありがたかった。すべての回を見たことがあるアニメもあったし、数十年前に観たきりのものあった中、あのアニメのストーリーの本質はそこにあったのかとか、そういえばそんなストーリーだったなと改めて思い出す機会になった。還暦を過ぎてアニメのストーリーなんてどうでもいいじゃないかと思われるかもしれないが、アニメにどっぷり浸かって生きてきた僕にとってはけっこう重要なところでもあるのである。
この本を読みながら、トランプ大統領の動きに思いを巡らせていた。ロシアのウクライナ侵攻とイスラエルのガザ地区への侵攻を終結すべく、いろいろな動きを見せている。ガザではパレスチナの難民を移住させアメリカが統治すると案を打ち出した。ウクライナでもロシアが占領している地域を放棄させて戦争を終わらせようとしているのだというような報道もある。
それぞれ、到底受け入れることができないような解決案だが、この本の著者が言うように、戦争が無くなることはないというのなら、また、今、これらの問題を解決する妙案がないのであれば、無茶苦茶な案を使ってもとりあえず戦争を終わらせ、次の世代にそれを委ねるというのもありうる考えなのではないかと思うこともある。そうすればとりあえず、今死ぬ人はいなくなるということは間違いがない。
これは僕の考えではなく、「銀河英雄伝説」の主人公が言った、『恒久平和なんて人類の歴史上なかった。だから私はそんなもの望みはしない。だが何十年かの平和で豊かな時代は存在できた。吾々が次の世代に何か遺産を託さなくてはならないとするなら、やはり平和が一番だ。そして前の世代から手渡された平和を維持するのは、次の世代の責任だ。それぞれの世代が、後の世代への責任を忘れないでいれば、結果として長期間の平和が保てるだろう。忘れれば先人の資産は食いつぶされ、人類は一から再出発ということになる。要するに私の希望は、たかだかこの先何十年かの平和なんだ。だがそれでも、その十分ノ一の期間の戦乱に勝ること幾万倍だと思う。』という言葉から思ったことだ。そんな短い平和を繋いでいくしかないということなのだが、トランプ大統領もそんなこと考えているとしたら、あながち変人でもないような気がする。(どうもそうでもなさそうだが・・)
たかがアニメ、されどアニメだ。創作とはいえ、現実世界に対して意見する力も持っているのである・・。
以前、よく似たタイトルの「アニメと戦争」という本を読んだことがある。この本はアニメ制作者と戦争の距離感を主眼において書かれた本であったが、「SFアニメと戦争」はアニメファンであると同時に、原題軍事戦略を専門とする国際政治学者が、SFアニメで描かれる戦争について、国際政治学における安全保障の視点から分析をおこなったというものである。現実の世界で起こってきた戦争とSFアニメで描かれる戦争のギャップを見ていこうというものだ。まあ、柳田理科雄の著作の軍事バージョンといったところか。ただ、柳田理科雄よりもかなりお堅い文章なのでそういったところの面白さはない。
読み始める前、そのギャップというのはアニメでは絶対に表現できない戦場の臭いや、主人公だけがどうして生き延びることができるのかというようなものかと思ったが、そこは全然違っていた。僕が考えていたのは「戦争」ではなく、「戦闘」であったというのをこの本を読んではっきりした。
小学生のころの国語のテストで、「平和」の反対語を問うという問題があった。この答えは「戦争」であったのだが、この答えにはどうしても違和感が残った。それが「戦争」と「戦闘」の違いであったのだ。
19世紀のプロイセンの軍人であったカール フォン クラウゼヴィッツが著した「戦争論」に書かれている戦争の定義というのは、『戦争は、政治的行為であるばかりでなく、政治の道具であり、彼我両国の間の政治的交渉継続であり、政治におけるとは異なる手段を用いてこの政治交渉を遂行する行為。』ということだ。すなわち、戦争も平和もある状態を示しているということで同等なのでお互いを反対語とすることができるのである。
SFアニメの中の戦争についてはとりあえず置いておいて、国際政治学が考える戦争についてまずは書いておく。
戦争が起きる原因について、ケネス・ウォルツという国際政治学者が、人間、国家、国際システムの三つに帰するとしている。それぞれ順番に、第1イメージ、第2イメージ、第3イメージと名付けているが、求められる戦争の原因とは、
人間:人間の欲望や邪悪さかに戦争の原因を求める
国家:戦争を志向しやすい国家が存在する。資本主義は帝国主義を追究する傾向にあり、戦争を志向しやすくなる。
国際システム:主権国家が最高の権威と最大の権力を有している。これらの国家の上位に立つ超国家組織が存在しない(アナーキーとよぶ)ことがそれぞれの国家は自己の生存を自助に頼らざるを得ない。その場合、最も安全なのはほかの国に優越した軍事力や経済力を持つということになる。
だから、基本的に世界から戦争はなくなることはないし、各国の軍備は縮小されることはない。ニュータイプ理論における、人々が心からわかり合うことができれば戦いを無くすことができるというのは理想論でしかない。
これを元にSFアニメで繰り広げられる戦争が起こった理由をみてみると、大半は敵キャラがいかにもというようなデザインの軍服を着ているくらいなので第1イメージ、もしくは第2位イメージの中で起こっているとみえる。
逆に、戦争が起こらない条件というのは次のふたつだ。これは、ケネス・ウォルツというアメリカの国際政治学者が論じたものである。
①敵と味方のすべての情報が手に入っており、戦争になった場合の結果が予測可能である。合理的な政策決定者であれば、負けると分かっている戦争をあえてたたかうことはない。②国家が約束を絶対に守ることが保証されていること。
である。これもそんな情報を得ることは実質不可能であるので、世界から戦争が無くなることはない。
その他、戦争には、「必要による戦争」、「選択による戦争」という分類がある。これは、アメリカの外交政策の専門家であるリチャード・ハースという人が論じたものであるが、「必要による戦争」は、戦わなければならない状況で開始した戦争、「選択による戦争」は、強い法的な根拠や国際世論の支持が無いのにもかかわらず開始された戦争である。実世界では、前者は1991年の湾岸戦争、後者は2003年のイラク戦争であると言われる。
SFアニメの世界では、前者は地球側から見たガミラスとの戦争、後者は、ジオン公国が起こした一年戦争がそれに当たりそうである。
これらの論理から、SFアニメに描かれている戦争にリアリティがあるかどうかというと、それは間違いなく、ない。
こんなことを事細かく描いていたら1クールで放送が終わらないし、かなり退屈になってくる。「銀河英雄伝説」はそういう意味ではかなり特異なSFアニメであったのだと思う。
元々、SFアニメの主人公のほとんどすべては政治家でもなく上級軍人でもなく前線で戦う一戦士である。そこでは政治的なかけ引きは関係ない。毎回、「機動戦士ガンダム」の次回予告の最後にナレーションで入る、「君は生き残ることができるか」ということがすべてだ。
まあ、これを最初に言ってしまうとこの本の存在意義がなくなってしまうのではないかと思うが、前書きに、『SFアニメは報道でもドキュメンタリーでもなく商業作品としての創作であり、戦争を描くことそれ自体が目的ではない。多くのSFアニメは登場人物たちが織りなす群像劇であり、その中での主人公たちの成長が主題である。いってみれば、戦争は彼らの成長を描く上での舞台装置でしかなく、国際政治学における議論に忠実に戦争を描くことが目的ではないし、そもそもその必要もない。』と本当に身もふたもないことを書いている。
しかし、それでも著者がこの本を書くのは、『SFアニメが広く視聴されるようになり、社会にある程度の影響力を持つようになっている今では、創作だからといって、現実世界の戦争のダイナミクスを完全に無視したかたちで戦争を描いていくことは好ましくないように思われる。・・・アニメを通じて戦争を感じたり、あるいは知ったつもりになる視聴者は少なくないように感じられる。』からだという。
確かにそう思う。僕でも、徴兵されて前線に出たとしても、主人公になぞらえて自分は多分死ぬことはないだろうと思っている。そんなはずはないのであるが・・。
国際政治としての戦争を知るというところまでいかなくても、戦場の臭いや音、そういったものに想像を巡らせるという必要はあるのではないかとこの本を読みながら思うのである。
この本の内容のおそらく三分の一は取り上げられているアニメのあらすじになっている。なんだかムダのようにも思えるが、僕にはありがたかった。すべての回を見たことがあるアニメもあったし、数十年前に観たきりのものあった中、あのアニメのストーリーの本質はそこにあったのかとか、そういえばそんなストーリーだったなと改めて思い出す機会になった。還暦を過ぎてアニメのストーリーなんてどうでもいいじゃないかと思われるかもしれないが、アニメにどっぷり浸かって生きてきた僕にとってはけっこう重要なところでもあるのである。
この本を読みながら、トランプ大統領の動きに思いを巡らせていた。ロシアのウクライナ侵攻とイスラエルのガザ地区への侵攻を終結すべく、いろいろな動きを見せている。ガザではパレスチナの難民を移住させアメリカが統治すると案を打ち出した。ウクライナでもロシアが占領している地域を放棄させて戦争を終わらせようとしているのだというような報道もある。
それぞれ、到底受け入れることができないような解決案だが、この本の著者が言うように、戦争が無くなることはないというのなら、また、今、これらの問題を解決する妙案がないのであれば、無茶苦茶な案を使ってもとりあえず戦争を終わらせ、次の世代にそれを委ねるというのもありうる考えなのではないかと思うこともある。そうすればとりあえず、今死ぬ人はいなくなるということは間違いがない。
これは僕の考えではなく、「銀河英雄伝説」の主人公が言った、『恒久平和なんて人類の歴史上なかった。だから私はそんなもの望みはしない。だが何十年かの平和で豊かな時代は存在できた。吾々が次の世代に何か遺産を託さなくてはならないとするなら、やはり平和が一番だ。そして前の世代から手渡された平和を維持するのは、次の世代の責任だ。それぞれの世代が、後の世代への責任を忘れないでいれば、結果として長期間の平和が保てるだろう。忘れれば先人の資産は食いつぶされ、人類は一から再出発ということになる。要するに私の希望は、たかだかこの先何十年かの平和なんだ。だがそれでも、その十分ノ一の期間の戦乱に勝ること幾万倍だと思う。』という言葉から思ったことだ。そんな短い平和を繋いでいくしかないということなのだが、トランプ大統領もそんなこと考えているとしたら、あながち変人でもないような気がする。(どうもそうでもなさそうだが・・)
たかがアニメ、されどアニメだ。創作とはいえ、現実世界に対して意見する力も持っているのである・・。