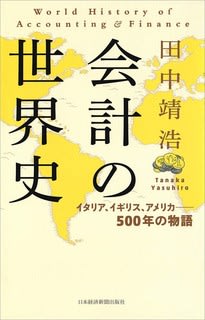田中靖浩 「会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語」読了
出向しているころに、財務諸表を読めるようにならねばといくつかの本を読んでみたがやっぱりダメだった。さすがにあともな会計の教科書を読まずに、いわゆる、「3分で理解できます!」っぽいタイトルのものばかり読んでいてはそれもいたしかたがない。頭のできもわるいのだからなおさらだ。
会社の研修でも丸二日勉強したけれども、それが去年の夏ごろだったのでもうすでに脳みそが硬化してしまっているのだからやっぱり理解できなかった。
実務でも投資回収の計算なんかをやるのだが、これが売り上げ見通しをまったく嘘っぽく設定するので嫌になっていた。それと、ファイナンスというものはすべてのものを貨幣価値に換算して経営の判断にするというなんの人情味もない考え方にもなんだかしっくりいかない感じがしていた。
こういうことがわからないからオワコンになってしまったのか、それとも会社に対しては面従腹背の姿勢でいたことがバレバレだったからなのか、どちらにしてももう、オワコンになってしまってそんな仕事をすることもないのだが、ピタッと左右が合う美しさというか、合理的な形というか、そういうものには感心していた。
この本は会計学というようなものを抜きにして、中世のイタリアで生まれた会計というものがどういう必要性があって生まれ、どうやって発展してきたかを当時の歴史や文化を織り交ぜながら解説している。
歴史としてはこんな流れで会計というものは進化してきた。
会計の歴史のスタートは15世紀のイタリア、フィレンツェ。金融業を営む人々がその記録を付け始めたのが最初だ。そんな人たちのことを“バンコ”と読んだ。今の“BANK”の語源となったそうだ。そして簿記が始まる。これはルネッサンスの立役者でもあったメディチ家が遠方の支店を管理するために生まれた。メディチ家も金融業で財をなしたけれどもその会社運営方法は今でいう持ち株会社のような方法であり、各支店の管理をするための方法であった。
メディチ家の資本は自前で準備されたものだが、少し時代が進むと仲間内で資金を出し合って事業をおこなうようになった。投資とは配当を期待しておこなうものだが、年に1回は決算をして配当をする。そのために簿記が生まれた。1年後に残った資産と生まれた利益をはっきりさせるのだ。一緒に(=com)パン(=pan)を食べる人たちという意味で、“カンパニー”という言葉が生まれた。
さらにオランダではその規模が大きくなってくる。東洋との貿易で大きな利益を生み出すようになってくるのだがその資本を集めるために見ず知らずの他人(ストレンジャー)からも資金を集めた。東インド会社、(VOC)だ。そしてその株主たちに決算の情報を説明するために複式簿記を取り入れた。貸借対照表の登場だ。そんなストレンジャーに決算を報告(アカウント)するから会計のことを“アカウンティング”という。
そして産業革命のイギリスへ舞台は移る。産業革命の一端を担ったのは鉄道であるが、初期投資が大変だ。普通に収支を計算してゆくと最初は投資が回収できないので赤字が続く。それでは最初に投資した人たちに配当が回らないというので減価償却という考えが導入された。
それまでは会社の過去の実態を記録していた会計がアメリカに渡り会社の将来の姿(どれだけ利益を上げられるか。)という管理会計が生まれた。原価計算であったり、損益分岐点の計算というようなものだ。
メディチ家から後はずっと投資家のために会計というものがあったけれども、管理会計が導入されたことでメディチ家の時代=自分たちのための会計に再び戻るということになった。
さらに時代は進み、M&Aと情報がお金を生む時代になり、企業価値というものは何かということが考え直された。最初に書いた、ファイナンスという分野だ。すべてのものに値段をつけ、それがある将来の時点にどれくらいの価値を持つかということを考えて事業や企業に投資をする。
この本は、そういった会計の歴史を当時の文化とリンクさせながらたどっている。”バンコ”の時代、キリスト教の世界では金融業は日陰の職業であった。利息というのは時間の経過の中で生まれるもので、その時間というのは神のものである。その神のものを利用してお金を稼ぐのは悪だと言われた。レオナルドダヴィンチの父親もそういった職業のひとりであった。そしてキリスト教支配の時代、芸術も宗教画が中心であったが、株主というものが力を持ち始めたオランダの時代では肖像画が多くなる。レンブラントという画家が代表的らしいが、その注文者はその投資家たちであった。
産業革命を経て科学技術が発展すると写実的な画風は写真に奪われ印象的な絵が好まれるようになる。ターナーという画家が有名だそうだ。
アメリカ編ではデキシーからジャズ、R&B、ビートルズへの変遷を会計の歴史になぞらえているが、ビートルズやエルビス・プレスリーは将来を予測する管理会計、ファイナンスの発展の中の、将来に価値を生み出すたとえとして登場する。
ビートルズは著作権をメンバーが持っているのではなく、当時のレコード会社が持っていて、著作権料は本人たちに入ってこなかったそうだ。ということで、資本のような扱いになる。マイケル・ジャクソンがその権利を5300万ドルで買ったのはファイナンスの考えのとおり、今の5300万ドルと将来に渡って生み出す著作権料を比較すると、将来の価値の方が上回るという考えからだと書かれている。
しかしながら、僕は研修や教科書を読んでもこれがどうやって実務に生かせるのかということが今一つよくわからなかった。よくわからなかったからオワコンになってしまったのだけれども、なんとか実務に生かしてやろうという熱意もなかった。悲しいかな、それほどの興味を仕事の中に見いだせなかった。興味があれば、もっと、もっとと自分の範疇を超えていろいろなことを理解したいと思い、ネットワークを広げて仕事の幅を広げて認められていくのだろうけれどもそういうこともなかった。なんとか時間内でやらねばならないことをうっちゃり続けるのがやっとだ。わざわざ休みの日にまで出て行って机に座りたいとも思わなかった。わが社も働き方改革が叫ばれているこれども僕はその前後であまり変わったということがない。体力も劣っていた。最近は特にそう思う。トライし続けないと、チャンスは絶対に巡ってこないというのはよくわかるしかし、気持ちというのはフィジカル的に鍛えた体力があってこそ湧き上がるものなのである。
そう思うと、たとえ今と違った職業を選んでいたとしても結果は同じようなものになっていたのだと思う。男は職業を選び間違えると一生不幸になるというけれども、そう意味では結果が同じだと思うと悲しいかな、悔いが残ったということさえおこがましい。
それももう今までの話だ。そんなことを憂いても、人生とは二回やり直さなければならないものではない。だから次はこうすべきだと反省しなければならないこともあるまい。それだけが救いだ。
面白い本であった。
出向しているころに、財務諸表を読めるようにならねばといくつかの本を読んでみたがやっぱりダメだった。さすがにあともな会計の教科書を読まずに、いわゆる、「3分で理解できます!」っぽいタイトルのものばかり読んでいてはそれもいたしかたがない。頭のできもわるいのだからなおさらだ。
会社の研修でも丸二日勉強したけれども、それが去年の夏ごろだったのでもうすでに脳みそが硬化してしまっているのだからやっぱり理解できなかった。
実務でも投資回収の計算なんかをやるのだが、これが売り上げ見通しをまったく嘘っぽく設定するので嫌になっていた。それと、ファイナンスというものはすべてのものを貨幣価値に換算して経営の判断にするというなんの人情味もない考え方にもなんだかしっくりいかない感じがしていた。
こういうことがわからないからオワコンになってしまったのか、それとも会社に対しては面従腹背の姿勢でいたことがバレバレだったからなのか、どちらにしてももう、オワコンになってしまってそんな仕事をすることもないのだが、ピタッと左右が合う美しさというか、合理的な形というか、そういうものには感心していた。
この本は会計学というようなものを抜きにして、中世のイタリアで生まれた会計というものがどういう必要性があって生まれ、どうやって発展してきたかを当時の歴史や文化を織り交ぜながら解説している。
歴史としてはこんな流れで会計というものは進化してきた。
会計の歴史のスタートは15世紀のイタリア、フィレンツェ。金融業を営む人々がその記録を付け始めたのが最初だ。そんな人たちのことを“バンコ”と読んだ。今の“BANK”の語源となったそうだ。そして簿記が始まる。これはルネッサンスの立役者でもあったメディチ家が遠方の支店を管理するために生まれた。メディチ家も金融業で財をなしたけれどもその会社運営方法は今でいう持ち株会社のような方法であり、各支店の管理をするための方法であった。
メディチ家の資本は自前で準備されたものだが、少し時代が進むと仲間内で資金を出し合って事業をおこなうようになった。投資とは配当を期待しておこなうものだが、年に1回は決算をして配当をする。そのために簿記が生まれた。1年後に残った資産と生まれた利益をはっきりさせるのだ。一緒に(=com)パン(=pan)を食べる人たちという意味で、“カンパニー”という言葉が生まれた。
さらにオランダではその規模が大きくなってくる。東洋との貿易で大きな利益を生み出すようになってくるのだがその資本を集めるために見ず知らずの他人(ストレンジャー)からも資金を集めた。東インド会社、(VOC)だ。そしてその株主たちに決算の情報を説明するために複式簿記を取り入れた。貸借対照表の登場だ。そんなストレンジャーに決算を報告(アカウント)するから会計のことを“アカウンティング”という。
そして産業革命のイギリスへ舞台は移る。産業革命の一端を担ったのは鉄道であるが、初期投資が大変だ。普通に収支を計算してゆくと最初は投資が回収できないので赤字が続く。それでは最初に投資した人たちに配当が回らないというので減価償却という考えが導入された。
それまでは会社の過去の実態を記録していた会計がアメリカに渡り会社の将来の姿(どれだけ利益を上げられるか。)という管理会計が生まれた。原価計算であったり、損益分岐点の計算というようなものだ。
メディチ家から後はずっと投資家のために会計というものがあったけれども、管理会計が導入されたことでメディチ家の時代=自分たちのための会計に再び戻るということになった。
さらに時代は進み、M&Aと情報がお金を生む時代になり、企業価値というものは何かということが考え直された。最初に書いた、ファイナンスという分野だ。すべてのものに値段をつけ、それがある将来の時点にどれくらいの価値を持つかということを考えて事業や企業に投資をする。
この本は、そういった会計の歴史を当時の文化とリンクさせながらたどっている。”バンコ”の時代、キリスト教の世界では金融業は日陰の職業であった。利息というのは時間の経過の中で生まれるもので、その時間というのは神のものである。その神のものを利用してお金を稼ぐのは悪だと言われた。レオナルドダヴィンチの父親もそういった職業のひとりであった。そしてキリスト教支配の時代、芸術も宗教画が中心であったが、株主というものが力を持ち始めたオランダの時代では肖像画が多くなる。レンブラントという画家が代表的らしいが、その注文者はその投資家たちであった。
産業革命を経て科学技術が発展すると写実的な画風は写真に奪われ印象的な絵が好まれるようになる。ターナーという画家が有名だそうだ。
アメリカ編ではデキシーからジャズ、R&B、ビートルズへの変遷を会計の歴史になぞらえているが、ビートルズやエルビス・プレスリーは将来を予測する管理会計、ファイナンスの発展の中の、将来に価値を生み出すたとえとして登場する。
ビートルズは著作権をメンバーが持っているのではなく、当時のレコード会社が持っていて、著作権料は本人たちに入ってこなかったそうだ。ということで、資本のような扱いになる。マイケル・ジャクソンがその権利を5300万ドルで買ったのはファイナンスの考えのとおり、今の5300万ドルと将来に渡って生み出す著作権料を比較すると、将来の価値の方が上回るという考えからだと書かれている。
しかしながら、僕は研修や教科書を読んでもこれがどうやって実務に生かせるのかということが今一つよくわからなかった。よくわからなかったからオワコンになってしまったのだけれども、なんとか実務に生かしてやろうという熱意もなかった。悲しいかな、それほどの興味を仕事の中に見いだせなかった。興味があれば、もっと、もっとと自分の範疇を超えていろいろなことを理解したいと思い、ネットワークを広げて仕事の幅を広げて認められていくのだろうけれどもそういうこともなかった。なんとか時間内でやらねばならないことをうっちゃり続けるのがやっとだ。わざわざ休みの日にまで出て行って机に座りたいとも思わなかった。わが社も働き方改革が叫ばれているこれども僕はその前後であまり変わったということがない。体力も劣っていた。最近は特にそう思う。トライし続けないと、チャンスは絶対に巡ってこないというのはよくわかるしかし、気持ちというのはフィジカル的に鍛えた体力があってこそ湧き上がるものなのである。
そう思うと、たとえ今と違った職業を選んでいたとしても結果は同じようなものになっていたのだと思う。男は職業を選び間違えると一生不幸になるというけれども、そう意味では結果が同じだと思うと悲しいかな、悔いが残ったということさえおこがましい。
それももう今までの話だ。そんなことを憂いても、人生とは二回やり直さなければならないものではない。だから次はこうすべきだと反省しなければならないこともあるまい。それだけが救いだ。
面白い本であった。