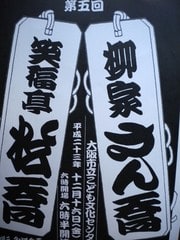ついに、今年も、あと少しで終わり。
今年は、仕事が忙しくて、去年よりも少なめの49公演、191の噺。
後半は、江戸での落語会と上方では笑福亭中心に。
今年は、なかなか時間がとれないので、贅沢ですが、演者と演目の組合せを見てから、落語会ヘ。
本来ふらりと行けるのが落語、私にもそんな時間と心の余裕が欲しい一年でおましたな。
では、今年一年の中から、個人的な好みが大いに入った、BEST30いや35・・・。
鶴二さん、梅團冶さんは贔屓だけに、どの演目もBEST入りするので、
今年も、噺家さん一演目に。
まあ単にごまめの、ひいき目と偏見と、お目溢しを。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011年・・BEST35
01・・・春團冶・・「寄合酒」・・・・・・・・・01・03・・・、今年も凛としてすべてがお洒落。
02・・・鶴二・・・・「らくだ」・・・・・・・・・09・17・・・噺家生活25周年のハレの舞台で堂々たる「らくだ」
03・・・松喬・・・・「ねずみ穴」・・・・・・・12・11・・・嫌な兄貴を薄めることなく緊張の「ねずみ穴」
04・・・さん喬・・「芝浜」・・・・・・・・・・・12・16・・・さん喬さん、夫婦の情愛をさらりと上品に。
05・・・梅團冶・・「ねずみ」・・・・・・・・・05・03・・・梅團治さんそのもの、人間味溢れる「ねずみ」に感動。
06・・・花禄・・・・「片棒」・・・・・・・・・・・07・31・・・神田の神輿、口での笛と太鼓に思わず拍手。
07・・・鶴志・・・・「千早ふる」・・・・・・・02・19・・・鶴志さんの、落語のもつアドリブ感にはまりますな。
08・・・ざこば・・「一文笛」・・・・・・・・・03.14・・・「それが、盗っ人根性というもんや」ざこばさんのこの台詞にジーンと。
09・・・雀松・・・・「星野屋」・・・・・・・・・01・16・・・男と女の化かしあい、死後は年の功の勝ちか。
10・・・米二・・・・「牛ほめ」・・・・・・・・・09・04・・・ベテランさんの前座噺は、なんておもしろいか。
11・・・雀三郎・・「くやみ」・・・・・・・・・10・09・・・ハチャメチャ感、一期一会のライブ感で、最高であます。
12・・・こごろう「高津の富」・・・・・・・01・22・・・「えべっさんのあほ」、楽しい楽しいこごろうさんの「高津の富」
13・・・かい枝・・「堪忍袋」・・・・・・・・・01・16・・・油の乗っているパワプルなかい枝さんの高座。
14・・・仁智・・・・「EBI」・・・・・・・・・05・03・・・仁智さんの新作落語はどれもまた聴きたくなる。「EBI」もしかり。
15・・・松枝・・・・「三枚起請」・・・・・・・05・11・・・「鶴二さんの祝いの会」で弟弟子思いの、印象残る高座。
16・・・三喬・・・・「おごろもち盗人」・05・11・・・押したり引いたり、主人とのかけひき絶妙、やはり泥棒は三喬さんに限りますな。
17・・・雀々・・・・「夢八」・・・・・・・・・・・06・04・・・マクラ無しのj雀々さんかっこいい。いつも通りの汗だくの熱演。
18・・・新治・・・・「柳田格之進」・・・・・01・22・・・上方で聴く機会の少ない人情噺を新治さんが。
19・・・文太・・・・「孝行糖」・・・・・・・・・07・16・・・「孝行糖、孝行糖シ\、テンスケテン、スケテンテン」この馬鹿らしさ、よろしいな。
20・・・遊雀・・・・「井戸の茶碗」・・・・・09・09・・・末広亭のトリ。この一席で満足、いっぱい。
21・・・文三・・・・「堪忍袋」・・・・・・・・・05・03・・・文三さんの「堪忍袋」のお咲さん、口は悪いが品があって、美人っぽい。
22・・・権太楼・・「町内の若い衆」・・・09・24・・・見ているだけで楽しくなる権太楼さんの笑顔。
23・・・鶴瓶・・・・「青木先生」・・・・・・・12・11・・・鶴瓶さんの私落語の代表作・・「ピイ―」
24・・・まん我・・「桑名船」・・・・・・・・・06・25・・・この噺のミステリー感、上手く表現。
25・・・宗助・・・・「蔵丁稚」・・・・・・・・・06・04・・・よく通る声、大音量で響き渡った動楽亭。
26・・・鶴光・・・・「荒茶」・・・・・・・・・・・09・04・・・落語は愉しいものと、小ギャグ満載の鶴光さん。
27・・・よね吉・・「天災」・・・・・・・・・・・01・22・・・八五郎もスッキリしていて正統っぽい、吉朝一門、本来の「天災」
28・・・遊喬・・・・「餅屋問答」・・・・・・・05・15・・・主人公の武骨さとデタラメさが遊喬さんと重なり秀逸。
29・・・塩鯛・・・・「はてなの茶碗」・・・03・19・・・笑福亭とだぶるどっしりとした塩鯛さんの「はてなの茶碗」
30・・・生喬・・・・「虱茶屋」・・・・・・・・・11・19・・・虱を扱っているのに、日本舞踊をしているように優雅に上品な高座、粋。
31・・・文鹿・・・・「お文さん」・・・・・・・07・16・・・骨太でありながら、人間味がにじみ出る文鹿さんらしい噺・
32・・・紅雀・・・・「くしゃみ講釈」・・・10・09・・・明るさ、たのしさが散りばめられた紅雀さんの「くっしゃみ講釈」
33・・・米左・・・・「豊竹屋」・・・・・・・・・09・04・・・聴かせ上手、名調子の米左さんの一席。
34・・・九雀・・・・「御公家女房」・・・・・03・19・・・九雀さんの十八番「公家女房」、随所に工夫があって楽しい。
35・・・春蝶・・・・「こうもり」・・・・・・・09・17・・・春蝶さんらしい独特の気怠さが漂うファンタジー噺。
今年も、一年、ごまめのいちょかみに、おつきあい頂きありがとうございました。
来年は、お正月の一心寺亭からが、笑い初めでおます。
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
今年は、仕事が忙しくて、去年よりも少なめの49公演、191の噺。
後半は、江戸での落語会と上方では笑福亭中心に。
今年は、なかなか時間がとれないので、贅沢ですが、演者と演目の組合せを見てから、落語会ヘ。
本来ふらりと行けるのが落語、私にもそんな時間と心の余裕が欲しい一年でおましたな。
では、今年一年の中から、個人的な好みが大いに入った、BEST30いや35・・・。
鶴二さん、梅團冶さんは贔屓だけに、どの演目もBEST入りするので、
今年も、噺家さん一演目に。
まあ単にごまめの、ひいき目と偏見と、お目溢しを。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011年・・BEST35
01・・・春團冶・・「寄合酒」・・・・・・・・・01・03・・・、今年も凛としてすべてがお洒落。
02・・・鶴二・・・・「らくだ」・・・・・・・・・09・17・・・噺家生活25周年のハレの舞台で堂々たる「らくだ」
03・・・松喬・・・・「ねずみ穴」・・・・・・・12・11・・・嫌な兄貴を薄めることなく緊張の「ねずみ穴」
04・・・さん喬・・「芝浜」・・・・・・・・・・・12・16・・・さん喬さん、夫婦の情愛をさらりと上品に。
05・・・梅團冶・・「ねずみ」・・・・・・・・・05・03・・・梅團治さんそのもの、人間味溢れる「ねずみ」に感動。
06・・・花禄・・・・「片棒」・・・・・・・・・・・07・31・・・神田の神輿、口での笛と太鼓に思わず拍手。
07・・・鶴志・・・・「千早ふる」・・・・・・・02・19・・・鶴志さんの、落語のもつアドリブ感にはまりますな。
08・・・ざこば・・「一文笛」・・・・・・・・・03.14・・・「それが、盗っ人根性というもんや」ざこばさんのこの台詞にジーンと。
09・・・雀松・・・・「星野屋」・・・・・・・・・01・16・・・男と女の化かしあい、死後は年の功の勝ちか。
10・・・米二・・・・「牛ほめ」・・・・・・・・・09・04・・・ベテランさんの前座噺は、なんておもしろいか。
11・・・雀三郎・・「くやみ」・・・・・・・・・10・09・・・ハチャメチャ感、一期一会のライブ感で、最高であます。
12・・・こごろう「高津の富」・・・・・・・01・22・・・「えべっさんのあほ」、楽しい楽しいこごろうさんの「高津の富」
13・・・かい枝・・「堪忍袋」・・・・・・・・・01・16・・・油の乗っているパワプルなかい枝さんの高座。
14・・・仁智・・・・「EBI」・・・・・・・・・05・03・・・仁智さんの新作落語はどれもまた聴きたくなる。「EBI」もしかり。
15・・・松枝・・・・「三枚起請」・・・・・・・05・11・・・「鶴二さんの祝いの会」で弟弟子思いの、印象残る高座。
16・・・三喬・・・・「おごろもち盗人」・05・11・・・押したり引いたり、主人とのかけひき絶妙、やはり泥棒は三喬さんに限りますな。
17・・・雀々・・・・「夢八」・・・・・・・・・・・06・04・・・マクラ無しのj雀々さんかっこいい。いつも通りの汗だくの熱演。
18・・・新治・・・・「柳田格之進」・・・・・01・22・・・上方で聴く機会の少ない人情噺を新治さんが。
19・・・文太・・・・「孝行糖」・・・・・・・・・07・16・・・「孝行糖、孝行糖シ\、テンスケテン、スケテンテン」この馬鹿らしさ、よろしいな。
20・・・遊雀・・・・「井戸の茶碗」・・・・・09・09・・・末広亭のトリ。この一席で満足、いっぱい。
21・・・文三・・・・「堪忍袋」・・・・・・・・・05・03・・・文三さんの「堪忍袋」のお咲さん、口は悪いが品があって、美人っぽい。
22・・・権太楼・・「町内の若い衆」・・・09・24・・・見ているだけで楽しくなる権太楼さんの笑顔。
23・・・鶴瓶・・・・「青木先生」・・・・・・・12・11・・・鶴瓶さんの私落語の代表作・・「ピイ―」
24・・・まん我・・「桑名船」・・・・・・・・・06・25・・・この噺のミステリー感、上手く表現。
25・・・宗助・・・・「蔵丁稚」・・・・・・・・・06・04・・・よく通る声、大音量で響き渡った動楽亭。
26・・・鶴光・・・・「荒茶」・・・・・・・・・・・09・04・・・落語は愉しいものと、小ギャグ満載の鶴光さん。
27・・・よね吉・・「天災」・・・・・・・・・・・01・22・・・八五郎もスッキリしていて正統っぽい、吉朝一門、本来の「天災」
28・・・遊喬・・・・「餅屋問答」・・・・・・・05・15・・・主人公の武骨さとデタラメさが遊喬さんと重なり秀逸。
29・・・塩鯛・・・・「はてなの茶碗」・・・03・19・・・笑福亭とだぶるどっしりとした塩鯛さんの「はてなの茶碗」
30・・・生喬・・・・「虱茶屋」・・・・・・・・・11・19・・・虱を扱っているのに、日本舞踊をしているように優雅に上品な高座、粋。
31・・・文鹿・・・・「お文さん」・・・・・・・07・16・・・骨太でありながら、人間味がにじみ出る文鹿さんらしい噺・
32・・・紅雀・・・・「くしゃみ講釈」・・・10・09・・・明るさ、たのしさが散りばめられた紅雀さんの「くっしゃみ講釈」
33・・・米左・・・・「豊竹屋」・・・・・・・・・09・04・・・聴かせ上手、名調子の米左さんの一席。
34・・・九雀・・・・「御公家女房」・・・・・03・19・・・九雀さんの十八番「公家女房」、随所に工夫があって楽しい。
35・・・春蝶・・・・「こうもり」・・・・・・・09・17・・・春蝶さんらしい独特の気怠さが漂うファンタジー噺。
今年も、一年、ごまめのいちょかみに、おつきあい頂きありがとうございました。
来年は、お正月の一心寺亭からが、笑い初めでおます。
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓