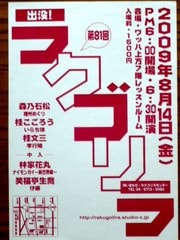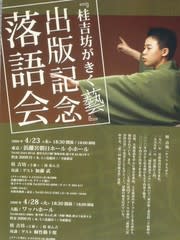第25回・紅雀と阿か枝の会
今日は、昼間は仕事、落語の禁断症状がでそうなので、
夜、ワッハにかけ込む予定。

紅雀さんと阿か枝さん、共に二席なので、普段聴けない大ネタに期待。
中堅の独演会が、二人一緒に聴けるようで、楽しみですな・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
期待どおりの充実の落語会。
「道灌」、「孝行糖」、「尿瓶の花活け」と演目だけで、ワクワクしまっしゃろ。
落語仲間のⅠ氏と、ご一緒に、ゆったりと満席のほぼ30名の入り。
一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・「時うどん」
いつもながらの、ハジケル楽しい喬介さんの高座。
30人の落語ファンが、大喜び。
普通、落語は、その世界に入ると、サゲまで夢を見させるものだが、
喬介さんの落語、新しいスタイルを開発か・・・・。
噺の途中で、ここまで話したという顔で、「あと、もう少し」、と言い、
うどん屋に、「あんたの出番はもうちょっと後や」とか
うどんを食べたあと、「あと、汁すするだけや」・・・・と、
アホの言葉と、演者喬介の独り言が重って、新鮮な笑いが生まれる。
一見、落語の破壊者であり、20年後には、新しい落語の創世者になるかも。
でも、あくまで、時うどんを幾度となく聴いている落語ファンが前提にあって、
パロディ的「時うどん」を楽しんでいるのである。
どこまでが、計算づくか、どこまでが自然体なのか、一度聴いてみたい。
でも、どんな一字一句の言葉でさえ、愛らしい喬介さんの笑顔が許してしまう。
喬介さんの落語、おもしろおまっせ。
二、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「道灌」
団姫さんが、演っているのを聴いた事があるが、落語の基礎の為の演目とか。
リズムとメロディに乗って、流暢に喋れて落語は、心地良さを感じる。
阿か枝さん、「金明竹」といい、この「道灌」、スランプになった時などに、
口慣らし的に利用する、、「東の旅の発端」と同じ様な、原点的演目なのか。
でも、しっとりと演じる「道灌」も、なかなかのもの。
阿か枝さんが、このようなネタを選んだだけで、シブさを感じますな。
三、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「七度狐」
楽しい、明るい、七度狐。
いつも聴く、笑福亭では、尼寺がろうそくだけの暗さを感じるのだが、
紅雀さんの話っぷりは、薄暗い電燈が点いているような、微妙な明るさがある。
どちらかというと、私はモノクロ的、山寺の暗闇の中での、喜六、清八が好きですな。
でも、紅雀さんの、おさよ後家の亡霊、顔の表情、とってもリアルで必見でおますで。
四、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「孝行糖」
これは、兄弟子、九雀さんにつけてもらったネタ。
人前で話す機会の無いままに、師匠の独演会でやれと、
800人の前で・・・シーン・・・。
それ以降も、枝雀師匠、「孝行糖」をやれと、客席はシーンだが、
舞台の袖で、師匠、ガハハの大笑い・・・客より師匠を信じて演っていたが
その、思い出深い「孝行糖」を・・・・・・。
孝行糖売りの、楽しさは、伝わるが。
客が、孝行糖の売り声に、顔がほころぶまでの、一心不乱の無邪気さ。
「孝行糖、孝行糖、孝行糖の本来は、昔々その昔、二十四考のそのうちで・・・・・・・
食べてんか、美味しいで、また売れた、嬉しいな。テン、テレツク、スッテンテン・・・。」
この台詞だけで、楽しくさせるには、この噺、相当難しいんでしょうな。
五、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「尿瓶の花活け」
橘ノ円都師匠で、大昔、聴いたことがあるが、
くすっとした笑いしか無い、いかにも地味なネタ。
尿瓶を買わされた侍が、古道具屋を叩き切ろうとした時、いい訳ごとが、
母親の病気で、高価な人参を購入の為に、つい五両でお売りしましたと・・・。
侍はその孝行に免じて、その場を去るが、ここでも、「孝行」が出てくる。
その当時でも、美談として扱われてるので、稀少価値ではあったようですが、
昔の日本には、儒教の教え、親への「孝行」は、立派に存在していたんですな。
そして、五両の金を、他人の孝行の為に、差し出す武士は、かっこいい。
今の、代議士の先生達にも、爪の垢でも・・・・と思いますな。
「道灌」、「孝行糖」、「尿瓶の花活け」と、珍しい噺を立続けに聴けるなんて。
予想以上の、お二人のセンスに、感激・・・
次回も期待いっぱいでお伺いしなければでおます。
第25回・久々の紅雀と阿か枝
2010年4月11日(日)午後7:00開演
ワッハ上方・4F・上方亭
一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・「時うどん」
二、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「道灌」
三、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「七度狐」
仲入り
四、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「孝行糖」
五、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「尿瓶の花活け」
10-18-81
 にほんブログ村
にほんブログ村
今日は、昼間は仕事、落語の禁断症状がでそうなので、
夜、ワッハにかけ込む予定。

紅雀さんと阿か枝さん、共に二席なので、普段聴けない大ネタに期待。
中堅の独演会が、二人一緒に聴けるようで、楽しみですな・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
期待どおりの充実の落語会。
「道灌」、「孝行糖」、「尿瓶の花活け」と演目だけで、ワクワクしまっしゃろ。
落語仲間のⅠ氏と、ご一緒に、ゆったりと満席のほぼ30名の入り。
一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・「時うどん」
いつもながらの、ハジケル楽しい喬介さんの高座。
30人の落語ファンが、大喜び。
普通、落語は、その世界に入ると、サゲまで夢を見させるものだが、
喬介さんの落語、新しいスタイルを開発か・・・・。
噺の途中で、ここまで話したという顔で、「あと、もう少し」、と言い、
うどん屋に、「あんたの出番はもうちょっと後や」とか
うどんを食べたあと、「あと、汁すするだけや」・・・・と、
アホの言葉と、演者喬介の独り言が重って、新鮮な笑いが生まれる。
一見、落語の破壊者であり、20年後には、新しい落語の創世者になるかも。
でも、あくまで、時うどんを幾度となく聴いている落語ファンが前提にあって、
パロディ的「時うどん」を楽しんでいるのである。
どこまでが、計算づくか、どこまでが自然体なのか、一度聴いてみたい。
でも、どんな一字一句の言葉でさえ、愛らしい喬介さんの笑顔が許してしまう。
喬介さんの落語、おもしろおまっせ。
二、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「道灌」
団姫さんが、演っているのを聴いた事があるが、落語の基礎の為の演目とか。
リズムとメロディに乗って、流暢に喋れて落語は、心地良さを感じる。
阿か枝さん、「金明竹」といい、この「道灌」、スランプになった時などに、
口慣らし的に利用する、、「東の旅の発端」と同じ様な、原点的演目なのか。
でも、しっとりと演じる「道灌」も、なかなかのもの。
阿か枝さんが、このようなネタを選んだだけで、シブさを感じますな。
三、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「七度狐」
楽しい、明るい、七度狐。
いつも聴く、笑福亭では、尼寺がろうそくだけの暗さを感じるのだが、
紅雀さんの話っぷりは、薄暗い電燈が点いているような、微妙な明るさがある。
どちらかというと、私はモノクロ的、山寺の暗闇の中での、喜六、清八が好きですな。
でも、紅雀さんの、おさよ後家の亡霊、顔の表情、とってもリアルで必見でおますで。
四、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「孝行糖」
これは、兄弟子、九雀さんにつけてもらったネタ。
人前で話す機会の無いままに、師匠の独演会でやれと、
800人の前で・・・シーン・・・。
それ以降も、枝雀師匠、「孝行糖」をやれと、客席はシーンだが、
舞台の袖で、師匠、ガハハの大笑い・・・客より師匠を信じて演っていたが
その、思い出深い「孝行糖」を・・・・・・。
孝行糖売りの、楽しさは、伝わるが。
客が、孝行糖の売り声に、顔がほころぶまでの、一心不乱の無邪気さ。
「孝行糖、孝行糖、孝行糖の本来は、昔々その昔、二十四考のそのうちで・・・・・・・
食べてんか、美味しいで、また売れた、嬉しいな。テン、テレツク、スッテンテン・・・。」
この台詞だけで、楽しくさせるには、この噺、相当難しいんでしょうな。
五、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「尿瓶の花活け」
橘ノ円都師匠で、大昔、聴いたことがあるが、
くすっとした笑いしか無い、いかにも地味なネタ。
尿瓶を買わされた侍が、古道具屋を叩き切ろうとした時、いい訳ごとが、
母親の病気で、高価な人参を購入の為に、つい五両でお売りしましたと・・・。
侍はその孝行に免じて、その場を去るが、ここでも、「孝行」が出てくる。
その当時でも、美談として扱われてるので、稀少価値ではあったようですが、
昔の日本には、儒教の教え、親への「孝行」は、立派に存在していたんですな。
そして、五両の金を、他人の孝行の為に、差し出す武士は、かっこいい。
今の、代議士の先生達にも、爪の垢でも・・・・と思いますな。
「道灌」、「孝行糖」、「尿瓶の花活け」と、珍しい噺を立続けに聴けるなんて。
予想以上の、お二人のセンスに、感激・・・
次回も期待いっぱいでお伺いしなければでおます。
第25回・久々の紅雀と阿か枝
2010年4月11日(日)午後7:00開演
ワッハ上方・4F・上方亭
一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・「時うどん」
二、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「道灌」
三、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「七度狐」
仲入り
四、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・「孝行糖」
五、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・「尿瓶の花活け」
10-18-81