2013年10月18日(金)
最近解散した地図愛好者グループのNさんと、谷中(やなか)周辺の街歩きをすること
にした。JR日暮里駅に集合し、10時30分に北口をスタートする。
まずは駅を出て西へ、谷中銀座への通りのすぐ北の、本行寺の山門を入る。

木々の多い境内に、小林一茶の↓「陽炎や道灌どのの物見塚」句碑、種田山頭火の句碑、
太田道灌の物見塚の碑などがある。

西隣は谷中七福神大黒天の教王寺(きょうおうじ)。

明暦元年(1655)の建立で、慶応4年(1868)の上野戦争のとき、敗走した彰
義隊士をかくまったため新政府群の攻撃を受け、山門にはその時の銃弾の痕が残っていた。

十字路を挟んで西側の延命院は、四代将軍徳川家綱の乳母、三沢局(みさわのつぼね)
により慶安元年(1648)の開創。

天保7年(1836)の「江戸名所図会」にも描かれた推定樹齢600年、東京都天然
記念物のシイの古木が立っている。

少し先の「夕やけだんだん」と呼ぶ坂を下ると、谷中銀座商店街。

約170mにわたる狭い通りの両側には惣菜、菓子、パン、肉、菓子など60前後の店
が続いている。
商店街の入口、「茶遊亭」と呼ぶ銘茶と菓子の店頭に積み上げたこれは、玄米シューク
リーム。Nさんがひとつ買おうとしたが、まだ開店準備中だった。

飴(あめ)屋さんの壁面には、近辺の古い社寺などの切り絵が並ぶ。


通りは観光客などで結構賑わっている。ここには著名人も数多く訪れるようで、かりん
とうの店の看板や肉屋さんに並ぶサインに、その人気の一端が知れる。

T字路に出て「よみせ通り」を南へ、千駄木駅近くで東に入ると、突き当たりが岡倉天
心記念公園。

日本美術院を設立した明治時代の美術界の指導者、岡倉天心の旧居跡を公園にしたもの
で、六角堂には天心像が祭られていた。

公園の南側の路地を入り、突き当たりを右折した上り道は蛍坂(ほたるさか)と呼ばれ、
江戸時代はホタルの名所だったとか。いま左手は、墓地のがけを保持する無粋なコンクリ
ート擁壁(ようへき)が続いている。
坂を上がり左折すると、台東区のまちなみ賞に選ばれ江戸時代の面影を残す、観音寺の
長い築地塀(ついじべい)が残っていた。

観音寺は、慶長16年(1611)の創建という。
すぐ先の十字路を右折して南に向かう。そばの長安寺の墓地には、岡倉天心や米人フェ
ノロサなどの日本画復興運動に加わったという明治初期の日本画家、狩野芳崖(かのうほ
うがい)の墓がある。

鎌倉時代の板碑3基と室町時代の板碑1基があることも門前に記されていたが、見つか
らなかった。
通りの両側は寺院が続く。その一角に、江戸時代建造の3階建て土蔵造りの質屋を活用
した「すぺーす小倉屋」と呼ぶギャラリーがある。

入館すると、近年亡くなったこの家のおばあちゃんが、写真やメモ無しで思い出して描
いたという、大正や昭和年代の近辺の風景の絵が展示されていた。

寺町の終わる上野桜木交差点際には、谷中六丁目から移設した旧吉田屋酒店の建物を活
用した下町風俗資料館付設展示場がある。

建物は、明治43年(1910)に新築し、昭和61年(1986)まで使われたもの
とか。開け放たれた内部に、吉田屋酒店で使われた道具やポスターなどが展示されていた。

正午を過ぎたので、この辺で昼食とする。交差点の西側にあるカヤバ珈琲店のランチが
お勧めとのことで、外で少し並んで待つ。

ランチメニューは4種類で、すべて900円。2階の和室に上がり、コーヒー付きのハ
ヤシライスを美味しくいただいた。
来た道を谷中霊園入り口まで戻り、ぎんなん通りの南側の細い通りを西に進む。

突き当たる辺りには、昭和をしのばせる古い木造民家の並ぶ一角が残っていた。


T字路を南下する途中の長久院の本堂前には、脇侍(わきじ)を従えた石像の閻魔(え
んま)像がある。

六十六部聖の光誉円心(こうよえんしん)という人物が、享保11年(1726)に造
立したもの。
都内に現存する六十六部聖造立の石仏は地蔵菩薩像が圧倒的に多く、円魔王像は極めて
まれだという。
次のT字路を西へ、「繪処」という看板の下がる建物があった。

自由に観覧できるというので入ると、芸大で学んだというアメリカ人の日本画屏風絵師、
アラン・ウェスト氏の屏風絵などが並ぶ画廊で、大小たくさんの絵を、5000円から
450万円までの値で販売していた。
すぐ先のY字路際に、みかどパン店という古くからの店があり、二つの道路に挟まれた
狭いところに、谷中のシンボルとして知られる、枝をたくさん伸ばしたヒマラヤスギの古
木が立っている。

パン店の初代店主が植木鉢で育てた木で、台東区の保護樹木に指定されていて、映画や
ドラマ、小説、雑誌などに数多く紹介されたようだが、昨年3月にこの地が売却され、伐
られる可能性があるとのこと。谷中地区の町会などが木を守る活動を続けているようだ。
南西に少し進むと、三浦坂と呼ばれる急坂がある。

坂を下らず北西に向かう辺りは、勝山藩(現在の岡山県)の下屋敷跡。その一角に都心
とは思えぬ緑豊富なお屋敷があり、「大名時計博物館」の古い看板が掛かっていたので観
覧することにした。

この地に住んでいた陶芸家の上口愚朗氏が収集した江戸時代の大名時計をはじめ、外国
製時計、掛時計、櫓時計、印籠時計、香盤時計など初めて見る貴重な時計がたくさん展示
されていた。中には、東京都有形文化財に指定されたものもある(入館料300円、展示
品の撮影は禁止)。

ひとつ西側の通りに回り、やや広いあかじ坂を下って、東京メトロ千代田線が地下を走
る不忍(しのばず)通りを横断して、根津神社へ。
翌日、10月19日(土)と20日(日)には「第15回根津・千駄木下町まつり」が
開催されるようで、境内には露店が多数並ぶが、今日は閉ざされていて営業はしていない。
根津神社は日本武尊(やまとたけるのみこと)の創建と伝えられ、五代将軍徳川綱吉が、
この地で誕生した六代将軍家宣(いえのぶ)の産土神(うぶすながみ)として宝永3年
(1706)に千駄木にあった社を移し、権現造りの社殿を造営したという。

露店の間を進んで朱塗りの山門をくぐり拝殿に参拝し、境内の神楽殿などを眺め、小休
止した。

不忍通りに戻って南東に進み、東京メトロ根津駅南側付近で左に入る。

池之端児童遊園地は、かつて都電池之端七軒町停留場跡。そこに都電7500形の
7506号車が保存展示されていた。

上野公園に向かって東進する。公園の台地西側下に森鴎外旧居跡の説明板があり、現在
は「天然森鴎外温泉」のビルになっていた。

台地下を少し南に回り、大鳥居をくぐって石段を上がり、徳川家康と吉宗、慶喜の三代
将軍を祭る東照宮に参拝する。
藤堂高虎が家康の遺言により、高虎の敷地であるここに寛永4年(1627)に本宮を
造営したが、将軍家光はその建物に満足できず、慶安4年(1651)現在の社殿を造営
替えしたとのこと。

近年、大修理が続いていたがほぼ完成したようで、周囲の壁面付近だけが白幕に覆われ
ていた。そばの五重塔も初重の屋根のみ、覆いが被されている。

境内の一角には、昭和20年(1945)8月に広島に投下された原爆で炎上した伯父
の家の火を故郷に持ち帰り灯し続けたという、福岡県の山本達雄さんの火と、長崎の原爆
瓦からとった火と合わせて点火し続けている「広島・長崎の火」のモニュメントがある。

公園の真ん中を東に抜けて、JR上野公園の公園口に15時34分にゴールした。
Nさんと私が各々用意した幾つかのガイドブックから拾った、この近辺のルートは10
近くあり、今日回ったのはその中のほんの一部。谷中銀座のユニークな店、寺町のたくさ
んの寺や幾つものミニ博物館など、まだ回ってみたいところは数多くある。また機会を作
って歩いてみたい。
(天気 晴後曇、距離 5.4㎞、地図(1/2.5万) 東京首部ほか、歩行地 荒川区、
台東区、文京区、歩数 11,700)
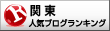 関東地方 ブログランキングへ
関東地方 ブログランキングへ

にほんブログ村
最近解散した地図愛好者グループのNさんと、谷中(やなか)周辺の街歩きをすること
にした。JR日暮里駅に集合し、10時30分に北口をスタートする。
まずは駅を出て西へ、谷中銀座への通りのすぐ北の、本行寺の山門を入る。

木々の多い境内に、小林一茶の↓「陽炎や道灌どのの物見塚」句碑、種田山頭火の句碑、
太田道灌の物見塚の碑などがある。

西隣は谷中七福神大黒天の教王寺(きょうおうじ)。

明暦元年(1655)の建立で、慶応4年(1868)の上野戦争のとき、敗走した彰
義隊士をかくまったため新政府群の攻撃を受け、山門にはその時の銃弾の痕が残っていた。

十字路を挟んで西側の延命院は、四代将軍徳川家綱の乳母、三沢局(みさわのつぼね)
により慶安元年(1648)の開創。

天保7年(1836)の「江戸名所図会」にも描かれた推定樹齢600年、東京都天然
記念物のシイの古木が立っている。

少し先の「夕やけだんだん」と呼ぶ坂を下ると、谷中銀座商店街。

約170mにわたる狭い通りの両側には惣菜、菓子、パン、肉、菓子など60前後の店
が続いている。
商店街の入口、「茶遊亭」と呼ぶ銘茶と菓子の店頭に積み上げたこれは、玄米シューク
リーム。Nさんがひとつ買おうとしたが、まだ開店準備中だった。

飴(あめ)屋さんの壁面には、近辺の古い社寺などの切り絵が並ぶ。


通りは観光客などで結構賑わっている。ここには著名人も数多く訪れるようで、かりん
とうの店の看板や肉屋さんに並ぶサインに、その人気の一端が知れる。

T字路に出て「よみせ通り」を南へ、千駄木駅近くで東に入ると、突き当たりが岡倉天
心記念公園。

日本美術院を設立した明治時代の美術界の指導者、岡倉天心の旧居跡を公園にしたもの
で、六角堂には天心像が祭られていた。

公園の南側の路地を入り、突き当たりを右折した上り道は蛍坂(ほたるさか)と呼ばれ、
江戸時代はホタルの名所だったとか。いま左手は、墓地のがけを保持する無粋なコンクリ
ート擁壁(ようへき)が続いている。
坂を上がり左折すると、台東区のまちなみ賞に選ばれ江戸時代の面影を残す、観音寺の
長い築地塀(ついじべい)が残っていた。

観音寺は、慶長16年(1611)の創建という。
すぐ先の十字路を右折して南に向かう。そばの長安寺の墓地には、岡倉天心や米人フェ
ノロサなどの日本画復興運動に加わったという明治初期の日本画家、狩野芳崖(かのうほ
うがい)の墓がある。

鎌倉時代の板碑3基と室町時代の板碑1基があることも門前に記されていたが、見つか
らなかった。
通りの両側は寺院が続く。その一角に、江戸時代建造の3階建て土蔵造りの質屋を活用
した「すぺーす小倉屋」と呼ぶギャラリーがある。

入館すると、近年亡くなったこの家のおばあちゃんが、写真やメモ無しで思い出して描
いたという、大正や昭和年代の近辺の風景の絵が展示されていた。

寺町の終わる上野桜木交差点際には、谷中六丁目から移設した旧吉田屋酒店の建物を活
用した下町風俗資料館付設展示場がある。

建物は、明治43年(1910)に新築し、昭和61年(1986)まで使われたもの
とか。開け放たれた内部に、吉田屋酒店で使われた道具やポスターなどが展示されていた。

正午を過ぎたので、この辺で昼食とする。交差点の西側にあるカヤバ珈琲店のランチが
お勧めとのことで、外で少し並んで待つ。

ランチメニューは4種類で、すべて900円。2階の和室に上がり、コーヒー付きのハ
ヤシライスを美味しくいただいた。
来た道を谷中霊園入り口まで戻り、ぎんなん通りの南側の細い通りを西に進む。

突き当たる辺りには、昭和をしのばせる古い木造民家の並ぶ一角が残っていた。


T字路を南下する途中の長久院の本堂前には、脇侍(わきじ)を従えた石像の閻魔(え
んま)像がある。

六十六部聖の光誉円心(こうよえんしん)という人物が、享保11年(1726)に造
立したもの。
都内に現存する六十六部聖造立の石仏は地蔵菩薩像が圧倒的に多く、円魔王像は極めて
まれだという。
次のT字路を西へ、「繪処」という看板の下がる建物があった。

自由に観覧できるというので入ると、芸大で学んだというアメリカ人の日本画屏風絵師、
アラン・ウェスト氏の屏風絵などが並ぶ画廊で、大小たくさんの絵を、5000円から
450万円までの値で販売していた。
すぐ先のY字路際に、みかどパン店という古くからの店があり、二つの道路に挟まれた
狭いところに、谷中のシンボルとして知られる、枝をたくさん伸ばしたヒマラヤスギの古
木が立っている。

パン店の初代店主が植木鉢で育てた木で、台東区の保護樹木に指定されていて、映画や
ドラマ、小説、雑誌などに数多く紹介されたようだが、昨年3月にこの地が売却され、伐
られる可能性があるとのこと。谷中地区の町会などが木を守る活動を続けているようだ。
南西に少し進むと、三浦坂と呼ばれる急坂がある。

坂を下らず北西に向かう辺りは、勝山藩(現在の岡山県)の下屋敷跡。その一角に都心
とは思えぬ緑豊富なお屋敷があり、「大名時計博物館」の古い看板が掛かっていたので観
覧することにした。

この地に住んでいた陶芸家の上口愚朗氏が収集した江戸時代の大名時計をはじめ、外国
製時計、掛時計、櫓時計、印籠時計、香盤時計など初めて見る貴重な時計がたくさん展示
されていた。中には、東京都有形文化財に指定されたものもある(入館料300円、展示
品の撮影は禁止)。

ひとつ西側の通りに回り、やや広いあかじ坂を下って、東京メトロ千代田線が地下を走
る不忍(しのばず)通りを横断して、根津神社へ。
翌日、10月19日(土)と20日(日)には「第15回根津・千駄木下町まつり」が
開催されるようで、境内には露店が多数並ぶが、今日は閉ざされていて営業はしていない。
根津神社は日本武尊(やまとたけるのみこと)の創建と伝えられ、五代将軍徳川綱吉が、
この地で誕生した六代将軍家宣(いえのぶ)の産土神(うぶすながみ)として宝永3年
(1706)に千駄木にあった社を移し、権現造りの社殿を造営したという。

露店の間を進んで朱塗りの山門をくぐり拝殿に参拝し、境内の神楽殿などを眺め、小休
止した。

不忍通りに戻って南東に進み、東京メトロ根津駅南側付近で左に入る。

池之端児童遊園地は、かつて都電池之端七軒町停留場跡。そこに都電7500形の
7506号車が保存展示されていた。

上野公園に向かって東進する。公園の台地西側下に森鴎外旧居跡の説明板があり、現在
は「天然森鴎外温泉」のビルになっていた。

台地下を少し南に回り、大鳥居をくぐって石段を上がり、徳川家康と吉宗、慶喜の三代
将軍を祭る東照宮に参拝する。
藤堂高虎が家康の遺言により、高虎の敷地であるここに寛永4年(1627)に本宮を
造営したが、将軍家光はその建物に満足できず、慶安4年(1651)現在の社殿を造営
替えしたとのこと。

近年、大修理が続いていたがほぼ完成したようで、周囲の壁面付近だけが白幕に覆われ
ていた。そばの五重塔も初重の屋根のみ、覆いが被されている。

境内の一角には、昭和20年(1945)8月に広島に投下された原爆で炎上した伯父
の家の火を故郷に持ち帰り灯し続けたという、福岡県の山本達雄さんの火と、長崎の原爆
瓦からとった火と合わせて点火し続けている「広島・長崎の火」のモニュメントがある。

公園の真ん中を東に抜けて、JR上野公園の公園口に15時34分にゴールした。
Nさんと私が各々用意した幾つかのガイドブックから拾った、この近辺のルートは10
近くあり、今日回ったのはその中のほんの一部。谷中銀座のユニークな店、寺町のたくさ
んの寺や幾つものミニ博物館など、まだ回ってみたいところは数多くある。また機会を作
って歩いてみたい。
(天気 晴後曇、距離 5.4㎞、地図(1/2.5万) 東京首部ほか、歩行地 荒川区、
台東区、文京区、歩数 11,700)
にほんブログ村















