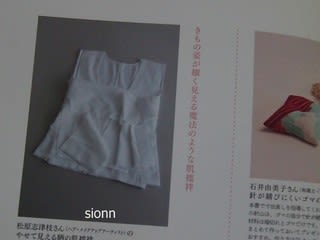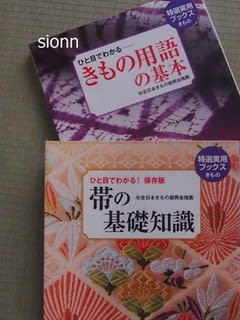先の着付けに関するブログに
参考になるコメントありがとうございます。
すごく勉強になりました。
思うに、
ヘアなどの世界ではプロとアマの世界が明確にあり、
プロがアマにあれこれ言うことはないのに、
こと着付けに関してはいつまでもが
この手の話が尽きませんね。
プロとしての強い誇りと自覚を持っている方々が
日々精進していらっしゃるのは確かで、
こういう方々には尊敬の気持ちを抱いて
おり、また
こういう方々は、教えを乞う方以外には
あれこれ口を挟まないのではないかと
思います。
しかし一方では、誰がなんのために
こういう細かいルールを作ったのか。
本来ならだれでも着られるきものを
窮屈なものにしてしまったのか。
これも調べ考えてみたい。
それを知ることで、
「ああ、これでもいいんだ」と思い、
気楽に気軽に着物着る人
もっと増えてほしいです。
さて、その話題は置いといて~~。
暇暇に、着物を自分サイズにお直ししています。
きれい着付けには
自分のサイズが合っているほうがいいとは、
わかっていたのですが、
なかなか、ね。

ブルーの真綿紬です。
色は気にいっていたのですが、
初期にサイズのこともわからずゲット。
何度か処分しようと思いましたが鳥模様と
色とが気にいってそのままになっていました。
それをお直し。
着てみました。

おはしょり、長すぎますね(汗&笑)
試着でおうちきものです。
帯は木綿更紗です。
こちらも箪笥の肥やしだったのですが、
合わせてみると、結構合うなあ、と
持っているイカットはマルチカバー。
ベッドカバーにしていたものですが、
この度の菊地信子さんの更紗展で、
そうだ、あれを羽織ものにしようと
思い立った次第。
菊地さんの着物の数々を拝見してよかったのは、
それこそ自由な発想!!

洗って干してただいま制作中。
というかひたすら縫うだけだから、
すぐにできるんです。
それまでも自由、というかめちゃくちゃ
とも言われてきた紫苑ですが、
どんなものも、自分が美しいと思った
モノは着物に応用できるのだなと。
もちろんあれほど高価で貴重な布ではありませんが、
分というものがある~~。

前に羽織っていたこちらは
帯に直します。裏の布は外して先の更紗の裏に。
こちらも洗ってスタンバイ。

試しに羽織ってみたもの。
というわけで、またまた楽しみが増えた
紫苑でした。
いつも応援ポチ
ありがとうございます。
励みになっております。