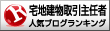宅建の試験には、法律的なセンスのいい者が合格者になって、宅建士として活躍してもらうという作戦があるといいました。
その法律的なセンスについてですが、
もともと身についている人・・・ほとんど少数です。
良い本にめぐりあって身についた人・・・絶対に書きたいです。
良い先生の指導によって身についた人・・・私がする授業では教えます。
様々ですが、どれでもいいのです。
その法律的なセンスがある人とは、
初めて出会った問題(実務なら事件)なのに、妥当な結論が出せること、
そして、その事が妥当だといえるために、相手方に一つ以上の理由をいってあげられることです。
では、それが身に付けるためには、何を学んでいかないといけないか、なのですね。
そのためには、日々、テキストを読むとき、問題を解くとき、それを見直すとき、自分で考えることです。
なぜ、そうなっているか、をです。
一つ問題を・・・
R02・10月試験、問1の肢2
(Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合)
2 Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、
Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。○か×か │
・・・・
この問題ですが、
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます。問題は、自動車による通行をみとめてよいかですね。
そこで考えます。
分析の仕方としては、ちょっと極端なことを考えてみるとよいでしょう。広大な土地のど真ん中にぽつんと囲まれた土地を所有している場合です。
当然この場合でも認められるはずですから、徒歩(例えば、1日かかる)で公道までいけというのはかわいそうでしょう。
そしてこういう紛争が生じるのは、民法のルールがそこまで規定されていないのですが、実は民法ができた時代を思い出すといい場合があります。
この規定は、明治30年代にできた規定なのです。そのころからあるんです。
その頃に自動車はありましたか。
あったとしても、ほとんど庶民は乗れていないのですね。
ですから、時代に応じた処理も必要ということです。
判例は、自動車による通行を前提とする通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきだといっています。
単に○か×か、正解していても、法律的なセンスは身につきません。時間が許す限り、なぜそうなっているか、考えてみてください。
では、また。


 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

その法律的なセンスについてですが、
もともと身についている人・・・ほとんど少数です。
良い本にめぐりあって身についた人・・・絶対に書きたいです。
良い先生の指導によって身についた人・・・私がする授業では教えます。
様々ですが、どれでもいいのです。
その法律的なセンスがある人とは、
初めて出会った問題(実務なら事件)なのに、妥当な結論が出せること、
そして、その事が妥当だといえるために、相手方に一つ以上の理由をいってあげられることです。
では、それが身に付けるためには、何を学んでいかないといけないか、なのですね。
そのためには、日々、テキストを読むとき、問題を解くとき、それを見直すとき、自分で考えることです。
なぜ、そうなっているか、をです。
一つ問題を・・・
R02・10月試験、問1の肢2
(Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合)
2 Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、
Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。○か×か │
・・・・
この問題ですが、
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます。問題は、自動車による通行をみとめてよいかですね。
そこで考えます。
分析の仕方としては、ちょっと極端なことを考えてみるとよいでしょう。広大な土地のど真ん中にぽつんと囲まれた土地を所有している場合です。
当然この場合でも認められるはずですから、徒歩(例えば、1日かかる)で公道までいけというのはかわいそうでしょう。
そしてこういう紛争が生じるのは、民法のルールがそこまで規定されていないのですが、実は民法ができた時代を思い出すといい場合があります。
この規定は、明治30年代にできた規定なのです。そのころからあるんです。
その頃に自動車はありましたか。
あったとしても、ほとんど庶民は乗れていないのですね。
ですから、時代に応じた処理も必要ということです。
判例は、自動車による通行を前提とする通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきだといっています。
単に○か×か、正解していても、法律的なセンスは身につきません。時間が許す限り、なぜそうなっているか、考えてみてください。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |