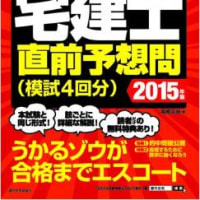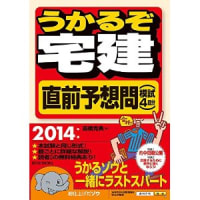難問の一つでした、問2を解説しましょう。
ケース①とケース②という形で、1問で実質2問分の内容をきいているものです。
非常にタイトでもあります。
・・・・・・
問2 令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
1 ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
2 ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
3 ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
4 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
・・・・・
こういう複雑で、内容がふんだんにあるものは、何か真に“がっちり”としたものがあると、ぶれずに自信を持って解けるのですが・・・ね。
そこでそれは、ケース①では、キーワードが「事業資金」ですから、特に事業に関わっていない人が保証人になる場合が大問題なのですね。
公正証書で意思確認をやれとか、情報を事前にあたえよというのも、この流れのポイントでいくといいわけです。
ケース②では、「一切」という根保証がポイントで、債務が膨れ上がる可能性がある点があるのですね。そこで、極度額という歯止めが考えられるわけです。
これらを意識するだけで、ミスが極端に少なくなります。
まず、肢1ですが、ここは落としてはいけません。
民法では、合意で契約が成立するのが原則なのに、唯一民法の契約では書面でしないと成立しないのが、保証契約でした。
保証なら、事業に係る債務についての保証(ケース①)でも根保証契約(ケース②)の場合であっても、同様です。
肢2ですが、これを正解としている人も割と多いですね。
極度額を定める必要があるのは、根○○のときですね。
ケース①は、特定の債務(1、000万円)を主たる債務としますから、保証人が個人であっても法人であっても極度額を定める必要はありません。
あ、個人か法人かも一つ押さえなければいけないポイントですね。
ケース②は、賃借人Aが負う不特定の債務を主たる債務とする根保証契約に当たりますから、保証人が個人である場合は極度額を定めていかないとかわいそうですから、いいのですが、Eが法人の場合には、体力がありますから、極度額を定める必要はないのです。
肢3ですが、これは連帯保証の論点です。ですから、従来の基本論点の一つでしょう。
しかし、これも結構な人が正解(ミス)にしています。
要は、保証契約又は根保証契約のいずれであっても、それが連帯保証契約であるならば、それぞれの保証人は催告の抗弁を主張することができないのですね。補充性がないのです。
肢4ですが、これが正解で正しいです。
本試験では、おそらく消去法でこれを出す問題です。なんとなくやったなと思っても、ここまで(肢4の内容)正確に覚えている人はいませんから・・・ね。
ケース①の保証契約ですが、まず「事業のために負担」しているし「貸金等債務が含まれている」こと、しかも「事業に関与しない場合」である点の3つが認定するうえで重要なキーワードですよ。
そして、「個人である」ときには、「その保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書(公証人役場にいって)で保証債務を履行する意思を表示すること」が必要です。
ケース②の場合は、事業のためではないので(上記3つの一つが欠ける)、保証債務を履行する意思を公正証書で表示する必要はありません。
まだまだ出ていないい論点もあり、今年も出題されることを予定して、出題されたところはしっかり理解しておきましょう。その際には、細かいことよりも、なぜそうなっているのかの土台を押さえる学習をするのですね。
では、また。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

ケース①とケース②という形で、1問で実質2問分の内容をきいているものです。
非常にタイトでもあります。
・・・・・・
問2 令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
1 ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
2 ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
3 ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
4 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
・・・・・
こういう複雑で、内容がふんだんにあるものは、何か真に“がっちり”としたものがあると、ぶれずに自信を持って解けるのですが・・・ね。
そこでそれは、ケース①では、キーワードが「事業資金」ですから、特に事業に関わっていない人が保証人になる場合が大問題なのですね。
公正証書で意思確認をやれとか、情報を事前にあたえよというのも、この流れのポイントでいくといいわけです。
ケース②では、「一切」という根保証がポイントで、債務が膨れ上がる可能性がある点があるのですね。そこで、極度額という歯止めが考えられるわけです。
これらを意識するだけで、ミスが極端に少なくなります。
まず、肢1ですが、ここは落としてはいけません。
民法では、合意で契約が成立するのが原則なのに、唯一民法の契約では書面でしないと成立しないのが、保証契約でした。
保証なら、事業に係る債務についての保証(ケース①)でも根保証契約(ケース②)の場合であっても、同様です。
肢2ですが、これを正解としている人も割と多いですね。
極度額を定める必要があるのは、根○○のときですね。
ケース①は、特定の債務(1、000万円)を主たる債務としますから、保証人が個人であっても法人であっても極度額を定める必要はありません。
あ、個人か法人かも一つ押さえなければいけないポイントですね。
ケース②は、賃借人Aが負う不特定の債務を主たる債務とする根保証契約に当たりますから、保証人が個人である場合は極度額を定めていかないとかわいそうですから、いいのですが、Eが法人の場合には、体力がありますから、極度額を定める必要はないのです。
肢3ですが、これは連帯保証の論点です。ですから、従来の基本論点の一つでしょう。
しかし、これも結構な人が正解(ミス)にしています。
要は、保証契約又は根保証契約のいずれであっても、それが連帯保証契約であるならば、それぞれの保証人は催告の抗弁を主張することができないのですね。補充性がないのです。
肢4ですが、これが正解で正しいです。
本試験では、おそらく消去法でこれを出す問題です。なんとなくやったなと思っても、ここまで(肢4の内容)正確に覚えている人はいませんから・・・ね。
ケース①の保証契約ですが、まず「事業のために負担」しているし「貸金等債務が含まれている」こと、しかも「事業に関与しない場合」である点の3つが認定するうえで重要なキーワードですよ。
そして、「個人である」ときには、「その保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書(公証人役場にいって)で保証債務を履行する意思を表示すること」が必要です。
ケース②の場合は、事業のためではないので(上記3つの一つが欠ける)、保証債務を履行する意思を公正証書で表示する必要はありません。
まだまだ出ていないい論点もあり、今年も出題されることを予定して、出題されたところはしっかり理解しておきましょう。その際には、細かいことよりも、なぜそうなっているのかの土台を押さえる学習をするのですね。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |