〈時に会話形式で〉
先生「では、担保についてまず説明してください。どういうものですか。」
生徒「債権の回収を確実にするための制度です。通常、人的担保と物的担保に分かれます。」
先生「そうですね。今日は、物的担保について質問します。民法の規定ではどういうものがありますか。」
生徒「4つあります。留置権、先取特権、質権、抵当権です。」
先生「そうですね。それぞれの意味はだいたいいえますね。では、その4つをいろいろに分類してください。」
生徒「法定担保物権と約定担保物権にわかれます。」
先生「契約がなくても成立するものと契約がないと成立しないものですね。具体的には。」
生徒「法定は留置権と先取特権、あとの2つは約定です。」
先生「あとの分け方は何かありますか?」
生徒「えーと。思い出せません。」
先生「ちょっと難しいかな。では、占有型と非占有型がありますね。」
生徒「あ、思い出しました。先生が授業で言っていたのを思い出しました。客体である物を債権者に渡すのを、占有型で、留置権と質屋さんの場合つまり質権も引き渡します。あ、渡すことができない物を質権の目的にできないわけですね。」
先生「そうです。条文にもきちんと規定されています。343条ですね。そして、要物契約となっています。344条です。先取特権と抵当権は、債務者のもとに置いて、利用させておきます。特に抵当権は、この視点を押さえておくことが重要ですね。あと、担保責任の所でも出てきますから、お楽しみに。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(質権の目的)
343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
(質権の設定)
344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生徒「判例ですが、抵当権者が占有してないことから、不法行為者からの明け渡しを代位権という方法でみとめたのでした。」
先生「そうですね。今では、判例は抵当権自体に基づいて、妨害排除を認めています。それは、実務ではそれだけ緊急性、必要性がでてきたからでした。銀行救済です。」
先生「今日はこれぐらいにしましょう。」
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
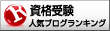
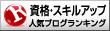
先生「では、担保についてまず説明してください。どういうものですか。」
生徒「債権の回収を確実にするための制度です。通常、人的担保と物的担保に分かれます。」
先生「そうですね。今日は、物的担保について質問します。民法の規定ではどういうものがありますか。」
生徒「4つあります。留置権、先取特権、質権、抵当権です。」
先生「そうですね。それぞれの意味はだいたいいえますね。では、その4つをいろいろに分類してください。」
生徒「法定担保物権と約定担保物権にわかれます。」
先生「契約がなくても成立するものと契約がないと成立しないものですね。具体的には。」
生徒「法定は留置権と先取特権、あとの2つは約定です。」
先生「あとの分け方は何かありますか?」
生徒「えーと。思い出せません。」
先生「ちょっと難しいかな。では、占有型と非占有型がありますね。」
生徒「あ、思い出しました。先生が授業で言っていたのを思い出しました。客体である物を債権者に渡すのを、占有型で、留置権と質屋さんの場合つまり質権も引き渡します。あ、渡すことができない物を質権の目的にできないわけですね。」
先生「そうです。条文にもきちんと規定されています。343条ですね。そして、要物契約となっています。344条です。先取特権と抵当権は、債務者のもとに置いて、利用させておきます。特に抵当権は、この視点を押さえておくことが重要ですね。あと、担保責任の所でも出てきますから、お楽しみに。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(質権の目的)
343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
(質権の設定)
344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生徒「判例ですが、抵当権者が占有してないことから、不法行為者からの明け渡しを代位権という方法でみとめたのでした。」
先生「そうですね。今では、判例は抵当権自体に基づいて、妨害排除を認めています。それは、実務ではそれだけ緊急性、必要性がでてきたからでした。銀行救済です。」
先生「今日はこれぐらいにしましょう。」
では、また。
























