14日(金)その2.よい子は「その1」も見てね。モコタロはそちらに出演しています





昨夕、サントリーホール「ブルーローズ」でクス・クァルテット「ベートーヴェン・サイクルⅤ」を聴きました プログラムはベートーヴェンの①弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131、②同第16番 ヘ長調 作品135です
プログラムはベートーヴェンの①弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131、②同第16番 ヘ長調 作品135です
「ベートーヴェン・サイクル」もこの日が最終回、セット券で購入したC2列8番の席もこれが最後です 通路から一番奥まったど真ん中の席は何かと窮屈です。来年はセット券の指定席の取り方を間違えないようにしたいと思います
通路から一番奥まったど真ん中の席は何かと窮屈です。来年はセット券の指定席の取り方を間違えないようにしたいと思います

1曲目は「弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131」です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1826)が1826年3月頃から7月にかけて作曲、甥のカールを士官に任命したヨーゼフ・フォン・シュトゥッターハイム男爵(当時陸軍の元帥副官の中尉)に献呈されました
この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1826)が1826年3月頃から7月にかけて作曲、甥のカールを士官に任命したヨーゼフ・フォン・シュトゥッターハイム男爵(当時陸軍の元帥副官の中尉)に献呈されました 初演はベートーヴェンの死後の1828年10月でした
初演はベートーヴェンの死後の1828年10月でした 第1楽章「アダージョ・マ・ノン・トロッポ・エ・モルト・エスプレッシーヴォ」、第2楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」、第3楽章「アレグロ・モデラート」、第4楽章「アンダンテ・マ・ノン・トロッポ・エ・モルト・カンタービレ」、第5楽章「プレスト」、第6楽章「アダージョ・クアジ・ウン・ポコ・アンダンテ」、第7楽章「アれグロ」の7楽章から成ります
第1楽章「アダージョ・マ・ノン・トロッポ・エ・モルト・エスプレッシーヴォ」、第2楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」、第3楽章「アレグロ・モデラート」、第4楽章「アンダンテ・マ・ノン・トロッポ・エ・モルト・カンタービレ」、第5楽章「プレスト」、第6楽章「アダージョ・クアジ・ウン・ポコ・アンダンテ」、第7楽章「アれグロ」の7楽章から成ります
ただし、各楽章の長短は極端に異なり、アルバン・ベルク四重奏団のCDによると、第1楽章:6分51秒、第2楽章:3分7秒、第3楽章:52秒、第4楽章:13分23秒、第5楽章:5分36秒、第6楽章:1分33秒、第7楽章:6分26秒となっており、第3楽章と第6楽章が極端に短く、それぞれ次の楽章(第4楽章、第7楽章)への序奏と考える見方もあるようです なおこの作品は全楽章が休みなく続けて演奏されます
なおこの作品は全楽章が休みなく続けて演奏されます
4人が登場し、さっそく第1楽章に入ります 冒頭、第1ヴァイオリンから第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロへと荘重なフーガが演奏されますが、この出だしは良かったと思います
冒頭、第1ヴァイオリンから第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロへと荘重なフーガが演奏されますが、この出だしは良かったと思います この日は4人とも楽器が良く鳴っていました。ただ、第4楽章あたりにくると、若干中だるみのような傾向が見られ、アンサンブルがしっくりこない場面もありました
この日は4人とも楽器が良く鳴っていました。ただ、第4楽章あたりにくると、若干中だるみのような傾向が見られ、アンサンブルがしっくりこない場面もありました この曲は楽章間の切れ目がないので、それだけにうまく流れを作っていくのに神経を使うところがあるかもしれませんね
この曲は楽章間の切れ目がないので、それだけにうまく流れを作っていくのに神経を使うところがあるかもしれませんね

休憩後の1曲目は「弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 作品135」です この曲は1826年10月に完成された最後の弦楽四重奏曲で、ベートーヴェンの死後の1928年3月23日にシュパンツィク四重奏団により初演されました
この曲は1826年10月に完成された最後の弦楽四重奏曲で、ベートーヴェンの死後の1928年3月23日にシュパンツィク四重奏団により初演されました 第1楽章「アレグレット」、第2楽章「ヴィヴァーチェ」、第3楽章「レント・アッサイ、カンタンテ・エ・トランクィッロ」、第4楽章「グラーヴェ、マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります
第1楽章「アレグレット」、第2楽章「ヴィヴァーチェ」、第3楽章「レント・アッサイ、カンタンテ・エ・トランクィッロ」、第4楽章「グラーヴェ、マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります
ベートーヴェンは第12番以降、作曲順に楽章構成を4楽章から、第15番=5楽章、第13番=6楽章、第14番=7楽章と拡大させてきましたが、最後の第16番では”古典的な”4楽章構成に戻しています
この作品でいつも問題になるのは、第4楽章です ベートーヴェンの自筆のパート譜には、4つのパートすべてに「ようやくついた決心」というタイトルと、グラーヴェとアレグロのモティーフの譜例、そしてそれぞれに「そうでなくてはならないか?」と「そうでなくてはならない!」という言葉が書き込まれているのです。これが何を意味しているのか、いくつかの説が提起されてきました
ベートーヴェンの自筆のパート譜には、4つのパートすべてに「ようやくついた決心」というタイトルと、グラーヴェとアレグロのモティーフの譜例、そしてそれぞれに「そうでなくてはならないか?」と「そうでなくてはならない!」という言葉が書き込まれているのです。これが何を意味しているのか、いくつかの説が提起されてきました 前出のアルバン・ベルク四重奏団のCDの解説を音楽評論家の故・門馬直美氏が書いていますが、この楽章については次のように書いています
前出のアルバン・ベルク四重奏団のCDの解説を音楽評論家の故・門馬直美氏が書いていますが、この楽章については次のように書いています
「家政婦との給料の問答だという説もある また、ベートーヴェンは1826年4月にこの『そうでなければならない!』のアレグロの動機を用いて、カノンを作曲しているという事実がある
また、ベートーヴェンは1826年4月にこの『そうでなければならない!』のアレグロの動機を用いて、カノンを作曲しているという事実がある このカノンは、作品130(第13番)の四重奏のパート譜の写しを貸すことに対して、シュパンツィヒに50グルデンを支払うように、音楽愛好者のデンプシャーに要求したことから生まれたものである。デンプシャーは、シュパンツィヒとの予約演奏会を無視して、自宅でこの曲を演奏させようと考え、ベートーヴェンからこの自宅の演奏会のために楽譜を借りられると思ったのである。この50グルデンのことを聞いたデンプシャーは、笑いながら、『そうでなければならないか?』と言った。人からこのことを伝え聞いたベートーヴェンも声高に笑って、テンポの速いカノンを書き、『そうでなければならない。そうだ、そうだ、犠牲を払え』という歌詞を付けた。このやり取りをベートーヴェンは大変気に入っていたようである。この四重奏曲の最初のスケッチとカノンの作曲の時期は大体に同じころと推定されるが、カノンの動機に使う目的であったのが、デンプシャーの『そうでなければならないか?』という発言で霊感がわいて、言葉を付けたカノンが書かれたのだろうという説が行われている
このカノンは、作品130(第13番)の四重奏のパート譜の写しを貸すことに対して、シュパンツィヒに50グルデンを支払うように、音楽愛好者のデンプシャーに要求したことから生まれたものである。デンプシャーは、シュパンツィヒとの予約演奏会を無視して、自宅でこの曲を演奏させようと考え、ベートーヴェンからこの自宅の演奏会のために楽譜を借りられると思ったのである。この50グルデンのことを聞いたデンプシャーは、笑いながら、『そうでなければならないか?』と言った。人からこのことを伝え聞いたベートーヴェンも声高に笑って、テンポの速いカノンを書き、『そうでなければならない。そうだ、そうだ、犠牲を払え』という歌詞を付けた。このやり取りをベートーヴェンは大変気に入っていたようである。この四重奏曲の最初のスケッチとカノンの作曲の時期は大体に同じころと推定されるが、カノンの動機に使う目的であったのが、デンプシャーの『そうでなければならないか?』という発言で霊感がわいて、言葉を付けたカノンが書かれたのだろうという説が行われている 」
」
さて、実際はどうなのか?「ベートーヴェンのみぞ知る」です。この曲を聴いていつも思うのは、「そうでなくてはならないか?」という問いと「そうでなくてはならない!」という答えは、すでに第1楽章の冒頭のメロディーに現われているのではないかということです。そんな風に聴こえませんか
それはともかく、4人のこの曲の演奏は最初から最後まで安定していたように思います。
最後の曲はマントヴァーニ「弦楽四重奏曲第6番”ベートーヴェ二アーナ」の世界初演です この曲は1974年フランス生まれ、2010年にパリ国立高等音楽院長に最年少で就任したブルーノ・マントヴァーニが作曲した作品で、本人の言葉によると「ベートーヴェンの全弦楽四重奏曲に由来する主題素材を11分に凝縮したもの」です
この曲は1974年フランス生まれ、2010年にパリ国立高等音楽院長に最年少で就任したブルーノ・マントヴァーニが作曲した作品で、本人の言葉によると「ベートーヴェンの全弦楽四重奏曲に由来する主題素材を11分に凝縮したもの」です 第2ヴァイオリンのオリヴァー・ヴィレが、サントリーホールでの世界初演に至るまでの経緯を英語で話してから演奏に入りました
第2ヴァイオリンのオリヴァー・ヴィレが、サントリーホールでの世界初演に至るまでの経緯を英語で話してから演奏に入りました
作品を聴く限り、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全17曲の全楽章を切り刻んで、パッチワークのようにつなぎ合わせたような曲想で、ラズモフスキーあり、セリオーソあり、大フーガあり、後期の作品あり、そしてアレグロあり、アダージョあり、プレストありといった「ベートーヴェン弦楽四重奏曲ごった煮コンピレーション」の如しでした
これをもって今年の「ベートーヴェン・サイクル」も終了したわけですが、今回のクス・クァルテットの4人は、日本音楽財団から貸与されたストラディバリウス「パガニーニ・クァルテット」で演奏したわけですが、誰かが突出して優れているということはなく、それぞれの動きを探り合いながら個々の実力を発揮していたように思います
来年の「ベートーヴェン・サイクル」はどこのクァルテットが演奏するのだろうか? 個人的には第1回目に演奏した「パシフィカ・クァルテット」の再登場を希望します

コンサートが終わりホールの外に出たら、杖を突いたカーネル・サンダース人形が出入口の方を向いて立っていたのでビックリしました ケンタッキーおじさんがこんな所にいるわけないよな、と思ってよく見ると、白髪で白い顎鬚を生やしたサスペンダー爺さんでした
ケンタッキーおじさんがこんな所にいるわけないよな、と思ってよく見ると、白髪で白い顎鬚を生やしたサスペンダー爺さんでした 「ブルーローズ」にはいなかったので、「大ホール」で開催の読響定期演奏会に出没していたようです
「ブルーローズ」にはいなかったので、「大ホール」で開催の読響定期演奏会に出没していたようです 今年のチェンバーミュージック・ガーデンでは一度も見かけなかったので、「ブルーローズ」は平和な状態が維持されていましたが、その分「大ホール」の方に不愉快な思いをする人が多数発生していることが予想されます。お気の毒です
今年のチェンバーミュージック・ガーデンでは一度も見かけなかったので、「ブルーローズ」は平和な状態が維持されていましたが、その分「大ホール」の方に不愉快な思いをする人が多数発生していることが予想されます。お気の毒です それにしても、何をしていたんだろう
それにしても、何をしていたんだろう どこのコンサートホールに行っても、白いシャツに吊りズボン(サスペンダー)、大きな荷物をしょって開演ギリギリにやってきて最前列ど真ん中の席に堂々と座る自己顕示欲旺盛なサスペンダー爺さん
どこのコンサートホールに行っても、白いシャツに吊りズボン(サスペンダー)、大きな荷物をしょって開演ギリギリにやってきて最前列ど真ん中の席に堂々と座る自己顕示欲旺盛なサスペンダー爺さん 今や知らない人以外はすべての人が知っている有名人(famousではなくnotoriousの方だけど
今や知らない人以外はすべての人が知っている有名人(famousではなくnotoriousの方だけど )。はっきり言って、コンサート終了後まで”顔見世興行”することはないのに、と思います
)。はっきり言って、コンサート終了後まで”顔見世興行”することはないのに、と思います














 「鶏~」は久しぶりに作りましたが簡単で美味しいです
「鶏~」は久しぶりに作りましたが簡単で美味しいです

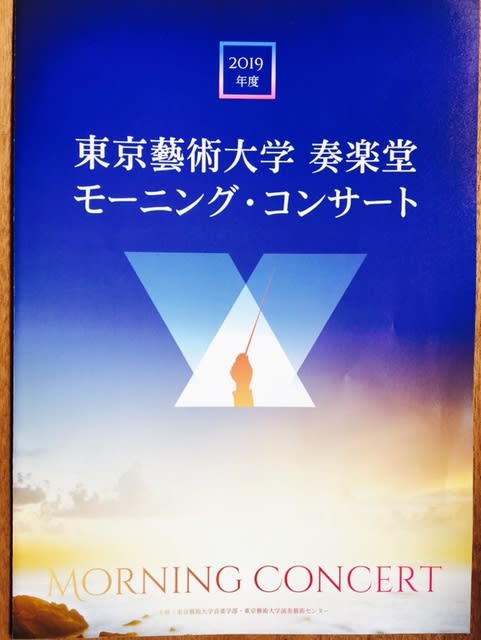

 第3楽章に入ると一転、リズム感に満ちた激しい音楽が展開します
第3楽章に入ると一転、リズム感に満ちた激しい音楽が展開します




