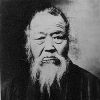ホット・スポッツ・ムーブメント社
インタビュー:リンダ・グラットン氏 —寿命100年時代を生き抜く—【後編】
リンダ・グラットン(ロンドン・ビジネススクール教授
組織に依存せず
働き方を自由にデザイン
アデコ
会社に依存してキャリアをデザインする時代が終わり、個人が自分のキャリアに責任を持つようになると、もはや組織は不要になるのでしょうか。
グラットン
寿命が延びていくにつれ、会社に所属せずに過ごす時間はどんどん増えていきます。
退職後の孤独感も大きな問題になるでしょう。従来のように、人間関係の多くを会社に頼ったままでは生きにくくなると思います。
同時に「会社以外の場所で、いかに自分の価値観に合ったネットワークをデザインしていくか」に目が向くようになるのは、自然な流れだと思います。
ただし、日本人は英語が苦手な人が多いことがネットワークづくりの弱点になりそうですね。
世界にはさまざまな働き方、暮らし方がありますが、日本語圏に限ってしまうとアクセスできるネットワークが限られてしまいます。私も日本語が話せるわけではないので偉そうに言えませんが(笑)。
アデコ
企業に属することで得られていた個人の安心感や安定は、そうしたネットワークで代替できるものでしょうか。
グラットン
企業に属するか否かにかかわらず、人間は、結局集まって何かをするのが好きなのだと思います。
かつては、テクノロジーが進化して在宅勤務が可能になれば、誰もが家で仕事をするようになると考えられていましたが、いざ条件が整ってみても、在宅勤務よりも集まって仲間と一緒に働くことを好む人は少なくありません。
私は、組織のイノベーション創出を支援する「ホットスポッツムーブメント」という会社を経営していますが、社員にいくら「在宅勤務OK」と伝えても、みんなオフィスに出てきたがるのです。
ですから、企業の存在が相対的に小さくなる社会においては、「みんなが集まって仕事に取り組める場」を自らデザインできるかどうかが人生における重要なポイントになるでしょうし、これからの大きな課題になるでしょう。
アデコ
グラットンさんもやはり、集まって仕事をするのが好きですか。
グラットン
私自身は自宅で仕事をするのが好きですね(笑)。特に執筆の仕事は自宅の方がずっと集中できます。
といっても、自宅が唯一の仕事場だと考えているわけではありません。ここロンドン・ビジネススクールにも、ホットスポッツムーブメントにもそれぞれオフィスがあり、タスクに応じて使い分けています。
ホットスポッツムーブメントのオフィスは、テムズ川沿いに立つサマーセットハウスという建物の中にあります。
18世紀に建てられた美しい建物です。個人事業主が100人ほど入居していて、それぞれ独立したオフィスを構えていますが、共用スペースでは大勢の入居者が毎日顔を合わせてお茶を飲み、あれこれと情報交換をします。
私はこの場所をとても気に入っていますが、1人で何かをじっくり考えるのに向いているとは思いません。
多くの人が「マルチプル・アイデンティティ」を持つようになれば、1人で多様な働き方を使い分けて、それぞれの生産性を上げていかなければいけません。
タスク(仕事・課されたつとめ)に適した働き方や働く場をダイナミックにデザインすることが大切なのです。
管理型から創造型へ
マネジメントも進化する
アデコ
グラットンさんの同僚であるゲイリー・ハメル氏(ロンドン・ビジネススクール客員教授)は、管理型マネジメントの終焉を予言しています。
今後、ワーク・シフトが進めばマネジメントはどう変わるでしょうか。企業が個人のワーク・シフトを活用するようになれば、もはや管理は不要になるのでしょうか。
グラットン
管理型マネジメントがなくなるかどうかはさておき、マネジャーの役割が大きく変化することは間違いないでしょう。
中でも「スタッフの管理」という意味のマネジメントは、テクノロジーでどんどん代替できるようになるため、マネジャーはもはや管理者というより、コーチ、メンター、あるいはサポーターとしての役割の方が重要になるでしょう。
ゲイリーが言うところの「マネジメントの終焉」とは、そういう意味だと思います。
むしろ組織のリソースを最大限に活用するというマネジメントが本来あるべき役割を果たすようになるともいえるのではないでしょうか。
アデコ
ジョブトレーニングについてはいかがでしょう。会社が時間をかけて人財を育てても、すぐに企業から離れてしまうのでは育成の意味がなくなります。
キャリアデザインの主体が企業から個人に移った社会で、企業の教育システムはどうあるべきでしょうか。
グラットン
重要な視点ですね。まさしく今、研究中のテーマです。
企業に属さずフリーランスで働くためにも、相応のトレーニングは必要です。しかし、その費用は誰が負担すべきなのでしょうか。
政府? 自分自身? 企業? また、テクノロジーは職業教育においてどんな役割を果たすべきでしょうか。
これらの問いに対する答えを、私自身もまだ持っていません。しかし、多くの企業がこれから考えなくてはならないポイントです。
アデコ
では、人財を評価するシステムについてはどうでしょう。
個人が「連続スペシャリスト」になるために、あるいは企業が自社に必要な連続スペシャリストを見極めるためにどんな基準を作るべきでしょうか。
グラットン
そのヒントは、企業がフリーランスの人財をどのように活用するかを考える中で見えてくると思います。
日本企業のほとんどは、給料を勤務時間に対して支払っています。フルタイム労働を前提として、労働者から時間を買っているのです。
いわば時給システムです。しかし、フリーランスへの報酬は成果(製品やサービス)に対して支払われます。
これは、時給システムとは根本的にマインドセットが異なります。そのための方法論をさまざまな角度から検証しなければならないと思います。
アデコ
社会に出るまでの学校教育も変わらざるを得ないと思います。教育現場にはどんな変化が必要でしょうか。
グラットン
最も大切なのは「情報の透明性」を確保することだと思います。
例えば配車サービスのUberを考えてみてください。かつてタクシーは路上で見つけるものでした。
しかし、Uber(より優れている配車サービス例えば宅配便)の登場で運転手の所在が調べられるようになった。この革新的な変化を生み出したのが、Uberのシステムの基盤となっている情報の透明性です。
職業選択に関しても、情報の透明性が高まれば、もっと選択肢が広がります。
どんな職業があるか、その職業に就くためには何が必要か、それはどれくらい困難か、その職業に就けばどんな結果が得られるか……。
全てが透明化されていれば、利益も不利益も踏まえて幅広い選択肢からふさわしい道を選べるようになるからです。
私の息子は「自分のスキルを有効活用して高い所得を得たいなら弁護士を目指せば良い」と十分に理解していますが、実際には著述家を目指しています。それこそが選択です。
逆に言えば、自分自身のスキルや労働市場を理解することなしに望む道を選択することはできないのです。
労働市場では、ビッグデータが蓄積されたリンクトインが情報基盤として重要な役割を果たしています。
登録されている全ての情報が正しいかどうかは分かりませんが、「誰がどんな仕事を獲得しているか」「どんな仕事が不足しているか」「どんなスキルが求められているか」といった情報を定量的に把握することができます。
アデコのような第三者的かつ客観的な会社は、この分野で重要な役割を果たすことが期待されていると思います。
社会の固定観念を
解きほぐすには
アデコ
日本では少子高齢化が進んでおり、生産年齢人口の減少による競争力の低下が懸念されています。
そして、それを補うために女性の社会参画を推進しています。こうした日本の女性施策について、どうお考えですか。
グラットン
3つの視点から考えてみましょう。
まず「家庭」から見ると、世帯収入の全てを1人の稼ぎ手に頼ることは、もはや大きなリスク要因です。
女性の労働参加は当然の流れといえるでしょう。
「社会の生産性」という面から見ても、男性と同等の生産性を持つ女性を労働市場から排除するのは大きな機会損失です。
ましてや移民の流入が極端に少ない日本においては、女性の労働力は不可欠なのですから。
「世界の中の日本」を考えても、もっと多くの女性の活躍が必要です。ロンドン・ビジネススクールでは日本人女性も学んでいますが、彼女たちは日本社会の性的役割分担意識の強さにうんざりしています。だから、日本に貢献したいと強く考えているにもかかわらず、どんどん海外の企業に流れてしまう。実際に、日本企業には本当に女性が少ないと思います。
日本のクリエーティビティや技術力の高さは世界の多くが認めるところですが、こと男女共同参画に関しては世界に遅れていると言わざるを得ません。その事実に世界も気付き始めています。
アデコ
その通りだと思います。
アデコグループでは、世界118カ国の「人財を獲得、育成、維持する能力」を調査し、ランク付けした「Global Talent Competitiveness Index(GTCI:人財競争力に関する国際調査)」を発表していますが、2017年の調査では日本は22位にとどまっています。
詳しく見ると、人財を惹きつけるための魅力を測る「Attract:魅力」という点が全体の51位となっており、総合順位を下げる大きな要因となっています。その中でも「男女の賃金格差」や「女性に対するビジネスチャンス」について特に評価が低く、大きな課題となっています。
こうした調査からも現在、企業の中枢にいる世代には、まだまだ古い固定観念が根強く、これが大きな壁になっていることがうかがえます。
グラットン
おっしゃるように、社会に浸透した固定観念は大きなハードルでしょう。しかし、現実を動かすのは行動しかありません。他人の考え方や態度を無理に変えようとするより、私たち一人一人が行動を変える方が早いのです。
その第一歩は、あらゆる場面で「そこに女性がいるかどうか」を確認し続けることです。
「候補者に女性がいるか」「雇用対象に女性がいるか」「仕事の現場に女性がいるか」。それを毎日問い続け、いなければ配置するためのプロセスを踏むのです。
クオータ制(社員や役員における女性の割合を一定にして起用する制度のこと)の採用でもいいし、男性の育休取得の推進でもいい。とにかく、現状の意識を変えることにつながるプロセスを実行することが重要です。
ただし、女性の参画がトークニズム(形式的平等)に陥らないように気を付けなければなりません。重要なポストに1人だけ女性を起用して良しとする例はあちこちに見られますが、これはたった1人に全ての女性を代表させることにつながり、意見が偏り、かえって後進の活躍を阻みます。どんな場所でも、最低でも女性の割合が3分の1を上回るように注意すべきです。
女性がどんな仕事のどんなポジションにいるのも当たり前となり、女性と共に働く機会が増えれば、かたくなだった上の世代も、男女の間に大きな違いなどないということに気付きます。
そして組織も少しずつ変わっていく。より良い変化をもたらせるかどうかは、結局のところ、私たち一人一人にかかっているのです。
インタビューの報告を受けて
個人のキャリアデザインをどのように描くかについては、私たち人材サービス業界において、重要なテーマとして認識されており、アデコでもさまざまな取り組みを始めている。
ただ、グラットン氏が今回の取材で語ってくれたことから、これまでの日本のキャリアデザインに関する取り組みは、働く個人の思いや意思をいかに実現するか、ということに視点が向き過ぎていたのではないかと考えさせられる。
どんな社会でも、雇用とは社会にとって必要な仕事(役割)と担う側のマッチングである。
昨年は人材が足りなかった業界が、今年になって仕事がないということも当たり前のように起こるのである。どう働くかを考える上でグラットン氏が言うどんな仕事が必要とされるか「予測する力」が重要であることは言うまでもない。それに加えて重要なことは、自分のキャリアデザインが、社会の変化に照らし合わせて必要とされるものになっているかどうか、常に微調整する習慣を働く人々に浸透させること。これこそが健全な雇用流動性を促す私たち人材サービス業界に課せられた問題だと実感している。
また、キャリアデザインが多様化することで、人財の評価システムにも影響が及ぶことをグラットン氏は指摘しているが、終身雇用というシステムが残る日本は、その重要な機能をいまだ企業が担っていることが今後大きな問題になるかもしれない。
突破口はグラットン氏のいう「情報の透明性」であろう。雇用する側が何を求め、雇用される側が何を提供するかを、公正に、かつ徹底的に見える化できるかどうかが鍵となる。
私たち人財サービス業界の仕事とは、測ることの難しい「人財」という価値をサービスとして提供することだ。私たちが自らの仕事を通して培った知見を、誰もが納得するモノサシづくりに生かすことができれば、キャリアデザインは働き方を超えて、生き方にダイナミズムをもたらすものになるはずである。
アデコ株式会社
代表取締役社長川崎健一郎