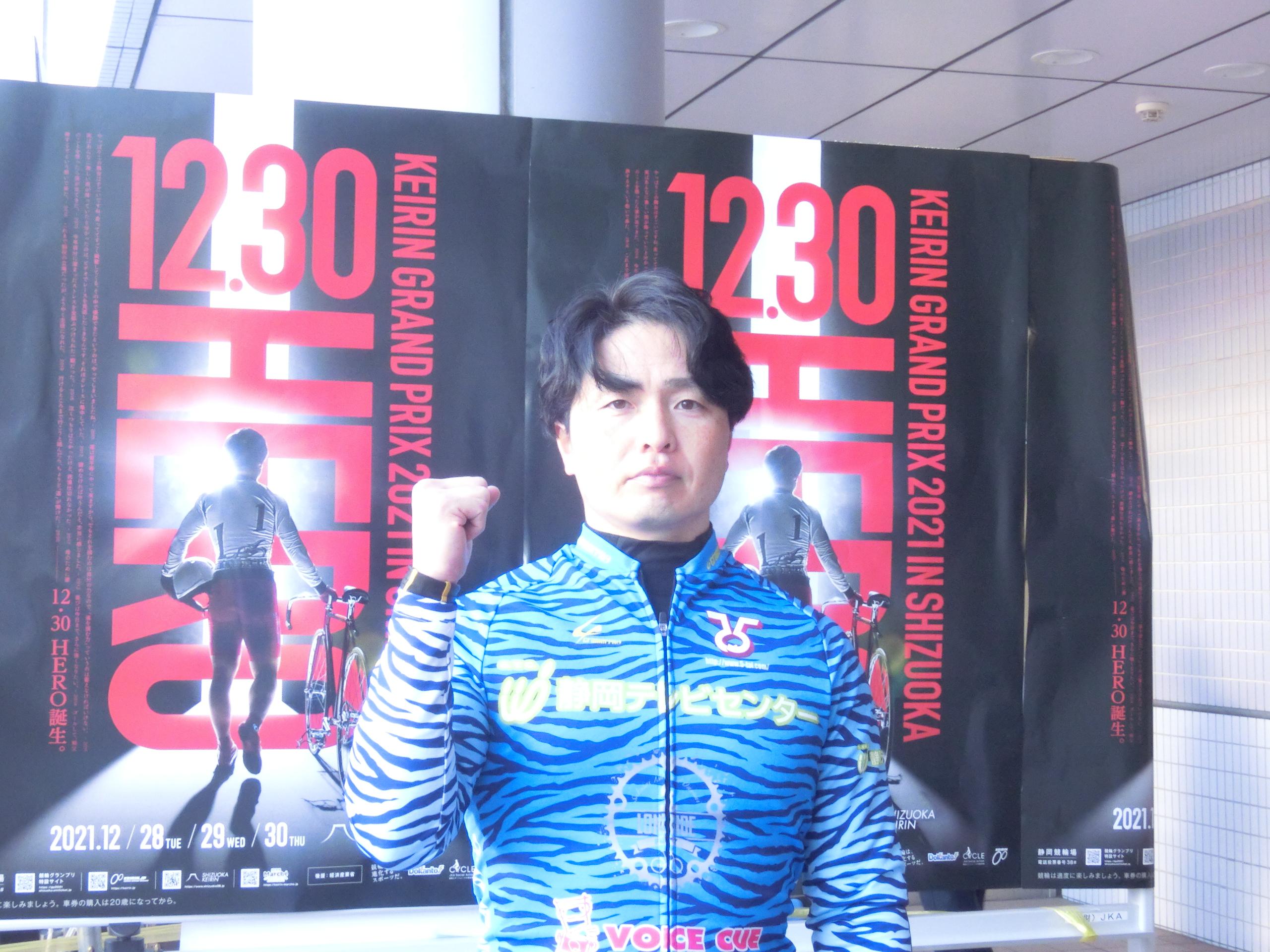GP 静岡競輪 KEIRINグランプリ2021
12月28日
初日8レース
並び 4-8 1-9-6 2ー5 7-3
レース評
松井を目標に岡村が番手差し!武井が3番手を固めて本線強烈。松岡のカマシ捲りも差は僅か。混戦なら三好の自在戦が浮上
1番人気 9-1(2.7倍)
2番人気(1-9 (2.9倍)
最周回 1-9-6ではなく、6番が追走できず、1-9ラインに4番のラインがはまり、1-9-4-2の並びとなってしまったのが、大きな誤算であった。
よくある競輪の<展開のアヤ>。
いわゆる3番手捲りで、4番が2着となる。
3連単 9-1-4(28.8倍)を取り損ねた。
2車単の1-4 を買っていたのに9-4を買っていなかった。
1番の松井 宏佑選は先行ではなく、捲りと考えて車券を買う。
そこで1-9からの3連単車券を重視して、9-1からの3連単車券は押さえにした。
以下の2車単車券を押さえに買う。
1-2(23.8倍)
1-7(31.2倍)
1-4(45.7倍)
いずれにしても、9-2 9-7を買って、9-4を買っていなかっことが悔やまれたのだ。
結果
9-4 6,010円(15番人気)
9-4-1 1万3,760円(22番人気)
| 予 想 |
着 順 |
車 番 |
選手名 | 着差 | 上り | 決ま り手 |
S / B |
勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | 岡村 潤 | 11.8 | 差 | 4角ハコ差 | ||
| 2 | 4 | 月森 亮輔 | 1/2車身 | 11.7 | ク | 飛付3番手 | ||
| ○ | 3 | 1 | 松井 宏佑 | 1/4車輪 | 11.9 | B | 若干末甘く | |
| ▲ | 4 | 3 | 西岡 正一 | 3/4車身 | 11.5 | 松岡叩かれ | ||
| × | 5 | 7 | 松岡 篤哉 | 1/8車輪 | 11.6 | 叩かれ口空 | ||
| △ | 6 | 2 | 三好 恵一郎 | 3/4車身 | 11.5 | 捲も前遠く | ||
| 7 | 5 | 岡田 征陽 | 1車輪 | 11.4 | 目標捲れず | |||
| 注 | 8 | 6 | 武井 大介 | 2車身 | 11.5 | カマシに離 | ||
| 9 | 8 | 石丸 寛之 | 1車身1/2 | 11.8 | 踏み遅れて |
戦い終わって
打鐘では後方に置かれた松井宏佑が一気の巻き返し。ホームで出切って番手の岡村潤が差し切り勝ち。「1番後ろから展開的にきつい踏み出しに。内に月森亮輔君がいて松井君も少し休んでと、難しい中で付け切れた。もうちょっと自分に余裕があれば松井君を2着に残せた。早めに踏んで申し訳ない。他のラインは自分達を後方に置こうとしてくる。その中で松井君は力でねじ伏せる気持ちだったと。それにどこまで付いて行けるかだった。走る前は不安しかなかったけど、少しはなくなったかな。思ったよりも脚は悪くないかと。3年前の静岡GPシリーズ優勝は自分でもびっくりだった。今年最後を良い形で締めれるように」。
松井と併せて仕掛けた月森が結果的に3番手に入り2着。「松井君が前受けだと思っていたから。松井君よりは先に仕掛けて、スピードが合ったらそこで粘るレースを考えていた。自分が1番びっくりしている。脚をためれたから、1着か2着とハンドルを思い切り投げた。前回が終わってから休みなく練習して、前回よりも全然良い感じ。久々に嬉しい結果で気持ちも大分乗る。自転車をいじったりもしたが、それも良い方向に出た」。