趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…
JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。
古紙蒐集雑記帖
池袋駅発行 西武新宿ゆき連絡片道乗車券
1967(昭和42)年12月に山手線池袋駅で発行された、高田馬場接続、西武鉄道新宿線の西武新宿ゆき連絡片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。
池袋からは山手線で高田馬場まで行き、同駅で西武新宿線に乗り換えて西武新宿までの連絡乗車券になります。
西武新宿駅は高田馬場駅の一つ先である新大久保駅からほど近く、新大久保駅の改札口を出てから西武新宿駅の一番近い改札口までは約0.5km、歩いても7~8分ほどの距離にありますが、その先、都内屈指の繁華街である歌舞伎町や新宿3丁目界隈へ行く旅客の需要があったのでしょうか、乗換時間を考慮すると乗換なしのルートと所要時間が殆ど変わらないのに、運賃は2倍近くになる区間の常備券が設備されていたほど、その需要があったことが窺われます。
新杉田駅発行 湯沢ゆき片道乗車券
1981(昭和56)年1月に根岸線新杉田駅で発行された、横浜市内・川崎・鶴見線内から湯沢ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のD型準常備式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。
準常備式券は常備券を設備するほど需要が無いものの、ボチボチの需要はあるため、いちいち窓口で運賃計算をして補充券を作成するのは面倒な区間について、1枚の券に纏めてしまったものです。
御紹介の券は東海道本線と東北本線を経由し、奥羽本線の関根・糠ノ目(現・高畠)・上ノ山(現・かみのやま温泉)・楯岡(現・村山)・新庄・真室川・湯沢の各駅および同じ運賃帯の駅までの片道乗車券を1枚の券に纏めてしまっています。発売する際には、着駅の下で切り取って発売します。
この券の着駅である湯沢駅の下に「------」という点線が見えますので、この券の最遠駅は湯沢駅であると推測され、旅客の手に渡る部分はすべて網羅されているものと思われます。
区間内にあります米沢・赤湯・山形・天童などの主要駅についてはこの券に記載がありませんが、恐らくそれなりの需要があると思われますので、常備券が設備されていたのでしょう。

裏面です。
発駅である新杉田駅は横浜市内の駅になりますので、「横浜市内・川崎・鶴見線内途中下車禁止」の文言があります。
武蔵野鉄道 武蔵大和から狭山公園前ゆき 片道乗車券 ~その2
前回に引き続き、武蔵野鉄道の武蔵大和から狭山公園前ゆき片道乗車券の話題です。
再掲いたしますが、武蔵野鉄道の武蔵大和駅で発行された狭山公園前ゆきの片道乗車券になります。

券面を見る限りでは地紋はなく、白色無地紋のようです。

裏面です。裏面には券番の他、「武蔵野鐵道」という社名が印刷されています。
表面と裏面を比較してみますと、何となく裏面の方が黄ばんでいるような色に見えます。なぜ、裏面が黄色っぽいのか不思議でしたが、よく見るとわかりました。

裏面をよく見てみますと、黄色いPJRてつだう地紋が印刷されていました。
同社の一般的な乗車券の地紋はPJRてつだう地紋ではありましたが、桃色地紋となっており、黄色地紋ではありません。理由は定かではありませんが、戦時色が濃くなってきている時代でしたので、すでに黄色地紋が印刷されている券紙を流用した可能性があります。
実際のところは不明です。
ところで、本券は発駅が本小平駅から武蔵大和駅に変更されています。着駅である狭山公園前駅は若干今の西武遊園地側に移動して現在の多摩湖駅になっているわけですが、現在の多摩湖駅から武蔵大和駅までは営業キロ1.1kmで運賃150円のところ、小平駅までは営業キロ5.7kmもあり、運賃も180円になります。どう考えても当時は同じ運賃帯であるとは思いにくく、どのような経緯でこの券が金額の訂正なく流用されたのか、そして、何の問題も起きなかったのか、この点についても謎の多い券です。
武蔵野鉄道 武蔵大和から狭山公園前ゆき 片道乗車券 ~その1
日付が薄くて読みづらいですが、1942(昭和17)年10月に武蔵野鉄道(現・西武鉄道)武蔵大和駅で発行された、狭山公園前(現・多摩湖)駅ゆきの片道乗車券です。

白色無地紋のB型矢印式大人・小児用券になっています。
この券は本来、本小平(もとこだいら。現・小平駅に吸収合併)駅発の乗車券として作成されていたようですが、欠札となってしまったのでしょうか、武蔵大和駅発の乗車券に転用されています。
元々の発駅であった本小平駅は、現在の多摩湖線の前身である多摩湖鉄道が開業させた駅です。多摩湖鉄道はその母体となる西武グループの中核企業であった箱根土地(現・コクド)が、自社で造成した小平学園都市の販売促進と完成目前の村山貯水池の行楽客輸送を目的とした鉄道でした。
このとき、鉄道省の調整によって(旧)西武鉄道村山線(現・西武鉄道新宿線)の予定線と萩山駅で接続する予定でしたが、(旧)西武鉄道は開業前に北の方に路線を変更してしまい、接続が取れなくなってしまいます。そこで多摩湖鉄道は村山貯水池方面への距離が短くなることを考慮し、1928(昭和3)年に当初より南側の位置に萩山駅を変更し、国分寺~萩山間を開業させています。
しかし、(旧)西武鉄道との接続を考えると、萩山駅と(旧)西武鉄道小平駅間に支線(小平連絡線)を延長敷設せざるを得ず、萩山開業に前後して申請を提出し、同年11月に開業しています。この時、萩山には国分寺から小平方へカーブして行く線と、貯水池方へ行く予定線でY字型の線ができ、後のデルタ線の原型ができています。
多摩湖鉄道の小平駅延長開業は(旧)西武鉄道と連絡する前提でしたが、「両社の協議が整わず直ちに連絡しがたく、旅客の利便を計るためとりあえず(離れたところに)設計した」とあり、(旧)西武鉄道は少々離れた場所に小平駅を開業させています。多摩湖鉄道側の小平駅が当初からあったことから「本小平」と呼ばれていたようです。
これは駅が離れていることから各々を区別するためであることは明確ですが、11月の開業当時は双方とも小平駅でした。しかし、同社の起点である国分寺駅が仮駅で開業していますが、1929(昭和4)年4月の国分寺本駅開業に合わせて本小平駅と改称されています。このことから「小平」→「本小平」となったことが判ります。
その後、同社は武蔵野鉄道(現・西武鉄道)に吸収合併され、さらに1949(昭和24)年に(旧)西武鉄道と合併した現在の西武鉄道となり、村山線と接続して一つの駅となった時に再び小平駅になっています。
一方、着駅である狭山公園前駅は、多摩湖鉄道が1936(昭和11)年に開業した村山貯水池駅(初代)という駅でした。1940(昭和15)年に同社は、武蔵野鉄道(現・西武鉄道)に吸収合併されて同社の駅になりますが、1941(昭和16)年の戦時下に、軍事的に重要な貯水池の存在を隠すために狭山公園前駅に改称されます。同時にライバルだった(旧)西武鉄道村山線の村山貯水池前駅は狭山公園駅(廃駅)に、同じ武蔵野鉄道狭山線村山貯水池際駅は村山駅(現・西武球場前駅)に改称されています。
日立駅発行 亀有までの準常備往復乗車券
1972(昭和47)年に国鉄東京印刷場が発行した見本券を御紹介いたしましたが、もうひとつ御紹介いたしましょう。

常磐線日立駅で発行された、石岡・取手・柏・松戸・亀有の各駅までの往復乗車券です。青色こくてつ地紋のC型準常備大人専用券となっています。
現在では硬券の記念乗車券などでしか見かける機会のないC型準常備往復券で、発売する着駅の下で切断して発売します。
右側の通常地紋の券が往路用で、着駅は最下段になります。逆に、左側の反転地紋の券が復路用となり、発駅が最下段になります。
発売運賃は復路用の発駅の右側に記載されており、往路用に記載されている560~1100までの数字は、裁断された報告片の発売額が分かるように記載された数字です。例えば、柏までの940円で発売された場合、着駅である柏と次の松戸の間で鋏を入れて切断し、切断された下の部分が売上報告用の報告片(証憑)となります。報告片の右端には松戸の右横に発売額である940が記載されており、これで940円で発売されたという売上内容を報告します。

裏面です。
上部には往路用乗車券と復路用乗車券の各々に券番が印字されておりますが、下部は報告片となっており、点線から2つに切断することが無いことから、券番は往路用乗車券側の片方にしかありません。
館山駅発行 南房総定期観光乗車券
見本券になりますが、内房線館山駅で発行された、国鉄バスの南房総定期観光乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型矢印式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。
見本券なので実際に発売されていたものかどうかは定かではありませんが、1972(昭和47)年に国鉄東京印刷場が発行した硬券見本帳に収納されておりましたので、その頃のものと思われます。
乗車経路は、内房線館山駅から外房線安房小湊駅を経由して小湊山誕生寺へ至る経路のもののようです。
「定期観光乗車券」といっても、券面を見る限りでは最終的に発地に戻る形ではなく、単なる片道乗車券に見えます。定員制乗車の関係と思われますが、乗車月日を指定する欄があることから、立席が可能な路線バスではなく、観光バス用車両を使用した路線であったと思われます。
現在では安房小湊駅にはJRバスの発着は無いようですし、同駅から誕生寺までは徒歩20分くらいの距離のようですが、鴨川市が運営するコミュニティバスが運行されているようです。

裏面です。券番の他には発行駅名のみが記載されており、ご案内文の類いの印刷はありません。
会津若松駅発行 喜多方・若宮ゆき片道乗車券
1966(昭和41)年8月に、磐越西線の会津若松駅で発行された、喜多方・新鶴・若宮ゆきの片道乗車券です。
実家の荷物がゴチャゴチャなところを片付けていたら、ひょっこり出てきました。保存状態はすこぶる悪いです・・・。

青色こくてつ地紋のB型地図式大人・小児用券で、仙台印刷場で調製されたものです。
仙台印刷場で調製された地図式券は手書き感満載の様式で、味のある地図が描かれているのものが多く、多くのきっぷコレクターから支持されています。
地図に書かれている有効区間は、磐越西線の喜多方駅と只見線の新鶴・若宮駅となっており、実際の路線通り、会津若松駅からそれぞれ分岐して記載されています。
発駅の会津若松駅は磐越西線の途中駅で、同駅でスイッチバックするように伸びていますが、せっかくの地図式の利点として同じ運賃帯の区間を1枚の乗車券口座にまとめることが可能なはずですが、喜多方と反対方向の猪苗代方面については記載されていません。なぜかと思って時刻表で調べてみますと、この運賃帯での猪苗代方面の着駅に該当駅が無いため、記載されていないようです。

裏面です。発行駅名や必要な文言等が裏面に記載されています。
静岡鉄道 新清水駅発行 普通入場券
1986(昭和61)年10月に、静岡鉄道新清水駅で発行された、硬券の普通入場券です。

白色無地紋横赤一条のB型大人専用券で、シンコー印刷で調製されたものです。
当時、新静岡駅では窓口でお願いすれば乗車券も窓口で発売して戴けましたが、前回エントリーで御紹介いたしましたように乗車券は半硬券しかありませんでした。しかし、普通入場券については硬券で設備されており、半硬券では使用されていないダッチングマシンまで使用されていました。

裏面です。発行駅名の他、「(静岡鉄道)」という社名も印刷されていました。
同社の硬券入場券はこの様式で発行されておりましたが、1980(昭和55)年頃の80円券あたりから風変わりな様式となり、横一条の線が太い緑色で、その中に白抜き文字で駅名が表記された様式に変更され、90円券の時代になると緑色部分が赤色に変更された様式になりました。そして、100円券の時代になると横一条の線が無くなったものの、水色の斜め線が2本印刷されるなど、かなり斬新な様式の券が出てきています。
しかし、110円券からは従来の様式とは細部が異なりますが、横赤線一条の様式に戻っています。いろいろと試してみたものの、結局はオーソドックスなものが良いということになったのかもしれません。
その後、同社では硬券の入場券は設備廃止されてしまいましたが、2003(平成15)年頃から全く異なる様式で復活し、新清水駅の他、新静岡駅でも発売されているようです。
静岡鉄道 新清水駅発行 新静岡ゆき片道乗車券
数回にわたって1986(昭和61)年に発行された静岡鉄道乗車券を御紹介して参りましたが、それから2年後の1988(昭和63)年に乗車した際にもまだ半硬券が残されていました。

1988(昭和63)年1月に新清水駅で発行された、新静岡ゆきの片道乗車券です。若草色静岡鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用千切り式券で、シンコー印刷で調製されたものと思われます。
当時の運賃は新清水~新静岡間の全線を乗り通して280円であり、1986(昭和61)年当時と変わらないことから、当時からの残券であった可能性があります。
静岡鉄道 新静岡駅発行 入江岡・新清水ゆき片道乗車券
前回および前々回エントリーで静岡鉄道の硬券および半硬券の乗車券を御紹介いたしました。今回は当時の券売機券を御紹介いたしましょう。

1986(昭和61)年10月に静岡鉄道新静岡駅で発行された、入江岡・新清水ゆきの片道乗車券です。若草色静岡鉄道自社地紋のA型矢印式券売機券で、スミインク式券時代のものになります。
この券は前回および前々回エントリーで御紹介いたしました硬券および半硬券と同じ日に購入して使用したものですが、新静岡駅には硬券や半硬券の設備はなく、券売機券のみとなっていました。
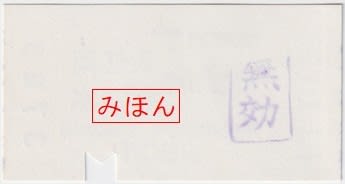
裏面です。新清水駅で記念に持ち帰りたい旨を申し出た際の無効印が捺印されていますが、当時はまだ自動改札機などは無かった時代で、裏面は真っ白で、磁気券にはなっていませんでした。
| « 前ページ |




