昨日に続いて、「ご当地あるある」ネタ。
昨日紹介した本でも、当然のことながら取り上げられている話です。

このような施設、内地の皆さんは何と呼ぶでしょう?
「ゴミ捨て場」「ゴミ置き場」「ゴミ集積場」・・・、まあそんなところでしょうね。
ですが、我々北海道民はと言いますと・・・。

「聞いて驚け!」の世界かもしれませんが、ご覧の通り「ゴミステーション」と呼ぶのです。
箱状の物が置かれているだけでなく、歩道上に家庭ゴミを集積させておく場所なども、同様に「ゴミステーション」と言います。
「ステーション」って、「ゴミの駅」?
色々疑問はあるかと思いますが、由来としては、特にこれというものはないようで、ある場所(どこかは不明)で、看板にそのように書かれていたのが自然に浸透していったとのことのようです。
内地の方がどう思われるかはわかりませんが、感覚的に、ゴミ収集車が通りかかって、ゴミ袋を回収する光景を考えると、「ゴミの置かれている場所=駅・拠点」ということで、「ステーション」となるのも、理解できます。
それに、「ゴミ置き場」と「ゴミ集積場」はともかく、「ゴミ捨て場」と言っちゃうのは、何となくだけど、不法投棄を連想しちゃいそうな気もしますしね。
因みに、これは以前にも取り上げたような気がしますが、家庭ゴミを持ってきて、この「ゴミステーション」に置くことは、「ゴミを投げる」と言います。そう、「捨てる」ではなく「投げる」なのです。
勿論、家庭や公共の場、オフィスなどで、ゴミ箱にゴミを入れることも、「ゴミを投げる」と言います。
内地の皆さんは、北海道に来られた際、道民の友人知人から、「このゴミ投げてきて」と頼まれても、本当にその場に放り投げたりしないようご注意ください。それは、不法投棄になっちゃいますので。
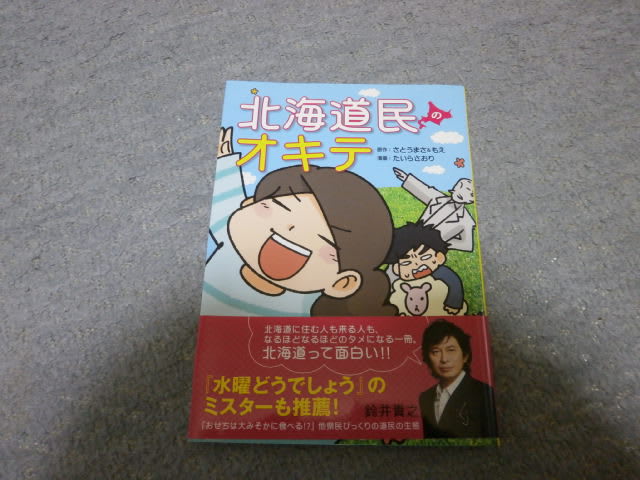
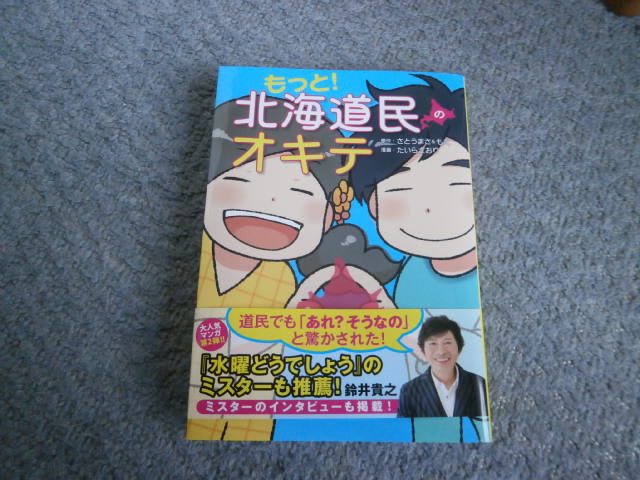
このお題の答えは、もう、この二冊に集約されていると言っても過言じゃないです。
上が昨年発売されたもので、最近、下の、続編というか上級編(?)が発売されました。
同じような趣向の本は他にもあるのだけど、この本は、福島県出身の男性が、北海道の女性と結婚したことで、その生活を通して、北海道の文化、日常を広く発信したいと思ったことがきっかけになっていて、全編が漫画になっていて大変読みやすく、※内地の方が読んでも、「へぇ~そうなんだ」と楽しめる内容になっていると思います。
なんたって、道民の私が読んでも、「そうだよね~」「わかるわかる~」を通り越して、わかり過ぎて大爆笑の内容ばかりですから。
(今日は我が家は私一人なので、それをいいことに声を出して笑っちゃいました・・・)
因みに、愛知県版や沖縄県版もあるそうです。
※ 私は普段は使わないけど、北海道の人、特に年配の方は、本州のことを「内地(ないち)」と言います。由来は諸説あるようですが、北海道の開拓時代の通達で、北海道を「北地(ほくち)」と呼び、北海道以外の地域を「内地」と呼ぶこととしたとされるものがあるそうです。つまり、本州だけでなく、四国も九州も「内地」なのですが、沖縄もまた、北海道と同様に、本州、四国、九州を「内地」と呼んでいるそうです。
雪虫、白老で大量に飛び回る 下校時の生徒ら悲鳴(苫小牧民報)
「ご当地あるある」なニュースをたまたま見つけたので、ご紹介。
でも、これはちょっと極端な例だと思う。
函館でも数日前から雪虫が飛び交っているけれど、ここまで大量のには遭遇した記憶がないです。
たまたま今日友人と話したこと。
90年に、「たま」というバンドが、「さよなら人類」をいう曲を大ヒットさせ、折からのバンドブームの中、一躍人気バンドの仲間入りをした。
調べてみると、03年10月をもって、バンドとしては解散したとのことだけど、友人と色々と話している中で、「今の若い人たちは知らないのだろうなあ・・・」という話になった。
どうなんでしょうね?解散したのが十二年も前だと、やっぱり若い人たちは知らなくても不思議はないのかな?
同じ時代の話で言うと、これは友人との話題には上らなかったのだけど、同じ90年に、リゲインのCMソングで、※時任三郎さんに瓜二つ(?)の「牛若丸三郎太」なるシンガーが歌ってメガヒットを飛ばした「勇気のしるし~リゲインのテーマ~」という曲も、前に何かの時に、「今の若い人は知っているのかな・・・」って思ったことがあるのだが、早いもので二十五年も前の曲になってしまったので、10代の人が知ってたら、それはそれで凄いことかなと思う。
私は当時この曲が大好きで、カラオケでもよく歌っていたのだけど、また今度歌ってみようかな。
確かね、CMとは違う別ヴァージョンのシングルもリリースされていて、それも買った記憶がある。
※「瓜二つ」って書いたけど、そういう触れ込みだっただけで、実際は同一人物です。
90年というと、私は高校2年生で、このグループのファンではあったが、J-POP(当時はそういうジャンル名ではなかったが)は幅広く聞いていて、好きな曲をCDレンタルしてカセットテープに録音するというのをコレクションにしていたので、この頃のヒット曲は、今でも思い入れが深い。
米米クラブの「浪漫飛行」なんかは、この年の学校祭のテーマソングにもなったし、同じく大ヒットを飛ばした「おどるポンポコリン」なんかもまた然りだが、カラオケでよく歌っていた曲として、THE BLUE HEARTSの「情熱の薔薇」とか、B'zの「EASY COME EASY GO!」なんかも好きだったなあ・・・。
そうだなあ・・・どこまでできるかわからないけど、レンタル店でアルバムを片っ端から探して、この時期限定のヒット曲集でも作ってみたい。それをカーステとかで聴いたら凄く楽しそう。
90年に、「たま」というバンドが、「さよなら人類」をいう曲を大ヒットさせ、折からのバンドブームの中、一躍人気バンドの仲間入りをした。
調べてみると、03年10月をもって、バンドとしては解散したとのことだけど、友人と色々と話している中で、「今の若い人たちは知らないのだろうなあ・・・」という話になった。
どうなんでしょうね?解散したのが十二年も前だと、やっぱり若い人たちは知らなくても不思議はないのかな?
同じ時代の話で言うと、これは友人との話題には上らなかったのだけど、同じ90年に、リゲインのCMソングで、※時任三郎さんに瓜二つ(?)の「牛若丸三郎太」なるシンガーが歌ってメガヒットを飛ばした「勇気のしるし~リゲインのテーマ~」という曲も、前に何かの時に、「今の若い人は知っているのかな・・・」って思ったことがあるのだが、早いもので二十五年も前の曲になってしまったので、10代の人が知ってたら、それはそれで凄いことかなと思う。
私は当時この曲が大好きで、カラオケでもよく歌っていたのだけど、また今度歌ってみようかな。
確かね、CMとは違う別ヴァージョンのシングルもリリースされていて、それも買った記憶がある。
※「瓜二つ」って書いたけど、そういう触れ込みだっただけで、実際は同一人物です。
90年というと、私は高校2年生で、このグループのファンではあったが、J-POP(当時はそういうジャンル名ではなかったが)は幅広く聞いていて、好きな曲をCDレンタルしてカセットテープに録音するというのをコレクションにしていたので、この頃のヒット曲は、今でも思い入れが深い。
米米クラブの「浪漫飛行」なんかは、この年の学校祭のテーマソングにもなったし、同じく大ヒットを飛ばした「おどるポンポコリン」なんかもまた然りだが、カラオケでよく歌っていた曲として、THE BLUE HEARTSの「情熱の薔薇」とか、B'zの「EASY COME EASY GO!」なんかも好きだったなあ・・・。
そうだなあ・・・どこまでできるかわからないけど、レンタル店でアルバムを片っ端から探して、この時期限定のヒット曲集でも作ってみたい。それをカーステとかで聴いたら凄く楽しそう。
先週水曜日に、人事異動に伴う歓送迎会があったのだが、最近は一時期に比べて飲み会の機会もめっきりと減った。
そんな中、先日うちの職場の上層部に、「飲み会への参加を強要された」という通報(?)があったらしい。
「強要」・・・、私が職場に入った二十年前は確かに多くあり、新人だった頃は、余程のやむを得ない事情(出張とか、身内の不幸とか)がない限り、欠席なんて許されないというような雰囲気があった。
さすがに最近は、「パワハラ」という言葉が市民権を得たせいもあるのか、少なくとも私の周りではそういうことはなくなり、「気乗りのしない回には無理してまで出ることはない」という私のような主義の人にとっては大変気が楽になったので、通報のあったケースも、昔のようなあからさまなものではなく、例えば、欠席の意思表示をしたら「都合が悪いのか?」と聞かれたとか、そんなレベルなのではないかという気がしないでもない。
もっとも、仮にそうだったとしても、「ハラスメント」の定義に当てはめるならば、言う方は悪気はなくても、言われた側がそれで不快な思いをしたならば、その時点で問題視されてしまうということになるので、これに理解を示すのか、あるいは「そんなことも言えないような世知辛い世の中になったのか」と考えるのかは、恐らくだけど人によって温度差が出るだろうと思う。
でも、真相がどうあれ、通報した人の気持ちは、よく分かる。
私だって、新人の頃から、出たくもない会への参加を強要されたなんてことは一度や二度じゃないし、あからさまな「強要」はなくても、欠席の意思表示をしただけで白い目で見られたり、翌日冷たい態度を取られたりしたこともあったからね。
職員同士親睦を深めるという観点からすると、「参加したい人だけ参加して楽しめばいい」という考えを疑問視するのもわからなくもないし、過度に気を遣うと、楽しめるものも楽しめなくなるってのもわかるんだけど、それでもやっぱり、「自分がされて嫌なことは人にもしない」という考えを優先させるのが私なので、長々と書いちゃったけど、この問題の結論としては、「この一件が、今一度みんなが考え直すよいきっかけになってくれればと思う」ってところかな。
因みに、次の飲み会は、今のところ予定はない。
嫌な思いをしたことはあったけど、飲み会自体を嫌っているわけでは決してないので、楽しい思いができる機会が今後も多くあることを願いたい。
そんな中、先日うちの職場の上層部に、「飲み会への参加を強要された」という通報(?)があったらしい。
「強要」・・・、私が職場に入った二十年前は確かに多くあり、新人だった頃は、余程のやむを得ない事情(出張とか、身内の不幸とか)がない限り、欠席なんて許されないというような雰囲気があった。
さすがに最近は、「パワハラ」という言葉が市民権を得たせいもあるのか、少なくとも私の周りではそういうことはなくなり、「気乗りのしない回には無理してまで出ることはない」という私のような主義の人にとっては大変気が楽になったので、通報のあったケースも、昔のようなあからさまなものではなく、例えば、欠席の意思表示をしたら「都合が悪いのか?」と聞かれたとか、そんなレベルなのではないかという気がしないでもない。
もっとも、仮にそうだったとしても、「ハラスメント」の定義に当てはめるならば、言う方は悪気はなくても、言われた側がそれで不快な思いをしたならば、その時点で問題視されてしまうということになるので、これに理解を示すのか、あるいは「そんなことも言えないような世知辛い世の中になったのか」と考えるのかは、恐らくだけど人によって温度差が出るだろうと思う。
でも、真相がどうあれ、通報した人の気持ちは、よく分かる。
私だって、新人の頃から、出たくもない会への参加を強要されたなんてことは一度や二度じゃないし、あからさまな「強要」はなくても、欠席の意思表示をしただけで白い目で見られたり、翌日冷たい態度を取られたりしたこともあったからね。
職員同士親睦を深めるという観点からすると、「参加したい人だけ参加して楽しめばいい」という考えを疑問視するのもわからなくもないし、過度に気を遣うと、楽しめるものも楽しめなくなるってのもわかるんだけど、それでもやっぱり、「自分がされて嫌なことは人にもしない」という考えを優先させるのが私なので、長々と書いちゃったけど、この問題の結論としては、「この一件が、今一度みんなが考え直すよいきっかけになってくれればと思う」ってところかな。
因みに、次の飲み会は、今のところ予定はない。
嫌な思いをしたことはあったけど、飲み会自体を嫌っているわけでは決してないので、楽しい思いができる機会が今後も多くあることを願いたい。























