
お世話になります
平成の終わり頃、令和の手前に60歳となります
これを機に、勝手に働き方改革を断行いたします
なんて与太話はともかく、ご報告致します
昨年2月より株式会社グランディスエステート東京支店 支店長として勤務しておりましたが、この度、4月20日を持ちまして退職することとなりました
今後も、引続き、東京にて不動産に関わりやっていこうといろいろ考え、模索中であります
面白いお話がありましたらよろしくお願いします
仕事の軸を「会社」をベースにした“硬いモノ”ではなくプロジェクトをベースにした“柔らかいモノ”に
「都合の良い時だけ集まる」「離合集散型共感コミュニティ」をつくりたいなどと考えております
意味不明ですかね
また、60歳を機に個人的な指針として「六箇条の了見」を考えてみました
◆
・なるべく「好きなコト」をし、なるべく「嫌いなコト」はしない
・「協調性」を無くす
もちろん「共感に基づく協調」は大いに意識し大切にする
・「我慢」を無くす
我慢は長続きしないのでやらないが、辛抱はする
・「真面目」を無くす
不マジメではなく「非マジメ」に考える
・「力を抜く」
手を抜くのではない
・「相手のこと、相手がどう思うか」を必ず考える
◆
ということで今回は、私のご報告と「与太郎的に」であります
参考図書)
「すべては好き嫌いから始まる」楠木 健著
「老後は非マジメのすすめ」立川談慶著
「立川談志 落語の革命家 総特集」KAWADE夢ムック
「なぜ与太郎は頭のいい人よりうまくいくのか」 立川談慶著
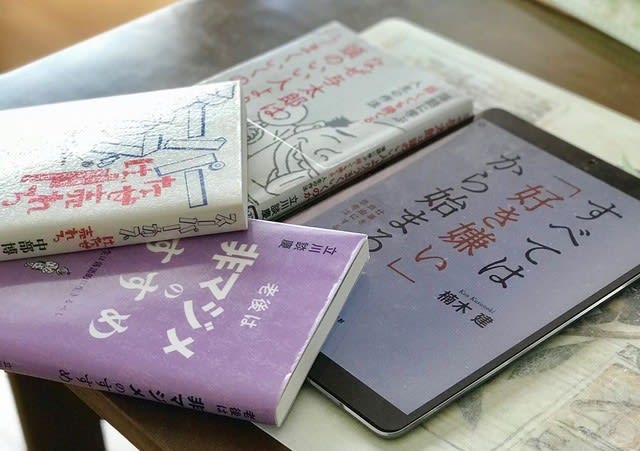
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
ニュートラル思考
プラス思考やマイナス思考ではなく、二元論の否定を意味する
善/悪、正/邪、優/劣、勝ち/負け「2つに1つ」 という考えが二元論
文明は、二元論を強固化させることで進歩した
「負けたくないなら、勝つしかない」 「劣っているより優れていたほうがいい」 「弱者より強者」といった按配で、前者を目指すことを前提とする 脅しのような雰囲気を醸成し、この国は進歩してきた
大学は偏差値という予備校の金儲けの指標のために序列化され、それを補強するかのように企業側も新卒一括採用を続けている
決められたレールに乗らないとまずい風情は、変えられないのが現状
何故か
二元論は効率的だから
二つに一つのわかりやすさの元 昔から発達してきた恩恵を享受しているのが我々現代人 それを素直に認め、感謝しつつも
「もうそれでは立ちゆかなくなってきている」
みんながみんな勝ち組に入れるわけではない 常に勝ちを目指すことは「いじめ」にもつながる
談志は「落語は人間の業の肯定だ」と定義した
落語は、現代人のヨシとする価値観とは真逆なもので出来ている
「正よりも邪、優より劣、勝ちより負け、勝者より弱者」 与太郎を始めとする落語の登場人物は、 ほとんど後者に属す 人間臭い、 だらしない
それでいてというか、だからこそ憎めない連中
現代人の生き様とは、シンメトリーの間柄、ネガとポジ 落語を聴くと、窮屈な二元論で攻め立て追い立てられている現代人はこのうえなく安らぎを感じる
そっくり真似して落語の登場人物のように生きることを奨励しているわけではない → その発想自体が、二元論の弊害
「善か悪か」ではなく「善も悪も」 「勝つか負けるか」ではなく「勝ちも負けも」 「優か劣か」ではなく「優も劣も」と 座標軸を変えるように見つめてみたらどうか、という提案
二律背反する二元論ではなく、すべてを包括してしまうようなおおらかな一元論の世界をイメージしたらもっと楽になるのでは、という提案
気長に、柔軟に、長期戦に臨もう もう一度「低成長」というゆるぎない事実を噛みしめるべき
あらゆる分野で「低成長」が当然の世の中になる つまりは「効率重視からの脱却」をも意味する
さあ、 そのコツは?
「手を抜く」のではなく「力を抜く」 そんな生き方が問われる 「手を抜く」というのは、話題の「建築基準の不適合」がその象徴 手間ヒマを省いた、根本には「効率」を追い求め過ぎるがあまりの「拙速さ」が浮かび上がる
片や「力を抜く」は、イメージとしては、仕事のお礼を、メールを送るというよりも、ふわふわしたような感じで毛筆で礼状を書くような感じ
「手を抜く」というのは「短期決戦を焦るがあまりのミステイク」 「力を抜く」 というのは「リラックスした雰囲気で、気長に長期戦に臨もうとする柔軟な姿勢」 「人生は長期戦」 こういう意識を持つだけで、あらゆるものへの取り組み方が変わってくる
目の前の失敗も、長期戦だとわきまえれば「後で元が取れるように頑張ればいい」と思える 逆に、瞬間風速的な成功は、長期戦だから 「勝って兜の緒を締めよ」ということにつながる
長期戦で要求されるのは、短期戦での「瞬発力」ではなく「持続力」になる 非マジメに生きることは、したたかに生きることと同義語
転んでもただでは起きないどころか、何かを得るために敢えて転ぶようないい意味でのズルさを意味する
非マジメ思考は、まず許容が前提となる
「自分もいい加減なんだから、人のいい加減をも認めてあげよう」という了見
マジメな人は他人もマジメであると思い込みがち 非マジメになると他者を許せるようになり、
結果として笑いのセンスも身につく
甚兵衛さんからふと出た言葉 「そんなに儲けてどうするの」
古典落語では、儲けようと必死になっている人がメインになる場面は圧倒的に少ない まして甚兵衛さんは古道具屋さん どう考えても、それほど需要があるジャンルの商売ではない
→そう考えてしまうこと自体、現代風な価値観に染まっている証拠だが
古今亭志ん朝師匠が『火焔太鼓』のマクラで甚兵衛さんを評して
「世の中をついでに生きている」と言ったが、言い得て妙 「ついでに生きる」というのは、メイン的な立ち位置の放棄
あくまでも副次的な形で生息する のんきさを如実に表した落語らしい表現
それが、生き馬の目を抜くような世界で生きている我々からしてみれば、限りなくホッと出来てしまうのが、面白いところ
落語の登場人物は、与太郎をはじめ、そんな連中ばかり 成長思考で疲れ果てた現代人からしてみれば、彼らはまぶしいスーパー サブ的ポジション
老後は誰もが甚兵衛さんを目指すべき 趣味をはじめとして「儲からないものを気長にやる」姿勢こそが、行き過ぎた利潤追求主義を緩和させて、日本全体を成長から成熟へと変換させるきっかけになる
と、密かに確信
儲けは若い世代へ譲ればいい
最低限の食い扶持を手に、悠然と構える風情を保つ、その方が若い世代にはむしろ、頼もしく映るはず

談志のギャグ
「若いヤツなんて長生きするわけがない。 それが証拠に若いヤ ツで長生きしているヤツは一人もいない。」
という秀逸なものがある
この考えを拡大すると、年を取るということは、年寄りの素晴らしい特権なのかもしれない、と思える
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
ということでした
世の中は低成長ですが、3回目の成人を迎えた身としては、ほんの少し、ほんの少しずつ、成長とは言わないまでも
どちらかの方向へは、進んでいきたい、と愚考する次第です
何か「オモロイ」お話しがありましたら、ぜひ!
引続きよろしくお願いします
ではまた










