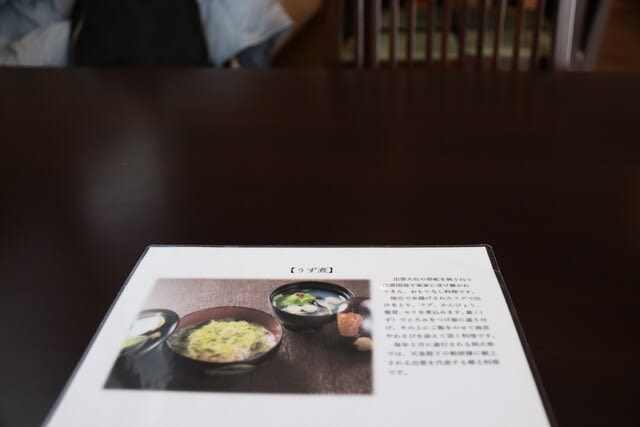松江で一泊をしてから山陰線米子行きに乗り30分弱で安来に着きました。ここからは電車に接続している足立美術館行き無料のシャトルバスに乗り20分で到着しました。
ここ足立美術館は昭和45年、地元安来出身の実業家、足立全康氏によって開館されました。
日本画の巨匠 横山大観 をはじめ竹内栖鳳、川合玉堂、富岡鉄斎、榊原紫峰、上村松園などの近代日本画と、料理人としても名を馳せた北大路魯山人の陶芸作品、
林義雄、武井武雄らの童画や、現代日本画を展示するとともに、約5万坪の日本庭園を堪能できる美術館です。
5万坪の広大な日本庭園は「庭園もまた一幅の絵画である」という信念のもと細部まで維持管理されており、白砂青松庭など多様な庭園が、春夏秋冬の季節ごとに美しい姿を
見せてくれます。
アメリカ専門誌の日本庭園ランキングでは毎年連続で「庭園日本一」に選出されています。また、フランスの旅行ガイドブック『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』では、
山陰エリアで唯一となる最高評価の「三つ星」として掲載されています。
平成22年に開館40周年を迎えたのを機に新館をオープンしました。足立美術館賞受賞作を中心に、現代を代表する日本画家の優秀作およそ350点を所蔵するほか、毎年秋には
「再興院展」を開催し、日本美術院同人の新作や院展入選作を一堂に展されているそうです。
新館オープン後は現代日本画の粋をあわせてお楽しみいただけるようになり、近代から現代に至る日本画の流れも一望できることとなりましたとパンフレットに記載されていました。
今回は真冬ということもあり観光客は比較的すくなくゆっくり鑑賞出来ました。喫茶室もすいていたのでのんびりし過ぎて新館を見る時間が少なくなったのは残念でした。
帰りは同じく無料のシャトルバスで安来まで送ってもらい安来発15:17のやくも22号で倉敷までいきました。今晩は倉敷泊です。
冬樹の芽光をまとい粛々と