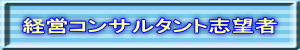■■ 【今日は何の日】 1月 15日 小正月とどんど焼き
経営コンサルタント歴35年の経験から、
◇ 経営者・管理職の皆様
◇ 経営コンサルタントを目指す人
◇ プロの経営コンサルタント
の皆様に、時宜に即した情報を毎日お届けしています。
【今日のブログ】 ←クリック
本日お届けした、その他の記事が掲載されています。![]()
一年365日、毎日が何かの日です。
季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。
これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。
独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。 詳細 ←クリック
】 日付を指定して【今日は何の日】を閲覧できます ■■ 【今日は何の日】 1月 15日 ■ どんど焼き<o:p></o:p> ■ 初閻魔<o:p></o:p> ■ 【一口知識】 小豆粥<o:p></o:p>
【今月の今日は何の日】 【今日は何の日】の今月分を月単位で閲覧できます

【今日の写真】 福岡・筥崎宮(はこざきぐう)近くにある植物園
ぼたんが寒風の中で凜と咲いていました。![]() 1月15日
1月15日■ 小正月<o:p></o:p> 小正月(こしょうがつ)とは、満月を年の始めとした、古い暦上の正月の名残で、正月の望の日(満月の日、旧暦1月15日)のことをもともとは指しました。
小正月の期間は、一般的には14日の夕から15日、地方によっては16日までとか20日までを含めるなど土地によつて多少の違いがあるようです。
呼び名も「小正月」以外に「女正月」と言ったり、地方によっては「若年」とあ「若正月」などとも言うようです。
餅をつく地方もあるようですが、私の子供の頃は団子を作って、飾り物などと共に木に刺して床の間に飾っていました。小正月が過ぎるとそれを焼いて醤油を付けて食べました。米粉の団子なので、香ばしさが違います。
古くは朝に小豆粥を食べる習慣があり、「土佐日記」や「枕草子」などにも記されています。
「どんど焼き」とは小正月の行事で、正月の松飾りや注連縄(しめなわ)などを一カ所に積み上げて燃やすという、日本の各処で行われる火祭り行事です。
残り火で、木や竹にさした団子や餅を焼いて食べるという風習です。それを食べるとその年は健康でいられと言われ、無病息災や五穀豊穣を祈ります。
成人の日が15日と定まらなくなった今日では、1月15日前後の終末に行う地方も増えました。
私は「どんど焼き」と聞いてきましたが、「どんどん焼き」とか「とんど焼き」など、色々な呼び名があるようです。その語源は、火が燃えるのを見て「尊(とうと)や尊(とうと)」というのが訛ったという説が有力です。 
藪入りの1月と7月の15~16日は、「閻魔賽日(えんまさいじつ)」と言って、地獄の釜の蓋が開いて鬼も亡者も休むとされる日です。
1月15日を「初閻魔」といいます。寺院では、十王図や地獄相変図を拝んだり、閻魔堂に参詣したりすることから「十王詣」とも言います。
十王とは地獄にいて亡くなった人の罪を裁く10人の判官のことで、閻魔大王はその一人です。
閻魔はインドの神話にある神で、人類最初の死者だったと言われています。そのことから「死の神」として冥界を支配しています。一二途(さんず)の川を渡る死者を待ちかまえて審判する判官です。善人は極楽へ、悪人は地獄へ落とす、その判断をします。審判の時に、嘘をつくと舌を抜かれるとも言われています。
この縁日に参拝すると長寿や厄除けの功徳にあずかれるそうです。
小豆粥(あずきがゆ)とは、米と小豆を炊き込んだお粥のことで、”ハレの日”、すなわち何かの行事の時に食べられます。
【Wikipedia】
中国においては、古くは冬至の際に小豆粥が食せられた。後にこの風習が発達して12月8日には米と小豆ほか複数の穀物や木の実を入れた「臘八粥」(ろうはちがゆ)というものが食せられ、六朝時代の中国南部では1月15日に豆粥が食せられた(『荊楚歳時記』)。
これが日本に伝わって1月15日すなわち小正月の朝に小豆粥を食するようになったと考えられている。『延喜式』によれば、小正月には宮中において米・小豆・粟・胡麻・黍・稗・?子(ムツオレグサ)の「七種粥」が食せられ、一般官人には米に小豆を入れたより簡素な「御粥」が振舞われている。
これは七種粥が小豆粥に他の穀物を入れることで成立したものによるとする見方がある。また、紀貫之の『土佐日記』によれば、承平7年(935年)の1月15日(小正月)の朝に「あづきがゆ」を食したという記述が登場している。江戸時代には15日すなわち「望(もち)の日」の粥という語が転じて「餅(の日)」の粥と解せられ、小豆粥に餅を入れて食べる風習も行われるようになった。今日でも地方においては正月や田植、新築祝い、大師講などの際に小豆粥や小豆雑煮で祝う風習のある地方が存在す。
![]() 毎日複数本発信
毎日複数本発信 ![]()