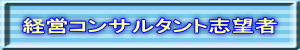■■【心de経営】 実践編 12 無用の用・不易流行

新シリーズの【心de経営】は、「経営は心deするもの」という意味になります。それとともにフランス語の前置詞であります「de(英語のof)」を活かしますと、「経営の心」すなわち、経営管理として、あるいは経営コンサルタントとして、企業経営をどの様にすべきか、経営の真髄を、筆者の体験を通じて、毎月第三火曜日12時に発信いたします。

【筆者紹介】 特定非営利活動法人日本経営士協会理事長 藤原 久子 氏
北海道札幌市出身、20年間の専業主婦を経て、会計事務所に約4年半勤務。その後平成元年7月に財務の記帳代行業務並びに経理事務員の人材派遣業の会社を設立し、代表取締役として現在に至る。従業員満足・顧客満足・地域貢献企業を目指し、企業の永続的発展を願う。
平成22年には横浜型地域貢献企業の最上位を受賞、続いてグッドバランスの受賞により、新聞、雑誌の掲載をはじめ、ラジオやWebTV(日本の社長100・神奈川県社長t v)に出演したりして、各種メディアで紹介されている。
←クリック

自社の経営に当たりまして、何かと忙しい経営者に安心して事業に専念してほしいとの想いと、そして忙しい経営者に、私たちからは「もっと心の通いあうサービス提供を」という原点を忘れてはならないと常に考えております。また、「顧客第一主義」と「企業は人なり」の精神を揺るぎないものとして持ち続けることも大切です。
その信念に「学び」をプラスして更なる人間的魅力を形成してはじめて、従業員やお客様から信頼されるのです。そのためにも、まず自分自身を磨くことが大切です。
人にはそれぞれ自分なりの生き方があります。このメールマガジンを通して、当メールマガジンの購読者であります経営者様をはじめ、これから経営者として歩み始めるみなさまや日本経営士協会会員の気づきや学ぶ機会になれば、これほどに嬉しいことはございません。
 無用の用 ・ 不 易 流 行
無用の用 ・ 不 易 流 行
「心で経営」をテーマにお届けして参りました私の企業人生も、前回を最終章として綴らせていただきました。長期に亘りご愛読いただき誠に有り難うございました。
これからは複雑な現代社会の中を生きぬく術・視点はどこにあるのかを私なりにお伝えする事を通して、読者の皆様にもご参加いただける様なコミュニケーションサロンとしての姿に成長していく事を願っております。その為には、時には叱咤激励をして頂きたく思います。
さて一回目は、過日横浜女性ネットワーク会議に出席して感じた事をお届けすることから始まりたいと思います。
■ 生きること、働くこと
女性の活躍促進が、日本の成長戦略の中核と言われる昨今、16年ぶりに史上2人目の女性事務次官に就任された村木厚子厚生労働事務次官をお迎えして、働き続けていらした原動力、これからの時代を担う女性たちに向けたメッセージを頂戴しました。
安倍総理の「成長戦略スピーチ」で、企業の方針決定過程に対して、女性の参画を促すという国レベルの視点で、固い内容のデータ説明もあっという間に400名超の参加者を自分の世界に引き込み、一体化させた見事な話術に感動しました。会場全体が終始暖かい雰囲気に包み込まれ、時折起こる笑いの渦、和みのひとときは、お人柄とキャリアの成せる技だったのでしょうか。
内容は総じて、女性の活躍推進・仕事と家庭の両立支援に係る施策の概要として、女性が抱える問題つまり、出産・育児・介護・の問題を社会全体で考え支援してゆく事。男性の育休取得促進等育児への関わりの促進他、次世代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資するために、国において地方公共団体及び事業主が行動する際の行動計画の策定義務づけ、10年間の集中的・計画的な取り組みを推進するということでした。
日本再興戦略として改訂2014年未来への挑戦を掲げ、女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築等が織り込まれたものでした。
厚生労働事務次官の村木厚子さんが、究極の立場に立たされた時に(H21.7.13~H22.9.20)何故頑張りぬく事ができたのでしょうか。
・仕事をして来たこと。
・家族の支えがあったこと。
・真実を貫け、負けるな。
・危機対応に慣れることも必要。
・今、何ができるかを考えるようになった。
・気分転換の必要性。
・頼りになった言葉として「何とかなる」
・根拠のない自信が大事。
・苦しかったら立ち止まって考える。
平成27年度は、これまでの女性活躍推進に向けた総合データベース化に力を注ぐようです。ネットワーク社会では、男性も女性もそれぞれの環境で、客観的に自分の持ち味を魅せ、認め合うことが出来たうえで、心のよりどころになれる組織体作りをし、貢献度の要となる人材を社会は欲していることが背景となっているようです。多様なキャリアが人を育て、自分らしく働き輝く為に自分の軸足を基にエリアを拡げる努力が必要だと感じました。
■ 「無用の用」「不易流行」
老子道徳経11章「無用の用」という概念があり、一見役に立たないと思われるものが実は大きな役割を果たしているという意味で、無用を知って初めて有用について語ることが出来るというものです。
激動の時代をいきてゆく上で是非覚えておきたい言葉として「不易流行」があります。松尾芭蕉が「奥の細道」の旅の間で体得したものです。世の中の変化、状況の変化があっても変わらざる真理を意味します。
「不易」すなわち「不変の真理」不易を基礎として刻々と流行する新な文化が発展してきました。時代を超えて変わらない価値のあるもの、豊かな人間性、正義感、公正さを重んじ自律と強調、思い遣り、人間尊重を重視し、一人ひとりの人間が「不易」と「流行」の狭間で成長していきます。
激動する現代の変化とともに変えてゆく必要性のあるものを目先の価値観にとらわれ、短期的に実用的なものを求めがちですが、国際化や情報化などの社会変化を柔軟かつ的確に対応できる資質や能力が求められます。
つまりこのような時代だからこそ変わらぬものを変わらぬ方法でつたえることではなく、変わらぬものを変わりゆく時の流れに合わせ、新たな価値を加えて改めて認識させていくよう努力する向上心にあるのではないでしょうか。
 ■■ 【心 de 経営】 バックナンバー ←クリック
■■ 【心 de 経営】 バックナンバー ←クリック
 ■■ 経営コンサルタントを目指す人の60%が覧るホームページ ←クリック
■■ 経営コンサルタントを目指す人の60%が覧るホームページ ←クリック


![]() 毎日複数本発信
毎日複数本発信 ![]()