■【経営士ブログ 今日は何の日】4月25日 孔子祭 東京・湯島聖堂は孔子で知られる
【今日は何の日】は、ウェブサイトと連動して、関連情報やその他の情報も併せて【経営マガジン】としてお届けしています。
そちらも併せてご覧下さると幸いです。
http://www.glomaconj.com/glomaconsph/topics.html

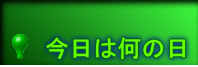
※ 前日のマガジン ←クリック
一年365日、毎日が何かの日です。
季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。
これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。
独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。 詳細 ←クリック 
【今日は何の日インデックス】
日付を指定して【今日は何の日】を閲覧できます
仁和寺は仁和2年(886年)第58代光孝天皇によって発願され、第59代宇多天皇により仁和4年(888年)に完成しました。
「御室桜」の花見の盛んな様子は江戸時代の儒学者・貝原益軒が書いた『京城勝覧』(けいじょうしょうらん)という京都の名所を巡覧できる案内書にも次の様に紹介されています。(仁和寺サイトより)

■ 孔子祭
4月25日は孔子祭です。孔子や儒教の先哲を祀る儀式が行われます。中国で儒教が国教となったときに、釈奠(せきてん/しゃくてん)と呼ぶようになりました。
孔子は紀元前5~6世紀の春秋時代における中国の思想家、哲学者で、儒家の始祖でもあります。幼くして両親を失い、孤児となってからも苦学をつづけたそうです。しかし、生きている間は無冠で、一人の学者であったようです。しかし、後の漢代(前漢)に司馬遷は『史記』の中ででは、孔子の功績を「王に値する」と記述しています。
孔子は、それまでにあった原始宗教を今日の儒教に体系化しました。孔子の考えの基本は「仁(じん)」です。「仁が貫かれるところに道徳が保たれる」と説いています。
「仁」は徳の一つで、人間関係の基本、人間愛をさす倫理規定でもあります。主に「他人に対する親愛の情、優しさ」をさし、仁と、人間の行動に関する概念である義を合わせて、「仁義」という表現もよく知られています。
仁義というと、ある種の世界の言葉のように思われがちですが、人間のあり方の基本のことです。むしろその世界だけに限定すると、映画などでの情報でしかありませんが、一般の人よりもむしろ仲間意識、結束感は強いのではないでしょうか。
今の日本は、残念ながら他人に対する思いやり、気配りがあまりにも希薄になっていると平素思っています。ところが、東日本大震災のような時には、眠っている「仁」が呼び起こされるのか、義援金やボランティア活動などへの参加という形で現れてきます。
「まだまだ日本は捨てたものではない」とテレビでどなたかが言っていましたが、「仁」ということを考え直す時間を各自がとっても良いと思います。もちろん、私自身も実行します。
空港でちょっとしたトラブルがありました。詳細は、相手の方に迷惑がかかるといけませんので記載しませんが、機転を利かせてくれたために難を避けることができました。
空港という人を相手にする仕事が多い人は、どうしてもマニュアル人間になりがちです。上司の方との連携で、利用者に嫌な思いをさせないサービス精神はすばらしいですね。同じことが、マニュアルが定着している国や企業等で起こったらおそらくこのような対処をしてくれなかったでしょう。
日本で仕事をしていてよかった~~
■ その他
◇ 奈良興福寺文殊会
◇ 西山浄土宗御忌
■【きょうの人】 孔子
【Wikipedia】 孔子
孔子(こうし、ピン音: Kǒng zǐ; ウェード式: K'ung-tzu、紀元前551年9月28日‐紀元前479年4月11日)は、春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。 氏名は孔、諱は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。孔子とは尊称である(子は先生という意味)。
■【一口情報】 初心者と中古パソコン
私たちは、何かの習いごとをするときに、「はじめは道具の善し悪しがわからないので、中古品からはじめよう」ということから、中古品を購入して、そこからはじめることがあります。しばらくやっているうちに、どのような道具が自分に適しているかの判断がつくようになると、自分の目的に即した道具を購入します。
パソコンも同じような考えで中古パソコンを買う人がいますが、パソコンの場合にはちょっと異なるように考えています。 <続き> ←クリック

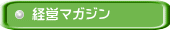
WEB版の経営マガジンは、内容が一層充実していますので、覗いてみてください。
http://www.glomaconj.com/glomaconsph/topics.html

![]()
ケイタイやスマホのカメラで撮影したものもありますので画質があまりよくありません。
私の限られた感性での写真ですので、たいした作品でもありません。
自分自身の作品を、自分のために整理したものです。


◆【経営コンサルタントの育成と資格付与】

 since 1951 特定非営利活動法人・日本経営士協会
since 1951 特定非営利活動法人・日本経営士協会
日本経営士協会は、戦後復興期に当時の通産省や産業界の勧奨を受け、日本公認会計士協会と母体を同じくする、日本で最初にできた経営コンサルタント団体です。
詳しくは、サイトでご覧下さい。
↓↓ クリック
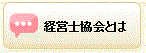 |
日本最古の経営コンサルタント団体・日本経営士協会とは |
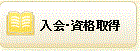 |
資格取得についてや入会の手続等 |
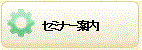 |
経営士が提供する全国各地開催セミナーのご案内 |
| コンサルタントへの依頼、講師捜しに関する情報 | |
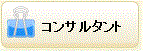 |
コンサルタントとして成功するための各種情報 |
| 経営や管理などに関する各種有益情報 | |
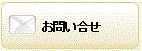 |
お問い合わせや入会・資格取得のお申し込み |
















