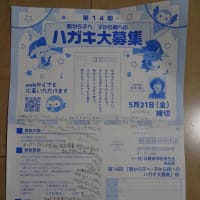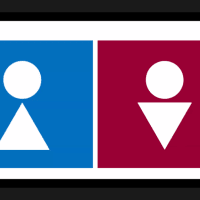子どもを家で見ることと生活団。
4,5才組の時は、迷いがあった。
2,3年仕事辞めて家で子どもを見るつもりだったけど、経済的に本当に大丈夫かなとか。
世間がこれだけ共働きの中、私は正しいのかなとか。
次に仕事をするとしたら、もう少し自由の利く仕事、できるだけ子どもの側にいれる仕事、と思ってたから、起業しか考えられなかった。だから、起業塾行ったり、町作りのワークショップ行ったり、自分の適性を見つけられるワークショップかなという物には行ったりした。それは全部子どもも連れて行った。
でも、それらに行って、起業するにしても何かを始めるには最初の初動が一番エネルギーを使う。その間、子どもの事は蔑ろになる。子どものためと思って、大切な幼児期の今を蔑ろにするくらいなら、あと少し待ってからにした方がいいのではないかという結論に自分の中で至った。
それに、生活団に対しても迷いがあった。
教育はいいと思った。子どもの成長を見てると、ここの教育に間違いはないと思えるようになった。
でも、母の働きに関しては、平等でないと感じた。母の働きが一杯あっても、それはそこまで気にならない。自分の勉強のためと思ったら、頑張れる方だから。
ただ、不平等なのは我慢できない。私は当番に当たる回数が多かった。
食当だと自分の勉強になるという思いがある一方、その回数が均等でなければ、この時間を起業の準備や自分が子どもにしたい事(裁縫等)に充てられるのにと思った。それに体力的にも結構しんどかった。
託児は本当つまらなくて、人の子を預かるために仕事辞めたんちゃうのになーと思ってた。
だから託児に行っても、あまり他の人と喋るというよりは、時間を有効に使わないとと、家計簿をつけたり、何か家の外でもできる用事を持って行ってた。
母の働きが多いのは気にならない。平等であれば。
妊婦だから、遠いからできないというのもちょっと違う。
できる事はあるはず。
ある時モヤっとしたのは、Oさんが母の働きの事を「3年間○○係で逃げ切った」と言ったのを聞いた時。
そういう気持ちでやってるのかと嫌になった。
それが最近になって、ようやく本音を言えるようになったり(生理の日の食当はきついとか)、生活団の今後とかを母同士で話す事があってから、働きをサボろうとしてる母だけではないと分かったのもあって、同じ志を持つ人もちゃんといると知った。それで少し距離を近付けた気がする。
人と共感できるというのは、心の中に暖かい光を灯す。
4,5才組の時は、迷いがあった。
2,3年仕事辞めて家で子どもを見るつもりだったけど、経済的に本当に大丈夫かなとか。
世間がこれだけ共働きの中、私は正しいのかなとか。
次に仕事をするとしたら、もう少し自由の利く仕事、できるだけ子どもの側にいれる仕事、と思ってたから、起業しか考えられなかった。だから、起業塾行ったり、町作りのワークショップ行ったり、自分の適性を見つけられるワークショップかなという物には行ったりした。それは全部子どもも連れて行った。
でも、それらに行って、起業するにしても何かを始めるには最初の初動が一番エネルギーを使う。その間、子どもの事は蔑ろになる。子どものためと思って、大切な幼児期の今を蔑ろにするくらいなら、あと少し待ってからにした方がいいのではないかという結論に自分の中で至った。
それに、生活団に対しても迷いがあった。
教育はいいと思った。子どもの成長を見てると、ここの教育に間違いはないと思えるようになった。
でも、母の働きに関しては、平等でないと感じた。母の働きが一杯あっても、それはそこまで気にならない。自分の勉強のためと思ったら、頑張れる方だから。
ただ、不平等なのは我慢できない。私は当番に当たる回数が多かった。
食当だと自分の勉強になるという思いがある一方、その回数が均等でなければ、この時間を起業の準備や自分が子どもにしたい事(裁縫等)に充てられるのにと思った。それに体力的にも結構しんどかった。
託児は本当つまらなくて、人の子を預かるために仕事辞めたんちゃうのになーと思ってた。
だから託児に行っても、あまり他の人と喋るというよりは、時間を有効に使わないとと、家計簿をつけたり、何か家の外でもできる用事を持って行ってた。
母の働きが多いのは気にならない。平等であれば。
妊婦だから、遠いからできないというのもちょっと違う。
できる事はあるはず。
ある時モヤっとしたのは、Oさんが母の働きの事を「3年間○○係で逃げ切った」と言ったのを聞いた時。
そういう気持ちでやってるのかと嫌になった。
それが最近になって、ようやく本音を言えるようになったり(生理の日の食当はきついとか)、生活団の今後とかを母同士で話す事があってから、働きをサボろうとしてる母だけではないと分かったのもあって、同じ志を持つ人もちゃんといると知った。それで少し距離を近付けた気がする。
人と共感できるというのは、心の中に暖かい光を灯す。