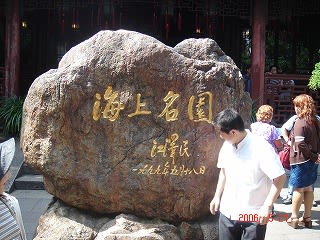● 韓国の嫁いびり!
韓国語講座で、
先生から「宿題です!これを読んで次回、韓国語で感想を言ってもらいます」
と言って花の写真が付いたプリントを1枚渡された。
訳してみて!ビックリ驚いた!
此花の由来が書いてあったのです。
内容は貧しかった遠い昔の悲しい話です。
姑から虐められ続けていた嫁がある日、お腹が空いて空いて我慢ならず
お釜の蓋を取ってご飯を口に入れたところを姑が見つけて、
「主人達が食べない前に食べるとは何事だ!」と言ってこん棒で殴り殺してしまった。
旦那が帰ってきて、悲しんで手厚く、日当たりの良い前山に埋葬してあげた。
翌年からその場所に真っ赤な唇にご飯粒を2つ付けた様な花が一杯咲いたそうだ。
村人は、
これは彼女の魂が乗り移ったんだと言ってそれからこの花を
「嫁ご飯草花(ミョヌリ・パッププルコツ)」
と呼ぶ様になったそうです。
韓国でも今では嫁いびりは余り無いだろうが、
嫁姑の関係はどこの国でも潜在しているものなんだね。
そして貧しかった昔からの言い草からかもしれないが、
今でも韓国人は 挨拶代わりに パンモゴッソヨ? ご飯食べた?と言うようだ。
なお日本ではこの花と同じようなものに、深い山に咲く、ミヤマママコナと言う花がありますよ。

でもどうして先生がこの花を選んだのだろうね。
花がきれいだったからだろうか?
花の名前の由来に何かを感じたのだろうか?
韓国語で聞いてみようかな!

韓国語講座で、
先生から「宿題です!これを読んで次回、韓国語で感想を言ってもらいます」
と言って花の写真が付いたプリントを1枚渡された。
訳してみて!ビックリ驚いた!
此花の由来が書いてあったのです。
内容は貧しかった遠い昔の悲しい話です。
姑から虐められ続けていた嫁がある日、お腹が空いて空いて我慢ならず
お釜の蓋を取ってご飯を口に入れたところを姑が見つけて、
「主人達が食べない前に食べるとは何事だ!」と言ってこん棒で殴り殺してしまった。
旦那が帰ってきて、悲しんで手厚く、日当たりの良い前山に埋葬してあげた。
翌年からその場所に真っ赤な唇にご飯粒を2つ付けた様な花が一杯咲いたそうだ。
村人は、
これは彼女の魂が乗り移ったんだと言ってそれからこの花を
「嫁ご飯草花(ミョヌリ・パッププルコツ)」
と呼ぶ様になったそうです。
韓国でも今では嫁いびりは余り無いだろうが、
嫁姑の関係はどこの国でも潜在しているものなんだね。
そして貧しかった昔からの言い草からかもしれないが、
今でも韓国人は 挨拶代わりに パンモゴッソヨ? ご飯食べた?と言うようだ。
なお日本ではこの花と同じようなものに、深い山に咲く、ミヤマママコナと言う花がありますよ。

でもどうして先生がこの花を選んだのだろうね。
花がきれいだったからだろうか?
花の名前の由来に何かを感じたのだろうか?
韓国語で聞いてみようかな!