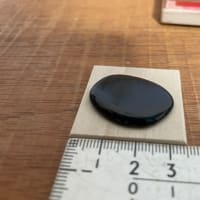二胡の弓
弓には二つのタイプがあります北方式と南方式です。
形としては、持ち手のところの毛のまとめ方が違うだけです
弓は竹と弓毛と弓魚の3つの部分で作られています。
竹は、基本的には中国産の篠竹(女竹ともいう)を使います。
この特徴は、内部に空洞がほとんどないことです。約1,5ミリくらいの細い管が通っています。
それと節と節の間がとても長く、北方式に使われるものは節と節の間が60センチくらいありますが、
中には45センチくらいのものもあります。
ですから弓に作った時節の間の短いものは、弓のほぼ真ん中くらいに節が一つあります。
この節の間の短いもののほうが竹は比較として硬いものが多く、
いわゆる無節といわれる弓(節の間が60センチ)のものは、多少柔らかめのものが多いです。
まれに硬いものもありますが、それらは、太さも太くなります。
竹は基本的に脱脂して使うものですが、比較的単価の安いものは、脱脂をせずに生のまま使われることが多く、
柔らかくまた弓それぞれの硬さの個体差がとても大きいです。
また1万円を超えるような弓は、熱をかけて脱脂をしてあるため、竹の一部に焦げ跡が残ることもあり、
特に高級なものといわっれるものの中には竹の上に塗装をしてあるものが多いです、
がこれはプロはほとんど使いません、
弓として良いのでしょうが、竹に塗装をすると、竹と弓毛とを二本の弦に当時にあてて弾く、重音が出せなくなるからです。
高難度の中国曲の中には重音を使う曲もかなり含まれますから。
馬毛は基本的にはモンゴル(内モンゴルも含み)の馬毛です。
ヴァイオリンなどはモンゴル以外のカナダ産のものもありましたが、今は日本には入ってきていません。
一頭の馬からとれる馬毛の量は約350gくらいです、
そのなかで、二胡の弓のように長さが90センチを超えるような馬毛は約50gくらいです。。
ヴァイオリンニ使うような約70センチから80センチの長さのものは、100gほどとれます。
それ以外の短いものは、ブラシや筆に使われます。
二胡の弓に使われる弓毛の量は9グラムくらいから10gの間です。
毛の数にすると約250本から280本くらいの数です。
一頭の馬毛の中でも太さはかなり違い、太いものは0・3mm
細いものは、0・1ミリくらいの差がありますが、大体は0.15mm前後です
ヴァイオリンの弓などの場合、
これらの極端に太いもの細いものは取り除かれ又縮れたもの、撚れたもの、枝毛のあるものなどは取り除かれますが、
二胡の弓の場合安い物販売額一万円以下のものは、比較的毛の選別をせずに作られているものが多いです。
15000円を超える弓などは、かなり毛も選別されているようです。
(販売価格は同じ弓のメーカーでも、販売各社によって値段は違いますから金額はおおよそと考えてください。又価格は2018年現在です)
二胡の弓毛は基本的に脱色されています。脱色は塩素を使いますから毛質を痛めます。
ですから弓がが切れるものが多いのです。また弓がは洗浄は水洗いだけがされています。
その後脱色されますが、脱色の程度によっては、多少の油分が残ります。
脱色されている難点は脆くなるのと、キューティクルが傷むのとでまつやにがとてもつけにくくなります。
中には10分も松脂を付けるのにかかるのもあります。
無脱色の馬毛は洗浄されてさえいれば両面10回くらい松脂を付ければ弾くことが可能です。
(20数年前の二胡弓は脱色されていいなかった物が多いようです)
又馬毛には牡馬の毛が優秀というメーカーもありますが、これは実証されていません。
なぜなら本当に牡馬の毛が使われているかがわからないこと、
そして、何故、牡馬の尻尾が良いのかの説明が無いからです。
ヴァイオリンの弓の製作メーカーでも、まれに、牡馬が優秀というところもあります。
それらの説明によりますと、
牡馬だと尿が馬毛に掛らないからだといわれますが、疑問は大便は雌雄どちらのものもかかります。
又モンゴルの馬頭琴の演奏家の方に聞いたところでは、どちらの馬毛も分けてはいないとのことでした。
ですので、ここでは、牡馬の毛のほうが優秀というのは確認が取れませんでした。
弓魚は今様々な形のものがあるいは色のものが発売されています。
ヴァイオリンの弓魚(フロッグといいます)もいろいろありますが、
色などの事よりむしろその質と、重さに重点が置かれています。それは弓全体のバランスを考えているからです。
二胡の弓の弓魚は南方式の重さが、約3グラム、北方式の弓魚が5グラム前後です。
固定されている南方式の弓魚は交換できません。交換するためには毛を切らないといけないからです。
また弓魚はどんな竹にも付け替えが可能です。
気を付けなければいけないのは
同じメーカーでも、弓魚についているネジの位置がばらばらであるという事、
その位置によっては、毛が緩くなりすぎたり、きつくなりすぎることですが、
ネジの位置は、変えることができます、
ネジの太さが2.8と一定ですから、2・5ミリのドリルの錐で下穴をあけておけば、
タップ(ネジ錐)を使わなくともそのままねじ込めます、
(木でできている弓魚はまれに割れることもあります)
ただし、弓魚に対して垂直に穴を立てないと、弓毛がねじれます。
弓には二つのタイプがあります北方式と南方式です。
形としては、持ち手のところの毛のまとめ方が違うだけです
弓は竹と弓毛と弓魚の3つの部分で作られています。
竹は、基本的には中国産の篠竹(女竹ともいう)を使います。
この特徴は、内部に空洞がほとんどないことです。約1,5ミリくらいの細い管が通っています。
それと節と節の間がとても長く、北方式に使われるものは節と節の間が60センチくらいありますが、
中には45センチくらいのものもあります。
ですから弓に作った時節の間の短いものは、弓のほぼ真ん中くらいに節が一つあります。
この節の間の短いもののほうが竹は比較として硬いものが多く、
いわゆる無節といわれる弓(節の間が60センチ)のものは、多少柔らかめのものが多いです。
まれに硬いものもありますが、それらは、太さも太くなります。
竹は基本的に脱脂して使うものですが、比較的単価の安いものは、脱脂をせずに生のまま使われることが多く、
柔らかくまた弓それぞれの硬さの個体差がとても大きいです。
また1万円を超えるような弓は、熱をかけて脱脂をしてあるため、竹の一部に焦げ跡が残ることもあり、
特に高級なものといわっれるものの中には竹の上に塗装をしてあるものが多いです、
がこれはプロはほとんど使いません、
弓として良いのでしょうが、竹に塗装をすると、竹と弓毛とを二本の弦に当時にあてて弾く、重音が出せなくなるからです。
高難度の中国曲の中には重音を使う曲もかなり含まれますから。
馬毛は基本的にはモンゴル(内モンゴルも含み)の馬毛です。
ヴァイオリンなどはモンゴル以外のカナダ産のものもありましたが、今は日本には入ってきていません。
一頭の馬からとれる馬毛の量は約350gくらいです、
そのなかで、二胡の弓のように長さが90センチを超えるような馬毛は約50gくらいです。。
ヴァイオリンニ使うような約70センチから80センチの長さのものは、100gほどとれます。
それ以外の短いものは、ブラシや筆に使われます。
二胡の弓に使われる弓毛の量は9グラムくらいから10gの間です。
毛の数にすると約250本から280本くらいの数です。
一頭の馬毛の中でも太さはかなり違い、太いものは0・3mm
細いものは、0・1ミリくらいの差がありますが、大体は0.15mm前後です
ヴァイオリンの弓などの場合、
これらの極端に太いもの細いものは取り除かれ又縮れたもの、撚れたもの、枝毛のあるものなどは取り除かれますが、
二胡の弓の場合安い物販売額一万円以下のものは、比較的毛の選別をせずに作られているものが多いです。
15000円を超える弓などは、かなり毛も選別されているようです。
(販売価格は同じ弓のメーカーでも、販売各社によって値段は違いますから金額はおおよそと考えてください。又価格は2018年現在です)
二胡の弓毛は基本的に脱色されています。脱色は塩素を使いますから毛質を痛めます。
ですから弓がが切れるものが多いのです。また弓がは洗浄は水洗いだけがされています。
その後脱色されますが、脱色の程度によっては、多少の油分が残ります。
脱色されている難点は脆くなるのと、キューティクルが傷むのとでまつやにがとてもつけにくくなります。
中には10分も松脂を付けるのにかかるのもあります。
無脱色の馬毛は洗浄されてさえいれば両面10回くらい松脂を付ければ弾くことが可能です。
(20数年前の二胡弓は脱色されていいなかった物が多いようです)
又馬毛には牡馬の毛が優秀というメーカーもありますが、これは実証されていません。
なぜなら本当に牡馬の毛が使われているかがわからないこと、
そして、何故、牡馬の尻尾が良いのかの説明が無いからです。
ヴァイオリンの弓の製作メーカーでも、まれに、牡馬が優秀というところもあります。
それらの説明によりますと、
牡馬だと尿が馬毛に掛らないからだといわれますが、疑問は大便は雌雄どちらのものもかかります。
又モンゴルの馬頭琴の演奏家の方に聞いたところでは、どちらの馬毛も分けてはいないとのことでした。
ですので、ここでは、牡馬の毛のほうが優秀というのは確認が取れませんでした。
弓魚は今様々な形のものがあるいは色のものが発売されています。
ヴァイオリンの弓魚(フロッグといいます)もいろいろありますが、
色などの事よりむしろその質と、重さに重点が置かれています。それは弓全体のバランスを考えているからです。
二胡の弓の弓魚は南方式の重さが、約3グラム、北方式の弓魚が5グラム前後です。
固定されている南方式の弓魚は交換できません。交換するためには毛を切らないといけないからです。
また弓魚はどんな竹にも付け替えが可能です。
気を付けなければいけないのは
同じメーカーでも、弓魚についているネジの位置がばらばらであるという事、
その位置によっては、毛が緩くなりすぎたり、きつくなりすぎることですが、
ネジの位置は、変えることができます、

ネジの太さが2.8と一定ですから、2・5ミリのドリルの錐で下穴をあけておけば、
タップ(ネジ錐)を使わなくともそのままねじ込めます、
(木でできている弓魚はまれに割れることもあります)
ただし、弓魚に対して垂直に穴を立てないと、弓毛がねじれます。