準決勝進出をかけたラグビー南アフリカ戦、残念ながら完敗してしまいました。
今回は日本の良い所を出せないまま力負けした感じです。やはり実力の差を感じます。でも、ベスト8まで行けたんですから凄いことです。
代表チームの皆様、お疲れ様でした。そして、ありがとう😊!
この後の4強の試合も楽しませて頂きます。
さて、レベル1/72 ホルテンGo229の完成写真アップします。
2017年の静岡ホビーショーのハセガワブースのバーゲン会場で安く購入したキットです。
実機は第二次大戦後半にドイツの若き技術者ホルテン兄弟が開発した全翼(無尾翼)のジェット戦闘機です。
初飛行は1945年2月で、最高速度977km/h、500kg爆弾二発を積んで飛ぶことができ、飛行安定性も優れていました。
武装は30mm機関砲2門で航続距離1300km、上昇限度16000mという高性能です。
また、機体の形状と炭素粉を塗装に用いてレーダーステルス性も備えており、戦後の米軍のテストでもそのステルス性能が確認されています。
但し、実戦配備には間に合わず、終戦を迎えましたので、実戦での戦果はありません。
ホルテン229のキットはドラゴンや造形村からもビッグスケールで出ていますが、1/72で現在入手可能なのはレベルだけではないかと思います。
キットは綺麗な凹の筋彫りで、コックピットや脚周りのディテールも1/72としては十分な物です。
組立後は見えなくなる30mm機関砲も再現されています。
パーツ精度も良く、若干の調整だけで何も問題なく組み立てられます。
今回は1/72ということで、飛行姿勢で製作しました。
ジェットエンジン排気口と翼端灯を電飾したことと、機体上面のループアンテナを真鍮線で自作したこと以外は素組みです。
マーキングはキット付属の物を使用しました。
クレオスの半艶塗料をそのまま使用して、クリアを吹かずにデカールを貼ったので見事にシルバリングを起こしています。
やはり手抜きは禁物です。(´;ω;`)
今年9個目の完成です。


















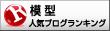


 (飛行機の前に回ると涼しいですよ・・・(笑))
(飛行機の前に回ると涼しいですよ・・・(笑))






























































































