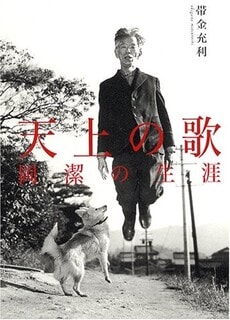エマ・チャップマン/著 熊谷玲美/訳 「ファーストスター 宇宙最初の星の光」読了
NHKBSで、「コズミックフロント」という番組が放送されている。けっこう凝ったCGが登場するので面白かった。「面白かった。」という過去形なのは、最近は、宇宙の番組なのになぜだか恐竜の話が出てきたり、地球の地質学の話が多くなったり、再放送ばかりになってしまって今では全く見なくなってしまったからだ。
放送当初はビッグバンの謎であったり、恒星の寿命、超新星爆発、銀河の生まれ方など、宇宙規模の壮大な話が多く、それがきれいなCGで解説されていた。
そんなトピックスの中に、この本のタイトルになっている「ファーストスター」も取り上げられていたことがあった。ファーストスターというのは、ビッグバンから始まった宇宙の歴史の中で最初に生まれた星のことだ。星は永遠に輝き続けるものではない。星も生まれては死んでゆく。星はその死んだ残骸からまた生まれてくる。じゃ、星がまったくなかった最初の星はどうやって生まれたか、ファーストスターが生まれた時の宇宙の環境はどんなものであったか、そしてその時代の光景を発見することはできるのか。そういった謎を研究しているのが著者である。しかし、その痕跡なり事実はいまだ正確には観測されていない。
ファーストスターが生まれたのは宇宙が始まって2億年ごろだったと言われている。その星がどんなものであったかということを知るにはその当時の宇宙を知る必要がある。だから、この本は宇宙の始まり、すなわちビッグバンの直後から始まる。
ビッグバンの直前、おそらく無限大に小さくて無限大に質量が高かった時というのは今の宇宙での物理法則が適用されないので知ることはできない。しかし、その直後からは研究で明らかにされている。ビッグバンは空間だけではなく時間の始まりでもあるのだが、直後の膨張速度は指数関数的であり、1秒後には100兆×1兆倍という大きさにまで広がったと言われている。インフレーション膨張期と呼ばれている。
この時から約38万年間、物質はプラズマ状態にあり、物質と同時に生まれた光子(光)はそのプラズマに邪魔されてまっすぐ進むことができなかった。38万年後、やっと光がまっすぐ進むことができるようになり、その時に観測者がいれば、景色を見ることができるようになった。これを「宇宙の晴れあがり」と呼ぶ。
物質はどうであったかというと、ビッグバンから3分46秒後に水素とヘリウムの原子核までが合成される。それより大きな原子核は飛び回っている光子が邪魔をするので大きくなれない。ヘリウム4の原子核が約25%、水素の原子核が約75%、0.01%の重水素の原子核、少量のリチウムとヘリウム3の原子核がその構成比率であったとされる。
そんな世界で生まれた最初の星は、金属を全く含まず、質量は太陽の100倍から1000倍の大きさがあったという。なぜこんなに大きな星になってしまうかというと、「ジーンズ質量」というものが決定をしている。
宇宙に漂っているガスが集まって収縮(星が生まれる)するとき、高温のガスよりも低温のガスのほうが少ない量で収縮できる。初期の宇宙は温度が高かったため、大量のガスを必要とし、星も大きくなる。この、ガスの温度と星が生まれるのに必要なガスの量の関係が「ジーンズ質量」なのである。
不思議なのは、星ができるきっかけを作るには、ガスの温度を下げてジーンズ質量を下げてやる必要があるのだが、それは高温の星ができるためには星を冷やす必要があるということである。そして、その役割をしているのが光子である。星が光子を発する、すなわち光り輝くということがエネルギーを運び去り、温度を下げるという効果を生む。なんとも不思議だ。
もうひとつ不思議というか、なんだかよくわからないものに、「オルバースのパラドックス」といものがある。これは、宇宙が有限であるということの証明なのだそうだが、こんな理屈だ。「宇宙の恒星の分布がほぼ一様で、恒星の大きさも平均的に場所によらないと仮定すると、空は全体が太陽面のように明るく光輝くはず」というのだが、なんとなくわかりそうで何となく騙されているような感じがする理屈なのだ。
話はもとに戻り、こんな巨大な星の寿命は短い。その寿命は数百万年くらいだったのではないかと考えられている。そして、その残骸から次の世代の星が生まれるまでには1000万年から1億年という、宇宙のスケールではごく短い時間しか要しなかったという。
その数百万年の間に、ファーストスターの中では水素原子核やヘリウム原子核の核融合によってさまざまな金属(天体物理学では酸素や炭素も金属として取り扱われるらしいので、様々な元素といったほうがよい、)が生まれる。その星が爆発することによって様々な元素を含む次世代の恒星が生まれ、我々人類が生まれる素になっていくのである。
著者たちはそういう現象の痕跡を探す努力をしているのだが、そのために、鉄を含まない星の探索をしている。鉄のスペクトルというのが見つけやすく、それがない星がファーストスターの候補といえる。
宇宙が始まってわずかな時間しか経っていないときに生まれた星をどうやって見つけるのか。おまけにその星は生まれてから宇宙の歴史の中ではわずかな時間といえる期間しか輝かない。それにはふたつの方法がある。
ひとつは、ファーストスターの中で長寿な星をみつけること。もうひとつははるか遠くの空域を調査することである。
ファーストスターにも長寿な星があると考えられている。その質量は太陽の数百倍以上と言われているが、その大きさにはばらつきがある。たとえば、ファーストスターの質量が太陽の0.8倍くらいだと百億年以上は輝き続けることができる。しかし、こういった星は暗いので銀河系の近くでそんな星がないかどうかを探すのだ。銀河系の本体は若い星が多いが、その周辺、ハローと呼ばれる空域には古い星が存在している。そんな中から鉄のスペクトルが出ない星を探す。しかし、なかなかそういった星は見つかっていないらしい。
はるか遠くの空域では矮小銀河の中にある星が候補にあがる。銀河系やアンドロメダ銀河はきれいな渦巻き型をしているが、これはいくつもの銀河が繰り返して合体した末に出来上がったものだ。その元になった銀河のひとつが矮小銀河である。だから、今、観測することができる矮小銀河は、そういった合体を免れた銀河で、その中に存在する星々も古く、ファーストスターの生き残りが存在するかもしれないというのである。
今年の初めに稼働し始めたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はまさに光学的(といっても人間の目には見えない赤外線を見るのだが。)にファーストスターを探そうという望遠鏡なのである。

これらは光学的にファーストスターを探そうという考えだが、もうひとつ、電波でファーストスターを探そうという考えもある。これは、ファーストスターが生まれた頃に発せられた電波、正確には、当時に合成された水素が出す電波を電波望遠鏡(正確には複数の電波望遠鏡を組み合わせた電波干渉計というもの)で見つけようというものだ。
この分野の研究が著者の研究領域だそうだが、その研究はまだまだこれからの分野だそうだ。
原題は「First Light」というが、まさに宇宙が発した最初の光を見つける日はそう遠くないのかもしれない。
しかし、そこにファーストスターや最初の光がみつかったとしてもそこに行くこともできないし、おそらく近づくことさえもできない。それが何か新しいものを生み出すわけでもない。それでも莫大な資金をつぎ込んで見つけようとする原動力というのは一体何なのだろうかと、こういう本を読むたびに思う。
自分たちは一体何者なのだろうか、この宇宙に生きている意味とはなんだろうかという、ただそれだけを知りたいということだろうが、そういった欲望というか渇望がもたらした力が解明する事実には感嘆させられるのである。
NHKBSで、「コズミックフロント」という番組が放送されている。けっこう凝ったCGが登場するので面白かった。「面白かった。」という過去形なのは、最近は、宇宙の番組なのになぜだか恐竜の話が出てきたり、地球の地質学の話が多くなったり、再放送ばかりになってしまって今では全く見なくなってしまったからだ。
放送当初はビッグバンの謎であったり、恒星の寿命、超新星爆発、銀河の生まれ方など、宇宙規模の壮大な話が多く、それがきれいなCGで解説されていた。
そんなトピックスの中に、この本のタイトルになっている「ファーストスター」も取り上げられていたことがあった。ファーストスターというのは、ビッグバンから始まった宇宙の歴史の中で最初に生まれた星のことだ。星は永遠に輝き続けるものではない。星も生まれては死んでゆく。星はその死んだ残骸からまた生まれてくる。じゃ、星がまったくなかった最初の星はどうやって生まれたか、ファーストスターが生まれた時の宇宙の環境はどんなものであったか、そしてその時代の光景を発見することはできるのか。そういった謎を研究しているのが著者である。しかし、その痕跡なり事実はいまだ正確には観測されていない。
ファーストスターが生まれたのは宇宙が始まって2億年ごろだったと言われている。その星がどんなものであったかということを知るにはその当時の宇宙を知る必要がある。だから、この本は宇宙の始まり、すなわちビッグバンの直後から始まる。
ビッグバンの直前、おそらく無限大に小さくて無限大に質量が高かった時というのは今の宇宙での物理法則が適用されないので知ることはできない。しかし、その直後からは研究で明らかにされている。ビッグバンは空間だけではなく時間の始まりでもあるのだが、直後の膨張速度は指数関数的であり、1秒後には100兆×1兆倍という大きさにまで広がったと言われている。インフレーション膨張期と呼ばれている。
この時から約38万年間、物質はプラズマ状態にあり、物質と同時に生まれた光子(光)はそのプラズマに邪魔されてまっすぐ進むことができなかった。38万年後、やっと光がまっすぐ進むことができるようになり、その時に観測者がいれば、景色を見ることができるようになった。これを「宇宙の晴れあがり」と呼ぶ。
物質はどうであったかというと、ビッグバンから3分46秒後に水素とヘリウムの原子核までが合成される。それより大きな原子核は飛び回っている光子が邪魔をするので大きくなれない。ヘリウム4の原子核が約25%、水素の原子核が約75%、0.01%の重水素の原子核、少量のリチウムとヘリウム3の原子核がその構成比率であったとされる。
そんな世界で生まれた最初の星は、金属を全く含まず、質量は太陽の100倍から1000倍の大きさがあったという。なぜこんなに大きな星になってしまうかというと、「ジーンズ質量」というものが決定をしている。
宇宙に漂っているガスが集まって収縮(星が生まれる)するとき、高温のガスよりも低温のガスのほうが少ない量で収縮できる。初期の宇宙は温度が高かったため、大量のガスを必要とし、星も大きくなる。この、ガスの温度と星が生まれるのに必要なガスの量の関係が「ジーンズ質量」なのである。
不思議なのは、星ができるきっかけを作るには、ガスの温度を下げてジーンズ質量を下げてやる必要があるのだが、それは高温の星ができるためには星を冷やす必要があるということである。そして、その役割をしているのが光子である。星が光子を発する、すなわち光り輝くということがエネルギーを運び去り、温度を下げるという効果を生む。なんとも不思議だ。
もうひとつ不思議というか、なんだかよくわからないものに、「オルバースのパラドックス」といものがある。これは、宇宙が有限であるということの証明なのだそうだが、こんな理屈だ。「宇宙の恒星の分布がほぼ一様で、恒星の大きさも平均的に場所によらないと仮定すると、空は全体が太陽面のように明るく光輝くはず」というのだが、なんとなくわかりそうで何となく騙されているような感じがする理屈なのだ。
話はもとに戻り、こんな巨大な星の寿命は短い。その寿命は数百万年くらいだったのではないかと考えられている。そして、その残骸から次の世代の星が生まれるまでには1000万年から1億年という、宇宙のスケールではごく短い時間しか要しなかったという。
その数百万年の間に、ファーストスターの中では水素原子核やヘリウム原子核の核融合によってさまざまな金属(天体物理学では酸素や炭素も金属として取り扱われるらしいので、様々な元素といったほうがよい、)が生まれる。その星が爆発することによって様々な元素を含む次世代の恒星が生まれ、我々人類が生まれる素になっていくのである。
著者たちはそういう現象の痕跡を探す努力をしているのだが、そのために、鉄を含まない星の探索をしている。鉄のスペクトルというのが見つけやすく、それがない星がファーストスターの候補といえる。
宇宙が始まってわずかな時間しか経っていないときに生まれた星をどうやって見つけるのか。おまけにその星は生まれてから宇宙の歴史の中ではわずかな時間といえる期間しか輝かない。それにはふたつの方法がある。
ひとつは、ファーストスターの中で長寿な星をみつけること。もうひとつははるか遠くの空域を調査することである。
ファーストスターにも長寿な星があると考えられている。その質量は太陽の数百倍以上と言われているが、その大きさにはばらつきがある。たとえば、ファーストスターの質量が太陽の0.8倍くらいだと百億年以上は輝き続けることができる。しかし、こういった星は暗いので銀河系の近くでそんな星がないかどうかを探すのだ。銀河系の本体は若い星が多いが、その周辺、ハローと呼ばれる空域には古い星が存在している。そんな中から鉄のスペクトルが出ない星を探す。しかし、なかなかそういった星は見つかっていないらしい。
はるか遠くの空域では矮小銀河の中にある星が候補にあがる。銀河系やアンドロメダ銀河はきれいな渦巻き型をしているが、これはいくつもの銀河が繰り返して合体した末に出来上がったものだ。その元になった銀河のひとつが矮小銀河である。だから、今、観測することができる矮小銀河は、そういった合体を免れた銀河で、その中に存在する星々も古く、ファーストスターの生き残りが存在するかもしれないというのである。
今年の初めに稼働し始めたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はまさに光学的(といっても人間の目には見えない赤外線を見るのだが。)にファーストスターを探そうという望遠鏡なのである。

これらは光学的にファーストスターを探そうという考えだが、もうひとつ、電波でファーストスターを探そうという考えもある。これは、ファーストスターが生まれた頃に発せられた電波、正確には、当時に合成された水素が出す電波を電波望遠鏡(正確には複数の電波望遠鏡を組み合わせた電波干渉計というもの)で見つけようというものだ。
この分野の研究が著者の研究領域だそうだが、その研究はまだまだこれからの分野だそうだ。
原題は「First Light」というが、まさに宇宙が発した最初の光を見つける日はそう遠くないのかもしれない。
しかし、そこにファーストスターや最初の光がみつかったとしてもそこに行くこともできないし、おそらく近づくことさえもできない。それが何か新しいものを生み出すわけでもない。それでも莫大な資金をつぎ込んで見つけようとする原動力というのは一体何なのだろうかと、こういう本を読むたびに思う。
自分たちは一体何者なのだろうか、この宇宙に生きている意味とはなんだろうかという、ただそれだけを知りたいということだろうが、そういった欲望というか渇望がもたらした力が解明する事実には感嘆させられるのである。