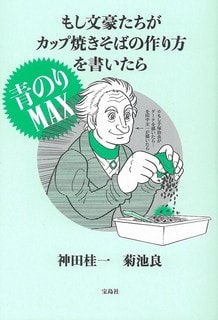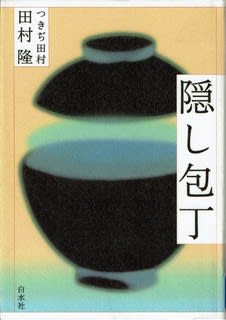北村雄一 「大人の恐竜図鑑 」読了
大人になってからも恐竜が大好きな人というのは大人になっても魚釣りが大好きな人と頭の構造はそれほど変わらないのだろうか?
魚釣りを研究する科学者はいないけれども恐竜を研究する科学者はいるのだからむこうの方がよい構造をしているのだろうか。
海面下も覗き見ることができないけれども化石だけ見ながら分類やましてやその生態を想像するというのもまあ、好き勝手にできて面白いのかもしれない。
僕がまだ科学と学習を読んでいた頃には、ステゴザウルスとブロントサウルス、ティラノサウルスや空を飛ぶやつ、海にいる首の長いやつくらいしか載っていなかったように思うけれども、最近は大きいやつから小さいやつまでやたらと数が多くなったものだ。
そういえば、トリケラトプスってかっこよかった。
恐竜の時代は三畳紀から白亜紀まで、地質時代でいえば中生代、2億5000万年前から6600万年前という約1億8500万年という長い期間だから恐竜も進化を繰り返してどんどん種類も増えてきたわけだ。
興味深いのは、鳥は恐竜から進化したということを大きくクローズアップしているところだ。
たいがいの想像図というのは象の皮膚のような感触で描かれているけれども、実はそこに羽毛をまとったものが多かったというかほとんどが多かれ少なかれ羽毛が生えていたのではないかと考えられている。
その羽根を使ってどのように行動していたかを時代ごとに解説を加えているのだ。最初の羽根の役割は陸上を早く走るための補助動力であった。そのうち、その補助動力を使って木の幹を上るものがでてきた。そこから滑走することを覚えて大空に飛び出した。最新の考察というのはこんな感じだそうだ。
以前の考えでは、鳥の祖先(始祖鳥なんか)は最初から木の上で生活していてそこから滑走することを覚えたと言われていたけれども、爪の形や、元々羽ばたく力を持っていたと思われる筋肉の付き方を総合すると新しい見解が出てくるらしい。
また、一応魚好きの僕にとっては魚の進化も気になる。魚は恐竜ではないのでこの本には直接的には書かれていないけれども、それを食べていたであろう翼竜のことが書かれている。(ちなみに翼竜や海を泳いでいた首長竜は恐竜ではない。)三畳紀の頃の初期の翼竜の奥歯には獲った獲物をすり潰して食べるための歯があったそうだ。それは当事の魚は甲冑のようなエナメル質の装甲で覆われていたのでそうするしかなかったのであるが、時代が下ってジュラ紀の時代になるとそれがなくなったのでただ魚を救い上げて食べるための機能をもった嘴に変わっていく。それは魚自体が今のような鱗に変わってきて飲み込みやすくなって翼竜の姿も変化してきた。魚も明らかに進化をしてきたのだ。
大人の・・・・。というタイトルはどういうところから付けられたのだろうか。今は「ブロントサウルス」という名前の恐竜は存在しないことになっている。ブロントサウルスはアバトサウルスという名前に改名されている。
なぜこういうことが起こるかというと、1800年代後半、化石が見つかると細かく分析することなく学者たちが勝手に名前をつけていたそうだ。ブロントサウルスと名付けられた個体はそれより前にアバトサウルスと名付けられていた個体と同じものだと結論付けられブロントサウルスという名前が消えてしまった。そしてこの二つの恐竜を命名したのは同じ人物だったというから面白い。発掘された1本の歯からでも命名されたものもあったそうだ。そういうことが分類、生態、復元図その他諸々においておこなわれていたということを批判的に書いている。
そんなところが「大人の・・」というタイトルにつながっているのかもしれないが、そこは著者が日本人であるから表現がやわらかだ。「ワンダフル・ライフ」を書いたスティーヴン・ジェイ・グールドなんかはライバルをもっとけちょんけちょんにこき下ろしているから、「大人・・」というにはまだまだ世間ずれしていないようにも思うのだ。著者もサイエンスライターという立場なので学者ほど権威がないという弱点を持っているからかもしれないけれども・・・。
トランプ大統領の大きな支持者であるキリスト教福音派は進化論を否定しているということで知られているが、これだけ精巧に作られてゆく生物を見ていると、確かに神様でなければお創りできないと考えても不思議ではないと思うのである。
大人になってからも恐竜が大好きな人というのは大人になっても魚釣りが大好きな人と頭の構造はそれほど変わらないのだろうか?
魚釣りを研究する科学者はいないけれども恐竜を研究する科学者はいるのだからむこうの方がよい構造をしているのだろうか。
海面下も覗き見ることができないけれども化石だけ見ながら分類やましてやその生態を想像するというのもまあ、好き勝手にできて面白いのかもしれない。
僕がまだ科学と学習を読んでいた頃には、ステゴザウルスとブロントサウルス、ティラノサウルスや空を飛ぶやつ、海にいる首の長いやつくらいしか載っていなかったように思うけれども、最近は大きいやつから小さいやつまでやたらと数が多くなったものだ。
そういえば、トリケラトプスってかっこよかった。
恐竜の時代は三畳紀から白亜紀まで、地質時代でいえば中生代、2億5000万年前から6600万年前という約1億8500万年という長い期間だから恐竜も進化を繰り返してどんどん種類も増えてきたわけだ。
興味深いのは、鳥は恐竜から進化したということを大きくクローズアップしているところだ。
たいがいの想像図というのは象の皮膚のような感触で描かれているけれども、実はそこに羽毛をまとったものが多かったというかほとんどが多かれ少なかれ羽毛が生えていたのではないかと考えられている。
その羽根を使ってどのように行動していたかを時代ごとに解説を加えているのだ。最初の羽根の役割は陸上を早く走るための補助動力であった。そのうち、その補助動力を使って木の幹を上るものがでてきた。そこから滑走することを覚えて大空に飛び出した。最新の考察というのはこんな感じだそうだ。
以前の考えでは、鳥の祖先(始祖鳥なんか)は最初から木の上で生活していてそこから滑走することを覚えたと言われていたけれども、爪の形や、元々羽ばたく力を持っていたと思われる筋肉の付き方を総合すると新しい見解が出てくるらしい。
また、一応魚好きの僕にとっては魚の進化も気になる。魚は恐竜ではないのでこの本には直接的には書かれていないけれども、それを食べていたであろう翼竜のことが書かれている。(ちなみに翼竜や海を泳いでいた首長竜は恐竜ではない。)三畳紀の頃の初期の翼竜の奥歯には獲った獲物をすり潰して食べるための歯があったそうだ。それは当事の魚は甲冑のようなエナメル質の装甲で覆われていたのでそうするしかなかったのであるが、時代が下ってジュラ紀の時代になるとそれがなくなったのでただ魚を救い上げて食べるための機能をもった嘴に変わっていく。それは魚自体が今のような鱗に変わってきて飲み込みやすくなって翼竜の姿も変化してきた。魚も明らかに進化をしてきたのだ。
大人の・・・・。というタイトルはどういうところから付けられたのだろうか。今は「ブロントサウルス」という名前の恐竜は存在しないことになっている。ブロントサウルスはアバトサウルスという名前に改名されている。
なぜこういうことが起こるかというと、1800年代後半、化石が見つかると細かく分析することなく学者たちが勝手に名前をつけていたそうだ。ブロントサウルスと名付けられた個体はそれより前にアバトサウルスと名付けられていた個体と同じものだと結論付けられブロントサウルスという名前が消えてしまった。そしてこの二つの恐竜を命名したのは同じ人物だったというから面白い。発掘された1本の歯からでも命名されたものもあったそうだ。そういうことが分類、生態、復元図その他諸々においておこなわれていたということを批判的に書いている。
そんなところが「大人の・・」というタイトルにつながっているのかもしれないが、そこは著者が日本人であるから表現がやわらかだ。「ワンダフル・ライフ」を書いたスティーヴン・ジェイ・グールドなんかはライバルをもっとけちょんけちょんにこき下ろしているから、「大人・・」というにはまだまだ世間ずれしていないようにも思うのだ。著者もサイエンスライターという立場なので学者ほど権威がないという弱点を持っているからかもしれないけれども・・・。
トランプ大統領の大きな支持者であるキリスト教福音派は進化論を否定しているということで知られているが、これだけ精巧に作られてゆく生物を見ていると、確かに神様でなければお創りできないと考えても不思議ではないと思うのである。