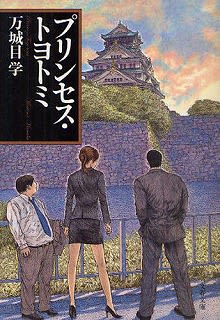万城目学 「プリンセス・トヨトミ」読了
以前に映画版をテレビで放送していたのを観たので、家に置いてあったこの本を読んでみた。個人的な感想だが、映画のほうが出来がよかった。こんな現象も珍しい。大概、映画のほうが面白くないという場合のほうが多いと思うのだが・・・。
映画では、父と子のコミュニケーションの難しさを長い回廊を使って表現されていて、そこを強調して描かれていたが、小説の中ではこのテーマ以外にもさまざまなテーマが提示されているようで、どうもまとまりに欠けているようなきがする。ただの奇想天外小説に終わってしまっているような気がした。
50歳を手前にしたオジサンには、映画が提示するテーマのほうが心に響く。
父親と息子というのはその通り、話したくても話せない。
僕はまだ父親と遅くまで行動をともにしたほうだと思うが、田辺や周参見までの道中、結局他愛もない話で終始して、父親も何か人生訓みたいなものをその与太話に乗せて語りたかったのかもしれないがそれはよくわからないことであった。今に至っては趣味と嗜好がまったく違うわが息子に何を話してやればよいものやら、まったくわからない。
洗面台で顔を洗うとき、水を出す量はもう少し少なくしないと節約にならないよ。と言ってやるくらいが関の山だ。
また、“ジンクス”という言葉の使い方も気になる。この言葉は、「それが起こると悪いことが起こる。」というような意味だと思うのだが、この小説では晴れ渡った富士山を見ると会計監査で大きな不正を見つけることができるのがジンクスだと語られているのはどうもしっくりいかない。この人たちは不正を暴くのが仕事だとしたら、これはジンクスではなくて吉兆だと表現すべきではないのかと、出だしから批判的な面持ちで読んでしまった。今の人にはこれのほうがしっくりくるのだろうか?
あとがき代わりのエッセイで、小説の舞台になった大阪市の谷町界隈は織田作之助や近松門左衛門が生活した場所だと紹介されていたが、開高健もこの辺りの出身で、梶井基次郎はさておきそれを紹介していないというのは、やはり、この作家の嗜好と僕の好みは大分違うのだと納得した。
以前に映画版をテレビで放送していたのを観たので、家に置いてあったこの本を読んでみた。個人的な感想だが、映画のほうが出来がよかった。こんな現象も珍しい。大概、映画のほうが面白くないという場合のほうが多いと思うのだが・・・。
映画では、父と子のコミュニケーションの難しさを長い回廊を使って表現されていて、そこを強調して描かれていたが、小説の中ではこのテーマ以外にもさまざまなテーマが提示されているようで、どうもまとまりに欠けているようなきがする。ただの奇想天外小説に終わってしまっているような気がした。
50歳を手前にしたオジサンには、映画が提示するテーマのほうが心に響く。
父親と息子というのはその通り、話したくても話せない。
僕はまだ父親と遅くまで行動をともにしたほうだと思うが、田辺や周参見までの道中、結局他愛もない話で終始して、父親も何か人生訓みたいなものをその与太話に乗せて語りたかったのかもしれないがそれはよくわからないことであった。今に至っては趣味と嗜好がまったく違うわが息子に何を話してやればよいものやら、まったくわからない。
洗面台で顔を洗うとき、水を出す量はもう少し少なくしないと節約にならないよ。と言ってやるくらいが関の山だ。
また、“ジンクス”という言葉の使い方も気になる。この言葉は、「それが起こると悪いことが起こる。」というような意味だと思うのだが、この小説では晴れ渡った富士山を見ると会計監査で大きな不正を見つけることができるのがジンクスだと語られているのはどうもしっくりいかない。この人たちは不正を暴くのが仕事だとしたら、これはジンクスではなくて吉兆だと表現すべきではないのかと、出だしから批判的な面持ちで読んでしまった。今の人にはこれのほうがしっくりくるのだろうか?
あとがき代わりのエッセイで、小説の舞台になった大阪市の谷町界隈は織田作之助や近松門左衛門が生活した場所だと紹介されていたが、開高健もこの辺りの出身で、梶井基次郎はさておきそれを紹介していないというのは、やはり、この作家の嗜好と僕の好みは大分違うのだと納得した。